不動産売買の物件調査には、物件の所在地にて行う「現地調査」と行政機関にて行う「役所調査」の2種類があります。
なお、現地調査に関しては別記事「不動産の現地調査について解説いたします!」をお届けいたしましたので、本日は「不動産の役所調査(行政調査)について解説いたします!」と題して、役所調査のノウハウをご紹介させていただきたいと思います。

法務局での役所調査
そもそも登記とは「国家が個人や法人の権利を証明する制度」となりますから、売買対象となる土地や建物の真の所有者を調べたり、不動産に設定されている権利を知るためには、法務局での調査は避けて通れないものとなるでしょう。
そして最近では登記事項の調査に際して、法務局がインターネットにて提供している「登記情報提供サービス」を利用している不動産業者さんが殆どであるとは思いますが、実は「法務局に出向いたからこそ得られる情報」も意外に多いものです。
例えば、法務局の窓口において謄本を取得する際に「この土地に他の建物は登記されていませんよね?」と尋ねることにより、取引対象の土地に『既に取り壊し済みにも係らず、滅失がなされていない古い建物の登記が残っている』ことに気が付くことができたなどというお話はよくあるものです。(滅失登記未了の土地に関する詳細については、別記事「建物滅失登記をしていない土地の取引体験記!」をご参照ください)
もちろん、登記情報提供サービスを利用した場合でも「地番から建物を特定」していれば、こうしたミスは防げますが、家屋番号を直接入力して検索をしてしまうとこのようなミスを犯してしまうケースもあるものです。
そこで今回は敢えて、法務局を直接訪問しての調査を前提にお話をさせていただきます。
※1988年の法改正により、登記事務はコンピューターシステム化されることとなり、コンピューター化が完了した法務局で取得する「登記簿の写し」については、登記簿謄本ではなく登記事項証明書と呼ぶのが正しいのですが、不動産業界では未だに「謄本」と呼ばれることが多いため、本書では敢えて『登記簿謄本』の呼称で統一させていただきます。
なお、不動産調査で取得すべき法務局管轄の資料は以下のものとなります。
- 登記簿謄本/土地や建物の権利状況を示す資料
- 公図/土地のおおよその形状と地番を把握するための資料
- 地積測量図/分筆等の登記の際に作成される測量図面
- 建物図面/建物の表示登記に際して作成される建物図面
ある程度の不動産屋さんとしての経験があれば、これらの書類は難なく取得が可能であると思いますので特にご説明することもないのですが、
某大手不動産会社に勤めるキレ者営業マンである管理人の友人は、この調査に際して物件に隣接する全ての土地・建物に関して登記簿謄本を取得するように心掛けているといいます。
もちろんこの方法を行うとなれば、それなりの費用が発生しますし、「そこまでしなくても・・・」と思われるかもしれませんが、これを行うことで『隣接する土地を少々厄介な団体が所有していることが判明した』などというケースもありますから、トラブル回避のヒントになることも確かです。
よって法務局の調査では「経費を惜しまず、あらゆる情報を取得しておくことが肝要」となるでしょう。
また建物図面に関しては、売主さんも記憶に無かった増築未登記部分を発見することがありますので、図面と現況の違いをしっかり見比べておくようにしましょう。
法令上の制限に関する役所調査
さて、ここからは法令上の制限と呼ばれる調査項目についての解説を行ってまいります。
法令上の制限とは「国や地方自治体などが【目指す街づくり】を実現するために、建物の建築や土地利用に関して、各種の法律によって制限を課すこと」を指しますが、こうした制限を見逃せば『不動産の所有者になったにも係わらず、思うとおりの土地利用ができない』といったクレームに繋がることになりますので、決して油断してはならない調査項目となるはずです。
ちなみに多くの自治体では、これらの法令上の制限を一枚の地図に落した図面(都市計画図)を作成し、インターネット上で閲覧できるサービスを実施していますから、調査を行う上で非常に重宝します。
しかしながら、法令上の制限に係わる法令は50種類以上にも及びますから、都市計画図に全ての制限が反映されている訳ではない上、自治体によって反映される情報が異なっている(A市では掲載されていた制限が、B市では反映されていないといった状態)こともありますので、この点には大いに注意が必要となるでしょう。
なお、このような状況に対応するべく私が行っているのは、調査の際に作りかけの重要事項説明書を持ち歩くようにし、役所の担当者に直接重説の書面を見せながら、説明項目を確認をしてもらうという方法です。
この方法なら、調査漏れを防ぐことができるばかりか、不慣れな地域での調査でも「次はどこに窓口に行けば良いか」を的確に教えてもらえますし、「都市計画図に反映されていない法令上の制限がないか?」などの確認も容易になります。
では、この点を踏まえた上で法令上の制限に関する調査のポイントを解説して行きましょう。
都市計画法について
都市計画法においてまず調査すべきポイントは、調査対象地が
- 都市計画区域
- 準都市計画区域
- 規制のないエリア
のどのエリアに属しているかを調べることです。
そして都市計画区域に属している場合には、更に
- 市街化区域
- 市街化調整区域
- 非線引き区域
というエリアの区別がありますが、多くの場合は市街化区域の指定を受けているはずです。
なお、市街化区域における調査では
などが主な調査事項となるでしょう。
建築基準法に関する調査
さて、都市計画法についての調査に続いては、建築基準法について調べることになります。
但し、ここで注意するべきは都市計画法と建築基準法の内容には重複する箇所が多々存在する点です。
実は都市計画法では非常に多くの法令上の制限を定めていますが、『その詳細についは建築基準法による』としているものが数多く存在しています。
よって先程も申し上げた通り、都市計画法と建築基準法の関係を正しく理解していれば、調査内容について混乱が生じることを避け、より効率的に作業を進めることが可能となるのです。
なお、建築基準法における具体的な調査項目は
- 用途地域の制限
- 建ぺい率と容積率
- 建物の高さ、日照に関する制限
- 外壁後退・敷地の最低限度・壁面線の制限
- 防火地域・準防火地域
- 建築基準法上の道路種別
以上のようなものとなります。
その他の法令上の制限
ここまで解説して来た都市計画法と建築基準法上の制限の調査が完了すれば、法令上の制限に係わる調査の半分は終了したことになりますが、まだまだ調べるべきことは存在します。
その他の法令に係わる制限の主なものには
- 宅地造成及び特定盛土等規制法
- 建築協定と地区計画
- 砂防法・地すべり等防止法・急傾斜地崩壊対策法・土砂災害防止法
- 文化財保護法
- 農地法
- 国土利用法
- 土壌汚染対策法
以上のようなものが挙げられるますが、これ以外にも50項目を超える法令についての調査が必要となります。
※調査すべき項目は非常に多いですが、取引対象物件が多数の法令上の制限を重ねて受けるケースは稀です。
※別記事「不動産重要事項説明書作成について解説いたします!」においては、調査が必要となる『その他の法令上の制限』の一覧を掲載しております。
なお、法令上の制限の中には市役所や区役所では管轄していない、国や都道府県扱いの法令もありますので、こうした官庁の所在地を事前に確認し、立ち寄るのに必要な時間を考えた上で、調査日程を組むのがおすすめです。
道路に関する役所調査
役所調査においては、物件が接する道路についても調査すべき事項が多数あります。
道路種別の調査
まず最初に確認するべきは「前面道路が建築基準法上の道路であるか否か」という点であり、これに該当するのならば「どの道路種別に該当するのか」という点も確認しましょう。
自治体の担当部署に出向けば、道路種別ごとに色分けされた地図の閲覧が可能なケースが多いですし、地域によってはインターネット上で情報を公開している場合もあります。
なお、建築基準法上の道路には公道・私道の両方がありますし、一見立派な道路に見えても、実は(建築基準法上の)道路ではないケースもありますのでご注意ください。
2項道路の場合の調査
前項の調査において、前面道路が建築基準法42条2項の道路であった場合には、建物を建築する際に「セットバック(敷地後退)」が必要となってくる可能性があります。
こうしたケースにおいては、「道路中心線の位置」と「想定されるセットバック面積、後退すべきライン」を調査する必要が生じるのです。
なお、これらの事項を調べるためには物件に隣接する建物の建築概要書などを取得する必要がありますが、詳細につきましては別記事「2項道路とセットバックについて解説いたします!」および「道路中心線とは?その決め方や調査方法を解説致します!」をご参照ください。
道路区域線図の取得
さて、調査対象の不動産が公道に面している場合には、自治体の担当部署にて道路区域線図(道路査定図)を取得しなければなりません。
道路区域線図とは「自治体等が管理する道路と、これに接する民間の土地の敷地境界を示した図面」となります。
近年では、境界トラブルを防止するために取引対象物件と隣接地の境界を確定した上で売買を行うのが通常ですが、公道に面した物件については自治体(官庁)とも境界の確定が行われているのが望ましいでしょう。
※土地の分筆などが取引の前提ではない場合には、公道との官民境界が定まっていないまま売買が行われるケースも珍しくありません。
なお、私道については当然ながら道路区域線図は存在しませんので、「私道に供されている土地」と「取引対象物件」の間で民地同士の境界確定を行うことになります。
道路の舗装について
物件の前面道路が公道の場合には、舗装の等級についても調べておきましょう。
こちらも自治体の担当部署にて台帳の閲覧なケースが多く、路線ごとにアスファルトの厚さや、掘削制限の有無などが記されています。
たとえ掘削制限がある道路でも、建物を建築する際には許可が下りる場合が殆どであるため、重要事項の説明で告知を行うことは稀ですが、舗装等級によっては引込み工事等に通常以上の費用を要するケースもありますので念のため確認をしておくべきです。
接面道路が私道である場合
接面道路が私道である場合には「通行や掘削の承諾が取れているか」についてもチェックが必要となります。
私道とは文字通り、民間人が所有する土地を道路として提供したものとなりますから、「通行する」にも「水道管等の工事(掘削工事)を行う」のにも関係権利者の承諾を得なければなりません。
そこで、私道に面する物件を売買する際には「道路の通行や掘削を私道の関係権利者全員が承諾していることを証する書面(覚書等)」を買主に交付するのが通常です。
よって、こうした書面が存在していない物件については、関係権利者と協議の上、通行・掘削の承諾書を作成する必要があるでしょう。
※売買対象物件に私道部分の土地が含まれている(売主が私道の土地を所有している)場合でも、他に私道の権利関係者いれば「通行・掘削の承諾書の作成が必要」となります。
※私道の関係権利者全員の承諾が得られない場合には、買主がこれを容認するか否かで取引の成立・不成立が決定することになるでしょう。
道路調査について更に詳細な情報が必要な方は、別記事「不動産の道路調査について!」をご参照ください。
★当ブログ管理人執筆の電子書籍(kindle)のご紹介!是非ご一読ください!★
 | 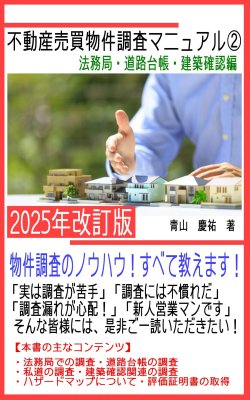 | 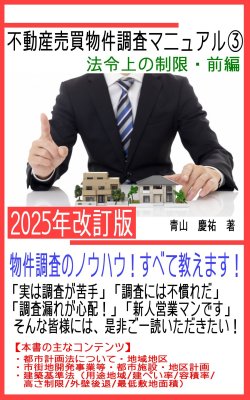 | 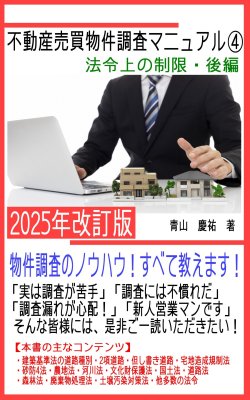 |
水道・下水・ガスの埋設管についての役所調査
水道や下水、ガスなどの「インフラ設備に係わる調査」は役所調査の中でも最重要項目の一つとなりますので、じっくりと解説を行っていきましょう。
水道について
水道についての調査は地域を管轄する水道局などで行うものとなり、前面道路に敷設されている「本管」、そして物件へと水を供給する「引込管」の管径や材質、そして引込工事を予定している場合には「本管からの分岐が(容量的に)可能であるか」などについて調べていきます。
なお、この調査においては隣家からの(隣家への)配管越境などが発覚する場合もありますし、宅地内の切り回しに鉛管が使用されていることが明らかになることもありますので、慎重に調べを進めて行きましょう。
また、前面道路が私道である場合には敷設されている本管が公設本管(自治体が管理する本管)ではなく、私設本管(民間人が管理する本管)である可能性があります。
私設本管については、引込管を分岐する際に所有者の承諾が必要となりますのでご注意ください。
下水について
下水については原則として、前面道路に敷設されている本管の位置と管径のみを調べれば役所調査は完了となります。
実は下水を管理する行政にも各宅地への引込管についての資料は残されておらず、正確には「調べたくても調べることができない」というのが実情です。
ただ、それ故に下水の引込管の位置がわからず、配管越境を見逃してしまうケースも少なくありません。
よって、引込管の位置がわからない場合や、隣地からの(隣地への)配管越境が疑われる場合には、現地で下水枡の蓋を開けて配管経路を確認する調査を行わねばならない場合も少なくないのです。
また、前面道路が私道である場合には、下水本管についても私設本管である可能性がありますので、新築工事に際して引込管と本管の接続工事を予定している場合には関係権利者の承諾が必要となるでしょう。
ガスについて
都市ガスが普及していない地域においては、プロパンガスが使用されているはずですので、原則としてガスの配管調査は不要となります。
また、都市ガスの場合でも各地のガス会社が配管の位置などについては詳細な資料を保管していますので、ガスの配管は最も調査が容易な設備と言えるでしょう。
但し、水道や下水と同様にガス管も、私道に面した物件の場合は掘削工事などに際して承諾が必要になる点にご注意ください。
電気について
電気に関しては、電柱を経由して電線にて引込みが行われている地域が殆どであるかと思いますが、こうした引込み電線が他人の土地の上空を通過(空中越境)していると後々トラブルに発展する可能性がありますので注意が必要です。
また敷地内に電柱がある場合には、「その所有者や管理者が誰なのか」といった事項についても確認しておく必要があるでしょう。
建築確認についての役所調査
都市計画区域や準都市計画区域においては、建物を建てる際に行政からの建築許可(建築確認)を取得することが義務付けられていますので、役所調査においては「建築確認に関する事項」も重要なチェック項目となります。
取引対象の建物に関する調査
既にお話しした通り、不動産取引の対象となる地域の多くでは、建物を建築する際に「建築確認」と呼ばれる行政の建築許可を取得する必要がありますので、まずは『売買対象物件がしっかりと建築確認に関する手続きを完了しているか』という点から調べていきます。
ちなみに建築確認の手続きは、建築計画の申請(建築確認申請)を行った上、完成した物件について検査(完了検査)が行われ、これに合格すると検査済証という書面が交付されるというのが一連の流れとなります。(建物によっては中間検査が行われることもある)
建築確認済証や検査済証は原則として売主が保管しているはずですが、古い建物の場合には紛失していまっているケースも多いので、自治体の担当部署に赴いて「建築概要書(建築確認の内容の概要が記された資料)」や「台帳記載証明(建築確認済証や検査済証の交付を証明する書面)」を取得する必要があるでしょう。
※建築確認は自治体が許可するものとなりますが詳細な図面等は保管していないのが通常ですので、売主が建築確認済証を紛失している場合には、建築概要書が建築確認に関する唯一の資料となるでしょう。
※築年数が古い物件(昭和50年代の建築物等)に関しては、建築概要書も保管されいないケースがあります。
なお、物件の中には建築確認は取得しているが、完了検査は受けていないという物件もありますので、こうした物件では買主に対してその事実を告知する必要があります。
工作物に関する役所調査
取引対象物件に関する建築確認の役所調査については前項で解説いたしましたが、物件の敷地内にブロック塀や擁壁(土留め)、地下車庫等の工作物がある場合にはこれらについても調査が必要となります。
ブロック塀や土留めに関しては、設置する際に開発許可や宅地造成の許可、あるいは建築確認を取得しているケースがありますので、こうした記録が役所に残されているかを確認しなければなりません。
※これらの許可等を取得していると、工作物の構造や強度が一定の水準に達していることの根拠となります。(ひび割れ等の劣化がある場合にはこの限りではありませんが)
また、地下車庫についても「建築確認等を取得しているか否か」を説明しなければなりませんので、しっかりとチェックしておきましょう。
ちなみに擁壁等については隣接地の敷地内にあるものでも、倒壊した場合に取引対象の土地に被害が及ぶ可能性があれば、「開発許可等に基づいて設置されたものあるか否か」、「ひび割れ等の劣化が認められない」などの点について説明が必要になります。
なお、擁壁についての詳細は別記事「宅地造成と擁壁について解説いたします!」にて、地下車庫については別記事「地下車庫の建築確認や費用、注意点等について解説致します!」にて詳細な解説を行っておりますので、是非こちらもご参照ください。
近隣の建築計画の調査
建築確認の役所調査においては、取引対象物件の周辺における建築計画をチェックすることも重要な作業となります。
例えば、取引対象物件の隣にある大きな空き地などにマンションの建築計画等があるにも係わらず、これを告知せずに売買を行えばクレームになるのは必定ですよね。
自治体の建築確認担当部署に赴けば、周囲の建築確認取得済み物件を示した地図等の閲覧が可能なケースもありますので、こうした資料には必ず目を通しておくべきです。(台帳がない場合には、役所の担当者に直接質問してみましょう)
また、たとえ戸建ての建築計画でも、取引対象のお隣りなどの場合には騒音等の問題が生ずることもありますし、買主が新築工事を計画しているケースでは、隣家と施工時期がバッティングして工事に着手できないこともあり得ますので、こちらも重要事項の説明に反映させるべきです。
洪水・液状化などハザードマップ系の調査
近年、世間では災害に対する危機意識が高まっていますが、不動産の取引においても災害に関する告知を行う必要があります。
そして、この告知の根拠となるのが自治体発行のハザードマップです。
これらの資料はインターネットなどでも閲覧が可能ですが、地域によって様々なパターンのマップが用意されていますから、後から買主に「こんなハザードマップの存在を知っていたら、この物件を買わなかった!」などと言われないよう、液状化マップなど普段あまりに気に掛けないマップについてもしっかり資料に添付しておくべきしょう。
ちなみに、2020年の宅地建物取引業法の改正においては水防法における洪水ハザードマップを重要事項説明において取り扱うことが義務化されておりますので、この点には充分にご注意ください。
埋蔵文化財
埋蔵文化財の調査は、「古墳や貝塚などの遺跡が売買対象物件の地下に埋蔵されていないか」のリサーチであり、建築工事中に遺跡が出た場合などは、工事が完全に止まってしまうことになりますので要注意の事項です。
また埋蔵文化財を管轄しているのは、行政の中でも教育委員会などの特殊なセクションとなりますから、見落としが無いようにしましょう。
分譲マンションにおける管理組合・管理会社への調査
ここまで役所調査についてご説明してきましたが、分譲マンションの仲介する際には管理組合や管理会社についても調べておくべき事項があります。
例えば「月々の管理費や修繕積立金の金額」、そして「これらの値上げが管理組合で協議されているか否か」、そして「近い将来に大規模修繕が計画されていないか」、「今後はどのようなスケジュールで修繕が行われて行く予定なのか」などの点も、買主へ必ず説明しておくべきでしょう。
そして、こうした項目の調査に欠かせないのが
- 重要事項調査報告書
- 管理規約
- 長期修繕計画書
- 総会議事録
などの資料となります。
重要事項調査報告書や長期修繕計画書、そして管理規約については、管理会社に依頼すれば有料で入手できますが、総会議事録は売主が保管していない場合、「管理人室などで閲覧させてもらう」といった方法でしか確認ができませんのでご注意ください。
行政調査まとめ
さてここまで、役所調査(行政調査)に関するポイントや注意点などをまとめてまいりました。
これまでの解説をお読みいただければ、役所調査の流れや要点は一通り網羅したことになるはずです。
なお役所調査においては、自治体によって役所の担当部署の名称や、一つの部署が管轄する業務の範囲が異なっていることも多いため、本記事でご説明する手順どおりに調査を進められないケースもあるかもしれませんが、
調査の要点をしっかりと把握していれば臨機応変な対応が可能となるはずですから、手順を丸覚えするのではなく「何を調べるのがポイントであるのか」を意識しながら本記事をご活用いただければと思います。
但し、不動産の物件調査は非常に奥の深いものとなりますから、この記事で得た知識のみで重要事項の説明に臨むのは「まだまだ危険である」というのが実情でしょう。
そして、「行政調査について更に深い知識を身に付けたい」という方に向けては、管理人が出版しているアマゾン・Kindleの電子書籍がおすすめとなりますので、以下で少々ご紹介をさせていただきます。
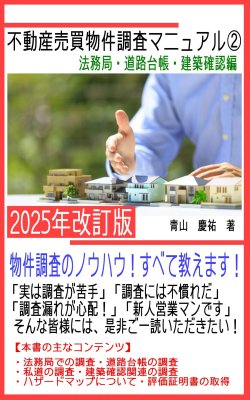
まず最初にご紹介する上記の書籍では、法務局・道路台帳・建築確認関連の調査ノウハウを解説したものとなります。
また、記事の中でもお話しした通り、法令上の制限については50種類にも及ぶ法令を解説することになりますので、下記の前編・後編2冊に分けて調査のポイントをご紹介してありますので『調査において失敗をしたくない』という方は、是非一度お目通しをいだだければ幸いです。
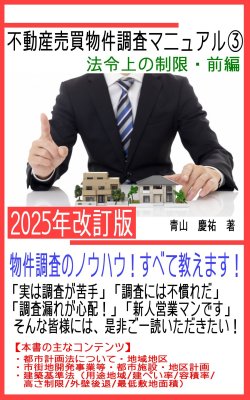
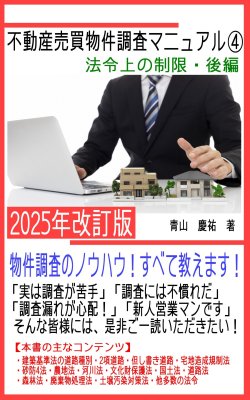
役所調査においてミスを犯した場合には、購入者から「これでは物件を購入した意味がない!」というヘヴィなクレームが寄せられることも珍しくありませんから、しっかりと知識を身に付け、自信を持って重要事項の説明にあたりたいものですよね。
ではこれにて、「不動産の役所調査(行政調査)について解説いたします!」の知恵袋を閉じさせていただきたいと思います。