近年、耳にする機会が多くなったのが「ゲリラ豪雨」や「爆弾低気圧」などのワードとなります。
そして、ゲリラ豪雨などが発生した後には「河川の増水や土砂災害などの痛ましいニュース」が飛び込んでくるケースが多いですから、住宅の購入などに際しては最大限の注意を払う必要があるでしょう。
そこで本日は「土砂災害対策の法律について解説します!」と題して、こうした土砂災害のリスクから私たちの生活を守る砂防4法についてお話をしてみたいと思います。

土砂災害対策の法律について
冒頭にて「砂防4法」なる用語が出てまいりましたが、『一体何のことだろう?』とお思いの方も多いはずです。
実は我が国では、国民を土砂災害の被害から守るべく、
という4つの法律が定められており、これらの法律を「砂防4法」と称しています。
また砂防4法は、マイホームを購入する場合などに行われる「重要事項説明」の中で必ず扱うべき事項と定められていますので、不動産の購入経験がある方なら『一度は耳にしたことがあるはずの法律』なのです。
しかしながら実際には、重要事項説明の中でサラリと流されてしまうことも多いですし、実は説明する不動産業者も法律の内容をしっかりと把握していないといった事情から、「これらの法律の存在がまだまだ一般の方々に浸透しきれていない」というのが実情でしょう。
但し、これらの法令は自分や家族の生命、そして財産にも直接関わってくる内容となりますから、『知らなかった』では済まされませんよね。
そこで本項では、各法令の特徴や相違点などに着目しながら、砂防4法の概要をガッチリと解説して行きたいと思います。
ちなみに、土砂災害には、
- 土石流/渓流に蓄積された土砂が、豪雨や降り続く雨によって押し流される現象
- 地すべり/地下水などの影響で地中の脆い地盤がゆっくりと滑り出す現象(なだらかな傾斜の地形で起こりやすい)
- がけ崩れ/地震や豪雨などで地盤が緩み、一気に斜面が崩れ落ちる現象
以上3つの種類があり、種類によって対策を行う法律も異なっておりますので、これを念頭に置いた上で以下の解説を読み進めてください。
砂防法
まず最初にご紹介するのが砂防法という法律です。
この法律は明治30年の施行という非常に古い法律となりますが、細かな改正を繰り返しながら未だに現役で私たちの生活を見守ってくれています。
そしてその内容はと言えば、国土交通大臣が「崩壊の危険(土石流発生の危険)あり」と判断した場所を区域指定(砂防指定地)する ことが可能であり、指定されたエリアでは建物・工作物の新築や開発行為等について都道府県知事の許可が必要となるのです。
なお、この砂防法の指定区域の周辺は「土砂災害のリスクが非常に高いエリア」となりますから、土地の購入などを考える際には基本的に避けるべき場所となります。
但し、砂防法の指定は規模の大きな渓谷や崖地がメインとなりますから、通常の不動産取引ではあまり縁のない法令と言えるかもしれません。
- 対象の災害/土石流
- 区域指定/砂防指定地
- 制限される行為/盛土や切土、建物や工作物の設置、鉱物等の採取、樹木の伐採等(自治体ごとの条例によります)
- 区域指定権者/国土交通大臣
- 制限行為の許可権者/都道府県知事
地すべり等防止法
続いてご紹介するのが地すべり等防止法という法律です。
こちらは砂防法よりも若干新しい法律で昭和33年に施行されており、国土交通大臣及び農林水産大臣は「地すべり防止区域」や「ぼた山崩壊防止区域」といった区域の指定ができる旨を謳っています。
そして地すべり防止区域では、工作物の設置、地下水排除の阻害、地表水浸透の助長等について都道府県知事の許可が必要です。
一方、ぼた山崩壊防止区域では樹木の伐採・一定規模以上の切土・土石の採集等の行為に関して、知事の許可が必要となります。
ちなみに「ぼた山」とは鉱石などの採掘に際して出てきた土や岩を積み上げた山のことを指す言葉となりますから、かなり限定された地域にのみ指定される区域となるでしょう。
- 対象の災害/地すべり
- 区域指定/地すべり防止区域、ぼた山崩壊防止区域
- 地すべり防止区域で制限される行為/工作物の設置、地下水排除の阻害、地表水浸透の助長、一定規模以上の切土・のり切等
- ぼた山崩壊防止区域で制限される行為/樹木の伐採、土石の採集、一定規模以上の切土・のり切等
- 区域指定権者/国土交通大臣、農林水産大臣
- 制限行為の許可権者/都道府県知事
★当ブログ管理人執筆の電子書籍(kindle)のご紹介!是非ご一読ください!★
 |  |  | 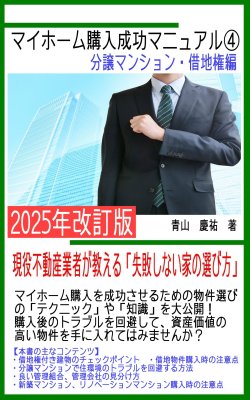 |
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地崩壊対策法)
さて次にご紹介するのが、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」なるものとなります。
同じような法律が出て来るので混乱してしまいそうですが、この法律が目的としているのは「がけ崩れ」への対策であり、特徴的なのが『警戒区域を指定するのは都道府県知事である』という点です。
実は前項までにご紹介した2つの法律では、国土交通大臣や農林水産大臣が区域指定を行うルールでした。(一定の行為に許可を与えるのは知事ですが)
そしてここで注目すべきなのは、大臣と都道府県知事とでは「身近さ」が全く異なるという点です。
つまり、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律にて指定される「急傾斜地崩壊危険区域」は、私たちの極身近に存在する上、想定される災害の規模も小さなものとなります。
さて、このような言い方をすると「規模が小さいなら安心だ」などと思われるかもしれませんが、たとえ家が一軒でも崖の上から流されてくれば大事件となりますし、そのような危険エリアが近所に何か所もあるというのは、むしろ非常に恐ろしいことですよね。
また、実際に市場で流通している物件の中にはこの「急傾斜地崩壊危険区域」の指定を受けているものも少なくありませんから、不動産の取引においては是非ご注意いただきたい思います。
なお、この区域に指定された土地を購入した場合には、土砂災害防止に必要な措置を行うことが所有者に義務付けられますし、工作物の設置や樹木の伐採、盛土・切土等を行う場合には知事の許可が必要です。
※急傾斜地崩壊対策法に基づいて自治体が行う崖の補強工事について恩恵を受ける者(工事によりメリットが得られる者)には、負担金が発生することもあります。
ちなみに、急傾斜地崩壊対策法の対象となるのは「5m以上の崖」であり、これよりも低い崖(5m未満の崖)については各自治体が「崖条例」にて制限を課しています。
- 対象の災害/がけ崩れ
- 区域指定/急傾斜地崩壊危険区域
- 制限される行為/水の放流、盛土・切土、工作物の設置、樹木の伐採等
- 区域指定権者/都道府県知事
- 制限行為の許可権者/都道府県知事
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)
そして最後にご紹介するのが、これまた都道府県知事が危険エリアの指定を行う土砂災害防止法となります。
こちらも土砂災害の被害を防止するのが目的の法律となりますし、『知事が指定を行う』という点から私たちの身近に指定区域が存在していることをご理解いただけると思いますが、これまで解説してきた「砂防法」「地すべり等防止法」「急傾斜地崩壊対策法」という3つの法律との最大の違いは災害が発生する状況です。
既にご紹介して来た3つの法律は指定された場所自体が災害時に崩れ落ちるリスクが高いエリアとなりますが、土砂災害警戒区域は『崩れて来た土砂が降り注ぐ場所』となります。
つまり、砂防法・地すべり等防止法・急傾斜地崩壊対策法が災害の発生防止を目的にしているのに対して、「土砂災害防止法は被害を最小限に止めるための法律」となっており、この法律だけが明らかに異なる性質を有しているという訳なのです。
なお、土砂災害防止法においては
- 対象の災害/土石流・地すべり・がけ崩れ
- 区域指定/土砂災害警戒区域(イエローゾーン)、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
- 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)で制限される行為/特になし
- 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)で制限される行為/開発行為、建築行為、建物の移転勧告等
- 区域指定権者/都道府県知事
- 制限行為の許可権者/都道府県知事
以上のようなルールが定められています。
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)においては「土砂災害の危険がある」という警告のみとなっていますが、
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)においては住宅(自宅を除くアパート等)・学校・病院・介護施設等の建築に際して知事の許可が必要となる上、建物自体の構造についても基礎の強化や一部を鉄筋コンクリート造(RC造)としなければならないなどの制限が課せられるのです。
また、自治体から移転勧告が出された場合には住宅金融支援機構などからの融資を優先的に受けることができますが、所有する物件の資産価値は非常に低いものとなってしまうでしょう。
土砂災害危険箇所
そして、最後にご紹介するのが土砂災害危険箇所という指定地域となります。
このようなお話をすると「あれっ?砂防4法じゃないの?」と思われるかもしれませんが、実はこの土砂災害危険箇所は法律に基づくものではなく、各自治体が独自に土砂災害の危険個所を周知しているだけのもの(行為の制限等は一切ありません)です。
但し、マイホームの購入などに当たっては、こうした危険区域の存在は絶対にチェックしておきべきものとなりますので、本記事の主旨からは少々脱線するのを覚悟で掲載させていただきました。
スポンサーリンク
土砂災害対策の法律まとめ
さてここまで、土砂災害に関わる砂防4法について解説を行ってまいりました。
もちろん、海沿いの平坦な物件にお住いの方などについては、全く係わりのないお話でしょうが、高低差のある山間の地域にお住いの方にとっては「非常に重要な問題」となるはずです。
また、これらの法令により指定された地域から外れているからと言っても、決して安心はできません。
たとえ自分の家が指定対象外でも、通勤に使うルートやお子様の通学路上に「こうした指定区域がない」とは言い切れないはずです。
当然、まともな不動産業者であればこうした指定区域に関する説明はしっかりとしてくれるはずですが、物件周辺の状況まではその目が及ばないケースもあるでしょうから、
マイホームを購入される際にはハザードマップなどを活用して「購入者ご自身の目でも土砂災害の危険地帯が近隣にないかの確認をするべき」でしょう。
ちなみに、砂防4法と似た言葉で「砂防3法」というものがあり、こちらは「砂防法」「地すべり等防止法」「急傾斜地崩壊対策法」の3つを法律を指します。
既にお話しした通り、土砂災害防止法だけは他の3法と異なる性質を持っているため、こうした区分が作られているようですので、この機会に是非覚えておいていただければ幸いです。
ではこれにて、「土砂災害対策の法律について解説します!」の知恵袋を閉じさせていただきたいと思います。