不動産の販売図面や、売買契約前の重要事項説明書などで見ていると「防火地域」「準防火地域」というワードを目にすることがあります。
字面を見るだけでも、「消防や火災に係わる用語なのだろうな・・・」という予想は付きますが、『その詳細をご存知?』と問われた際には、不動産業者さんの中にも苦笑いを浮かべる方がいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで本日は「防火地域・準防火地域とは?わかりやすく解説いたします!」と題して、火災の被害から私たちの生活を守る、こちらの法令上の制限について解説をさせていただきたいと思います。

防火地域・準防火地域って何だろう
ではまず、「そもそも防火地域・準防火地域とはどのようなものなのか?」という点から、お話をスタートさせましょう。
防火地域や準防火地域は、都市計画法という法律が定める「地域地区」という制度の一つとなります。
※地域地区の詳細は別記事「地域地区とは?わかりやすく解説いたします」をご参照ください。
但し、都市計画法という法律はあまり細かな取り決めは行わず、「詳細は●●法による!」というのがお決まりのパターンであり、この防火地域・準防火地域についても『詳細は建築基準法による』としていますから、
防火地域・準防火地域は「都市計画法上のルールではあるが、具体的な内容は建築基準法によって定められた制限を受けるエリア」となります。
なお、防火地域や準防火地域の指定を受けたエリアでは、
火災による被害を最小限に抑えることを目的に「建築される建物に一定の耐火性能を備えること」が義務付けられる
のがルールです。
ちなみに、防火地域は「準防火地域よりも、求められる防火性能のハードルが高いエリア」となることを覚えておいてください。
では、次項より更に具体的に防火地域と準防火地域の内容を見ていきましょう。
防火地域の建築制限
先程もお話しした通り、「準防火地域」よりも厳しい防火性能(最も厳しい防火性能)を求められるのが『防火地域』となります。
よって防火地域の指定がなされるのは、建物が密集している駅前などのエリアや、大規模な火災が発生した際に緊急車両が往来することになる幹線道路沿い等が多いようです。
なお、具体的な制限の内容については
耐火建築物
- 延べ床面積100㎡超で耐火建築物
- 延べ床面積100㎡以下で耐火建築物または準耐火建築物
と定められています。
ちなみに「耐火建築物」とは、
ドアや窓といった開口部に防火扉などが設置されている上、火災が発生した場合でも倒壊することのない構造を有した建物
を指す用語となりますから、鉄筋コンクリート造の建物などをイメージしていただくとわかりやすいかもしれません。
但し近年では、建築技術の進歩によって木造であっても耐火建築物と認定される建物を建築することが可能となっています。
これに対して、「準耐火建築物」とは
耐火建築物ほどではないものの、これに準ずる耐火性能を持った建物
ということになります。
準防火地域の建築制限
一方、防火地域よりも基準が緩い準防火地域では、
耐火建築物
- 延べ床面積1500㎡超で耐火建築物
- 延べ床面積が500㎡超~1500㎡以下で耐火建築物または準耐火建築物
- 延べ床面積が500㎡以下の建物も耐火建築物または準耐火建築物、技術的基準適合建築物
※技術的基準適合建築物とは準耐火建築物に準じる耐火性を備えた建物のことです。
- 延べ床面積1500㎡超は耐火建築物
- 延べ床面積が500㎡超~1500㎡以下で耐火建築物または準耐火建築物
というルールになっています。
★当ブログ管理人執筆の電子書籍(kindle)のご紹介!是非ご一読ください!★
 |  |  | 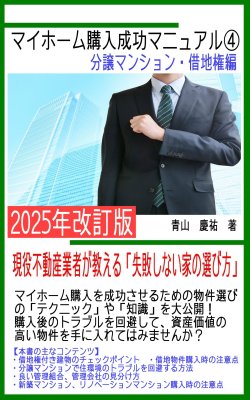 |
防火地域・準防火地域にまたがる物件
さて、ここで気になるのが「防火地域と準防火地域にまたがっている物件は、どちらの制限が適用されるのか?」という点になるかと思います。
そして結論から申し上げれば、
常に制限の厳しい地域、つまり「防火地域の制限が適用される」
ことになります。
なお、建ぺい率や容積率などのケースでは異なるエリアに物件またがる場合には「案分計算」が用いられるため、混同しやすいところではありますが、防火地域・準防火地域ではたとえ僅かにエリアがまたがったケースでも『常に厳しい方の制限』が適用されるのです。
ちなみに「防火地域と未指定のエリア」がまたがった場合は、当然のことながら『防火地域の制限が適用される』こととなり、
「準防火地域と未指定のエリア」がまたがったケースも『準防火地域の制限が適用』となります。
法22条区域
さて、防火地域や準防火地域の具体的な定めを行っている建築基準法には、法22条区域という「もう一つの防火に係わるルール」が存在しています。
※法22条区域については都市計画法上の定めはなく、建築基準法単体のルールとなります。
そして法22条区域では
建物の屋根などに対して一定レベルの防火性能が求められる
ことになりますが、防火地域や準防火地域の制限の厳しさに比べれば「かなりソフトな内容」といえるでしょう。
また原則として法22条区域は「防火地域や準防火地域の指定がなされていない地域に指定される」ことになります。
不動産売買における注意点
ここまで防火地域や準防火地域の制限の概要についてお話をしてまいりましたが、実際に不動産売買を行う際にはどのような点に注意が必要となるのでしょうか。
既に解説した通り、これらのエリアで建物を建築する場合には、耐火建築物や準耐火建築物といった仕様にしなければならないケースがありますが、ここで最も問題となるのは建築コストの問題です。
ご存知の通り、木造住宅よりも鉄筋コンクリート造の建物の方が建築単価は高額となるものですし、同じ木造でも未指定エリアの仕様と防火・準防火仕様の建物とでは「相当なコストの差」が出てきます。(準防火仕様と防火仕様でもコストはかなり変わってきます)
よって、建物の新築に際して「未指定のエリアを想定して建物の見積もりを取っていた場合」には、
防火地域で同じ建物を建てようとした場合に『建築費用に大きな差異が生じる』
ことになりますし、
中古物件の購入に際しては
建替えようと思ったら「驚く程高額な見積もりが出てきた」
というケースも珍しくありませんので、不動産の購入時には防火地域・準防火地域など法令上の制限をしっかりと確認した上で、意思決定を行う必要があるのです。
スポンサーリンク
防火地域・準防火地域まとめ
さてここまで、防火地域と準防火地域についてお話をしてまいりました。
重要事項の説明などでは、案外サラリと流されてしまうこちらの制限ですが、じっくりと掘り下げてみると「意外に奥が深い」ことにお気付きいただけたのではないでしょうか。
火災に対する備えは、都市を整備する上で非常に重要なポイントとなりますから、不動産の取引に際しても充分な注意を払いながら計画を進めて行きたいところです。
ではこれにて、「防火地域・準防火地域とは?わかりやすく解説いたします!」の知恵袋を閉じさせていただきたいと思います。