マイホームの購入に際しては「物件の価格」についてはもちろんのこと、「土地の面積や形状」や「住環境」など実に様々な事柄を検討しなければならないものです。
そして住環境に関しては、「とにかく利便性重視!」という方もいらっしゃれば、「少しでも環境の良い立地の物件を購入したい」という方も多いことと思いますが、
『良好な住環境と抜群のコストパフォーマンスを両立させたい』という方に是非ともお勧めしたいのが、市街化調整区域に建てられた建売りや中古物件となります。
但し、このようなお話をしても「市街化調整区域って何だろう」という方も多いでしょうし、「市街化調整区域の物件を買って、建て替えや売却ができるのだろうか?」と不安を感じる方もおられることでしょう。
そこで本日は「市街化調整区域の建て替えや物件購入について解説いたします!」と題して、皆様の市街化調整区域に関する疑問にお答えして行きたいと思います。

市街化調整区域とは
では、まず最初に「市街化調整区域とは一体どのような地域であるか」という点からご説明を始めていくことにいたしましょう。
我が国「日本」では、国土の効率的な利用を行うために都市計画法という法律にて、
- 都市計画区域(都市として整備・開発をしていくエリア)
- 準都市計画区域(無秩序な開発を防ぐために一定の制限がされたエリア)
- 規制のないエリア(特に制限のないエリア、都市計画区域外)
という3つのエリアが定められています。
更にこの法律では都市計画区域について、
- 市街化区域 ・・・市街化を積極的に行う区域
- 市街化調整区域・・・市街化をしない区域
- 非線引き区域 ・・・特にプランを定めない区域
という地域分けを行っています。
よって市街化調整区域は「原則として市街化を行わない地域」となりますので、学校や病院などの「公共施設」や「農業に従事する方の住宅」等を除いて原則として宅地分譲などの開発行為が行えない地域となっているのです。
※自治体からの開発許可が得られれば「建物の建築等」が可能になりますが、原則として市街化をしない地域だけに簡単に許可を下ろすことはありません。
市街化調整区域の開発制限の歴史
なお、前項の解説をお読みになった方の中には『知り合いに市街化調整区域で新築の建売を買った人がいるのだが、これは一体どういうこと?」との疑問が頭に浮かんでおられる方もいらっしゃることと思いますが、
実は市街化調整区域においては1974年(昭和49年)の都市計画法改正以来、長きに渡って
「既存宅地制度(既存宅地確認制度)」と呼ばれるルールによって、自由に建物の建築や宅地分譲を行うことのできるエリアが存在していた
のです。
※「既存宅地」とは都市計画法の施行によって市街化調整区域に指定される以前から、既に住宅地として利用されていた土地を指す言葉となります。
※既存宅地制度においては、自治体の開発許可を受けることなく建物の建築等が可能となっていました。
しかしながら「出る杭は必ず打たれる」もので、2006年(平成18年)には行き過ぎた市街化調整区域の開発行為に行政からの『待った』が掛かります。
この年、政府は既存宅地制度の廃止を決定し、
これ以降は「市街化調整区域内での開発行為」には原則として許可が必要というルールに変更
されたのです。(通常の理由では許可が下りることはありません)
さて、ここまでのお話を聞くと「それではもう、調整区域で住宅を建てることはできないの?」と思われてしまいそうですが、そうとばかりは言えません。
実は既存宅地制度の廃止に伴い、各地方自治体から「市街化調整区域の開発を禁止しては、地域の過疎化が更に加速するのでは?」という不安の声が噴き出したのです。
そこで「既存宅地制度の廃止」と入れ替わりに誕生したのが、
都市計画法第34条11号の規定による新たな開発許可区域
となります。
※改正後の都市計画法第34条11号における「市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であって、おおむね五十以上の建築物が連たんしている地域」については条例によって開発が許可されるという条文が、自治体による開発許可区域の根拠となっています。
そしてこちらの制度においては、市区町村などの自治体が独自に許可区域の指定を行い、この区域に属するエリアにおいては一定の基準を満たす建物であれば原則として建築が許可されることになっていますから、むしろ既存宅地制度の頃よりも盛んに市街化調整区域の開発が行われる結果となっているのです。
ちなみに、都市計画法第34条11号の開許可区域における開発のルールは各自治体によって異なりますが、下記のようなルールで運用を行っている地域が多いでしょう。
- 原則として誰でも建築が可能(親族要件なし)
- 土地の登記上の地目が平成18年以前から「宅地」であること
- 住宅や建売分譲住宅であること
- 自治体が定める建築基準や最低敷地面積などをクリアしていること
ただ現在では「あまりに市街化調整区域の開発が進み過ぎた」との理由から、第34条11号の指定区域を廃止したり、エリアを狭める自治体も出て来ていますので、今後は再び市街化調整区域の開発が下火になっていく可能性もあるでしょう。
※本項でご紹介した都市計画法第34条11号の指定区域以外にも、「旧住宅地造成事業に関する法律」により開発が行われた区域では開発行為が可能となっています。
★当ブログ管理人執筆の電子書籍(kindle)のご紹介!是非ご一読ください!★
 |  |  | 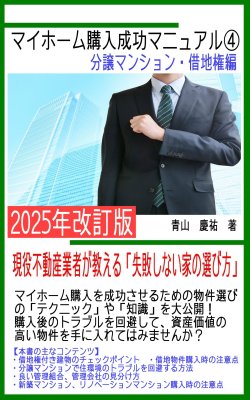 |
市街化調整区域での建て替え・物件購入のメリット・デメリット
これまでの解説にて「市街化調整区域についての基礎知識」はバッチリと身に付けていただけたことと思いますので、本項ではより具体的に市街化調整区域における建て替えや物件購入のメリット・デメリットについて考えて行くことにいたしましょう。
市街化調整区域での建替えや物件購入時の利点とポイント
市街調整区域の物件を購入する際の最大のメリットは、何と言っても抜群の住環境となります。
これまで解説してきた通り、市街化調整区域では自由な開発を行うことができませんので、大きなマンションや商業施設が建つ可能性は殆どありませんから、将来に渡って平穏な住環境が維持されるはずです。
なお、実際にこれから市街化調整区域の物件を購入するとなれば都市計画法第34条11号の開発許可区域に存する物件を購入するべきですが、この区域においても建築等には大きな制約が課せられますから住環境の悪化を懸念する必要はあまりないでしょう。
また、こうした地域だけに物件の販売価格は低めの設定がなされますし、固定資産税等の評価額も低いですからマイホーム購入における税金対策としても市街化調整区域の物件は効果を発揮します。
但し、「土地は購入したものの建物が建てられなかった」「思い描いていた建物のプランが入らなかった」というのでは本末転倒ですから、
購入の意思決定を行う前には自治体へ事前相談に赴いた上で、市街化調整区域の取引経験を十分に有する不動産業者、そして地域の事情に精通した設計士やハウスメーカーへ依頼を行うべきです。
- 抜群の住環境を手に入れられる
- 物件購入価格がリーズナブル
- 固定資産税等の税額を低く抑えられる
市街化調整区域での建替えや物件購入時のデメリット
市街化調整区域での建替えや物件購入においてまず注意すべきは、「自治体が定める条例等の内容」についてとなります。
既にお話しした通り、都市計画法第34条11号の指定区域においてはある程度自由な開発行為が可能となりますが、各自治体によって様々なルールがありますので、その内容をしっかりと把握した上で物件の購入意思を決定する必要があるでしょう。
例えば、建替えに際して大幅な床面積の制限が発生するケースは珍しくありませんし、アパートなどの収益物件を建てることができない自治体も珍しくありません。
※建て替え時の床面積については現在の建物の床面積の1.5倍以内とする自治体が多いようです。
また、一度更地にしてしまうと建て替えが困難になってしまう場合もありますし、用途が「店舗」となっている中古物件を購入してしまうと「住居への用途変更」ができないケースも考えられますので注意が必要です。
※店舗を住居として使い続けた場合は建築基準法違反となります。
そして、購入する土地が農地として利用されている場合には農地転用が必要となりますが、市街化調整区域では許可が下りないことも珍しくありません。
更に、市街化調整区域は原則として市街化を行わない地域であるが故に電気や水道、下水・ガスなどのインフラ設備が前面道路まで到達しておらず、その整備に多額の費用を要する場合もありますし、人里離れた場所にあるため建築コストが高額になってしまうことも考えられるでしょう。
一方、生活を行う当たっては静かな住環境である反面、周囲に店舗がないのは当たり前ですし、通勤や通学にも苦労させらる可能性も十分にあります。
そして、こうしたデメリットがあるが故に売却する際の価格はどうしても安価となってしまい、資産価値が低いという点も市街化調整区域のデメリットに挙げられるでしょう。
- 自治体によって建築制限の内容が異なる
- 更地にしてしまうと再建築できない場合がある
- 建築基準法上の用途変更ができない場合がある
- 農地転用が必要となる場合がある
- 電気・水道・下水等のインフラ設備が整備されていない可能性がある
- 立地の悪さにより建築コストが高額になる
- 商業施設等がないため生活に不便を感じる
- 物件の資産価値が低い
スポンサーリンク
市街化調整区域の建て替え・物件購入まとめ
さてここまで、「市街化調整区域内での建て替えやマイホームの購入」というテーマにて解説を行ってまいりました。
本記事をお読みくだされば、市街化調整区域での開発行為に様々な制約が生じること、またその一方で多くのメリットを享受できることをご理解いただけたことと思います。
なお、同じ市街化調整区域の中でも都市計画法第34条11号の開発許可区域等に所在する物件を選択することで、建物の規模や用途に関する制約を最小限に抑えつつ、緑に囲まれた静かな住環境に建つ戸建てがリーズナブルに購入できるはずですから、これは環境重視派の方にとっては申し分がありませんよね。
ちなみに、「建築許可の申請」などの手続きについてはハウスメーカーや設計士が全て代行してくれますから、購入者が煩わしい思いをすることはないはずです。
市街化調整区域というだけで不安を覚えてしまう方も多いとは思いますが、こうした物件を上手に購入し、他では味わえないスローライフを手に入れるのも一興なのではないでしょうか。
ではこれにて、「市街化調整区域の建て替えや物件購入について解説いたします!」の知恵袋を閉じさせていただきたいと思います。