マイホーム探しの際に不動産の物件情報サイト等を見ていると、備考欄に「用途地域/準住居地域」といった記載があるのを目にしますよね。
ただ、物件を探している際には立地や価格、間取りなどに関心が向いてしまい、こうした表示に注目される方は殆どおられないのが現実でしょう。
ところが、このような扱いを受けている用途地域には「物件購入の意思決定に役立つ情報が満載されている」のです。
そこで本日は不動産の用途地域と種類、そして注意すべき点などについて解説させていただきたいと思います。

用途地域とは何か
自動車や電車の窓から流れる景色を眺めていると、くるくると移り変わっていく街並みが目に入ってくるものですが、実はこうした何気ない風景の中にも「行政の街づくりのプラン(マスタープラン)」が組み込まれているものです。
そして、こうした行政による「街づくりプラン」の根幹をなしているのが『都市計画法』と言われる法律であり、この法律では、
- 市街化区域・・・積極的に街づくりを行う区域
- 市街化調整区域・・・原則、市街化をしない区域
- 非線引き区域・・・特にプランが定まっていない区域
という3種類の区域を定めることとしています。
そして通常、私たちが家を建てたり、土地を購入したりする地域は、この都市計画法の線引きにおける積極的に街作りを行って行くべき地域、つまりは「市街化区域」に指定されているケースが多いはずです。
また、一口に市街化区域と言っても、街の中には「住宅地」や「工場地帯」、そして「商業地」など様々な地域が必要となりますし、閑静な住宅街に突然巨大な工場やデパートが建てば、街並みはグチャグチャになってしまいますよね。
そこで市街化区域に指定されたエリアについては、建築できる建物の種類や規模に「様々な縛り(規制)」を加えることとなりました。
そして、この「縛り」こそが『用途地域』と呼ばれるものなのです。
※用途地域は都市計画法が定める地域地区の一つですが、具体的な運用のルールは建築基準法の規定によります。
※用途地域は原則として市街化区域に定められるものですが、例外的に市街化調整区域や非線引き区域、準都市計画区域に定めらることもあります。
つまり、用途地域とは「自治体が目指す街づくりの理想(マスタープラン)を実現するために定められた、土地の使い道(用途)の制限」ということになるでしょう。
そして行政が指定できる用途地域の種類は全部で13種類あり、以下がその一覧となります。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
なお、用途地域を理解する上で重要なのは「これから物件を買おうと考えている地域に、どんな街並みが広がっていくのか?」というイメージを用途地域の種類から思い描けるようなることとなりますので、次項では各用途地域の特性をご説明してまいります。
不動産の用途地域を解説
では早速、各用途地域の特徴と思い描くべきイメージを解説してまいりましょう。
第一種低層住居専用地域
「閑静な住宅街」という表現がピッタリの地域であり、家と家の間隔もゆったりと確保されています。
また「絶対高さ制限」という厳格な制限があり、10mもしくは12mが建築できる建物の高さの限度です。
よって2階建ての戸建てが圧倒的に多い地域となりますが、3階てのマンションも目にすることがあるでしょう。
更に建築できる建物の用途にも厳しい制限があり、住居や共同住宅、小中学校、診療所は認められますが、大学や病院は許可されません。
※児童厚生施設や老人福祉施設は600㎡以下なら認められます。
ちなみに、店舗兼住宅や事務所兼住宅は認められますが住居以外の部分(非住居部分)は50㎡以下、且つ床面積の1/2未満としなければなりませんし、店舗に関しては営業できる職種にも制限が設けられています。
一方、建物の形状にも制約があり、日当たりに関する北側斜線制限や、隣地から距離をとって建築を行う外壁後退などのルールも定められているのが特徴です。
なお、建ぺい率と容積率については以下の通りとなります。
- 建ぺい率/30、40、50、60%のいずれか
- 容積率/50、60、80、100、150、200%のいずれか
このように第一種低層住居専用地域はとにかく住環境を重視したエリアとなりますので、駅や商店街からも遠く、コンビニやスーパー等に行くのにも苦労させらる地域となりますが、何よりも静かな生活を望む方には絶好のロケーションとなるはずです。
第二種低層住居専用地域
前項にて解説した第一種低層住居専用地域よりも少々制限が緩やかなエリアとなりますが、10mもしくは12mの絶対高さ制限や北側斜線制限は課せられていますので、2階建ての戸建てや、3階てのマンションが中心の街並みとなります。
但し、第一種低層住居専用地域で許可される建物に加えて、床面積が150㎡以下であればコンビニや飲食店(喫茶店など)も認められますので、生活の利便性はかなり向上するばずです。
よって、「閑静な住環境が希望ではあるが第一種低層住居専用地域は厳しすぎる」という方におすすめのエリアとなるでしょう。
ちなみに建ぺい率と容積率については以下の通りです。
- 建ぺい率/30、40、50、60%のいずれか
- 容積率/50、60、80、100、150、200%のいずれか
第一種中高層住居専用地域
その名の通り、中高層住宅の良好な住環境を守るためのエリアであり、ここでは10mもしくは12mの絶対高さ制限が適用されません。(北側斜線制限は適用)
よって、3階建ての戸建てやある程度の高さのマンションも建築が可能となります。
また、2階建て以下で床面積500㎡以下という制限はあるものの、様々な飲食店やスーパーマーケット、そして銀行や大学なども認められますので、ある程度閑静な住環境と利便性を両立させたマンション暮らしや、3階建て住宅の購入を希望される方向けの地域となるでしょう。
そして建ぺい率と容積率については以下の通りとなります。
- 建ぺい率/30、40、50、60%のいずれか
- 容積率/100、150、200、300、400、500%のいずれか
第二種中高層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域と同じく、マンションと3階の戸建てが立ち並ぶエリアとなりますが、2階以下で許可される飲食店などの店舗の床面積が1500㎡以下まで拡大されているのが特徴です。
また、事務所も許可されるエリアとなりますので、この地域では中高層住宅の街並みにオフィス街の風味も加わることになります。
なお建ぺい率と容積率については以下の通りです。
- 建ぺい率/30、40、50、60%のいずれか
- 容積率/100、150、200、300、400、500%のいずれか
第一種住居地域
第一種住居地域というネーミングからも判る通り、住環境を重視したエリアとなりますがここでは厳しい日照の規制である「北側斜線制限」が適用されないため、これまでご紹介してきた用途地域と比較して「住宅の密集度」と「建物の高さ」がかなり向上してきます。
更に、床面積3000㎡以下であればホテルや旅館などの宿泊施設に加え、ボウリング場・プールなどの遊戯施設も許可が下りますので、かなり繁華街の色が濃厚になってくるでしょう。
但し、パチンコ屋やカラオケボックスは禁止となっていますから、街中だがそれなりの住環境は維持したいという方におすすめのエリアとなります。
ちなみに建ぺい率と容積率については以下の通りとなります。
- 建ぺい率/50、60、80%のいずれか
- 容積率/100、150、200、300、400、500%のいずれか
第二種住居地域
第二種住居地域では、第一種住居地域で許されていた施設に加えて床面積10000㎡以下の店舗、そして床面積3000㎡以下の事務所の建築が可能となる上、パチンコ屋に雀荘、カラオケボックスまでも解禁となりますので、これは最早プチ繁華街と言っても過言ではないでしょう。
また、大型の商業施設の建築も可能となりますから、これまでの住居系用途地域とは一線を画した都市型のエリアとなりはずです。
なお建ぺい率と容積率については以下の通りです。
- 建ぺい率/50、60、80%のいずれか
- 容積率/100、150、200、300、400、500%のいずれか
準住居地域
国道や県道など、原則として「道幅の広い道路沿いに指定される地域」となります。
基本的には第二種住居地域に近い許可基準となりますが、道路沿いという特性から床面積150㎡以下の自動車修理工場や大型の立体駐車場(3階以上)も認められるますし、住居系用途地域では唯一、映画館や演芸場(床面積200㎡以下)の建設が認められているエリアとなります。
なお、イメージがしやすいのはファミレスや超大型スーパー、郊外型ドラッグストアーなどのロードサイド店が並んでいる、幹線道路沿いの風景なのではないでしょうか。
そして建ぺい率と容積率については以下の通りとなります。
- 建ぺい率/50、60、80%のいずれか
- 容積率/100、150、200、300、400、500%のいずれか
田園住居地域
住居系最後の用途地域となるのが、2018年から導入されることになった田園住居地域となります。
その名の通り、農地が広がる静かな住環境を守るために創設された用途地域となりますので、第一種低層住居専用地域と肩を並べる厳しい建築制限が特色です。(10mもしくは12mの絶対高さ制限や北側斜線制限が適用されます)
さて、このような解説を行うと「第一種低層住居専用地域と何が違うの?」というお声も聞こえて来そうですが、田園住居地域の特徴は「農地と住宅地の共存をテーマにしている点」にあります。
よって、農作物の貯蔵庫や加工場はもちろんのこと、農作物の即売所や地産地消をコンセプトにしたレストランといった施設(床面積500㎡以下)については建築が許されているのです。
ちなみに建ぺい率と容積率は以下の通り厳しめとなります。
- 建ぺい率/30、40、50、60%のいずれか
- 容積率/50、60、80、100、150、200%のいずれか
★当ブログ管理人執筆の電子書籍(kindle)のご紹介!是非ご一読ください!★
 |  |  | 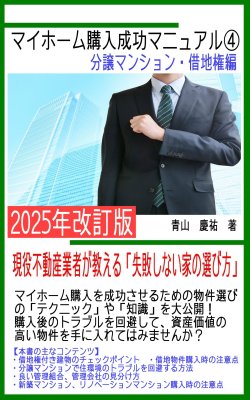 |
近隣商業地域
さて、ここまでは住居系の用途地域でしたが、ここからは商業系のエリアとなります。
近隣商業地域はその中でも本格的な繁華街の一歩手前といった雰囲気の街並みとなりますので、「駅前の賑やかな商店街」というイメージがしっくりとくるのではないでしょうか。
なお、床面積10,000m以下のデパートや飲食店、大型パチンコ店も営業が可能ですし、150㎡以下であれば工場も建てられますから、住環境としては歓楽街風味の少々派手な街並みといった印象を受けるはずです。
こうした地域ですから、建ぺい率と容積率は以下の通り緩めのエリアとなります。
- 建ぺい率/60、80%のいずれか
- 容積率/100、150、200、300、400、500%のいずれか
商業地域
高層ビルがそびえ立つ、天下無敵の繁華街といったイメージのエリアとなります。
映画館や百貨店、銀行などのオフィスビルが建ち並ぶ、ターミナル駅の周辺地域などを思い浮かべていただければ、イメージがしやすいかと思います。
また、こうした地域であるが故に、キャバクラや風俗店等の営業も可能となります。
このような解説を行うと「住環境としては厳しいものがあるのでは・・・」と思われてしまいそうですが、こうした地域だからこそ建築可能なのがタワーマンションです。
利便性抜群、刺激に溢れたアーバンライフを夢見る方々にはおすすめのエリアとなるでしょう。
ちなみに建ぺい率と容積率も突き抜けており、以下の通りとなっています。
- 建ぺい率/80%
- 容積率/200、300、400、500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1300%のいずれか
準工業地域
そしてここからは、工業系の用途地域となります。
ただ、準工業地域は危険性を伴う作業が行われる施設や極端に大きな工場は建築不可の地域となりますので、街並み的には「住居系にも見える地域」が少なくありません。
また、容積率等が緩和されているため大型の分譲マンションも多いエリアとなります。
よって、思い描いていただく街並みとしては中小規模の工場と3階建の小さな建売住宅、そして大戸数マンションが混ざり合った活気のある風景といったところでしょうか。
- 建ぺい率/50、60、80%のいずれか
- 容積率/100、150、200、300、400、500%のいずれか
工業地域
所謂、工場地帯というイメージの街並みとなりますが、戸建てやアパートなども建築は可能です。
但し、前項の準工業地域とは異なり、大規模な工場、危険性が高いプラントも建てることができるエリアですので、工業主体の地域であることは間違いありません。
こうした理由から病院や学校、そしてホテルなどは許可されませんので、住環境としては少々問題があると言わざるを得ません。
なお建ぺい率と容積率については以下の通りです。
- 建ぺい率/50、60%のいずれか
- 容積率/100、150、200、300、400%のいずれか
工業専用地域
完全なる工業地帯であり、住宅や商店は見掛けることさえないはずです。
広大な敷地を持つ工場が建ち並ぶ、湾岸の工業地帯などをイメージしていただければと思います。
その名の通り、工業が最優先される地域となりますから学校や病院はもちろん、住宅の建築さえも原則制限されるエリアです。
よって、マイホーム探しに際して「縁のない地域」と言って差し支えないでしょう。
ちなみに建ぺい率と容積率については以下の通りとなります。
- 建ぺい率/30、40、50、60%のいずれか
- 容積率/100、150、200、300、400%のいずれか
用途地域の建築制限について
ここまでの解説にて用途地域の種類についてはご理解いただけたことと思いますので、本項では用途地域によって課せられる各種の建築制限の概要についてお話しさせていただきたいと思います。
用途の制限
用途地域という名称の通り、ここまで見てきた13種類の地域では土地の利用法(用途)に様々な制限が課せられています。
具体的には第一種低層住居専用地域でホテルの営業が禁止であったり、工業専用地域に住宅が建てられなかったりといった内容となりますが、「用途地域の境目にまたがる土地」の場合にはどのような用途の制限が課せられるのでしょうか。
実はこのケースでは、対象の土地面積の中でより多くの範囲を占める用途地域の制限が適用されることになります。
つまり、土地面積の60%が第一種住居地域で、残りの40%が準工業地域であった場合には、より多くを占める第一種住居地域の用途制限が課せられるという訳です。
建ぺい率と容積率
各種の用途地域の説明の中でも、指定される容積率と建ぺい率については記載いたしましたが、改めて制限の概要を記しておきましょう。
「建ぺい率」とは対象の土地における建築面積の上限を示すものあり、「容積率」は建築可能な建物の床面積の上限となります。
よって、100㎡の土地で建ぺい率50%、容積率100%なら、建物の敷地とできる上限の面積が50㎡、建物の床面積の上限が100㎡となる訳です。
なお、建ぺい率と容積率の制限内容は用途地域によって異なりますが、そのライン上にある土地に建物を建てる場合については、ラインで仕切られた部分(面積)ごとに建ぺい率と容積率の計算を行い、その結果を合算して建ぺい率や容積率の割合(%)を求めるという方法で上限を導き出すことになります。
ちなみに、建ぺい率と容積率については別記事「建ぺい率・容積率の計算や緩和についてご説明いたします!」において詳細な解説を行っております。
建物の高さと日当たりについての制限
続いては用途地域ごとに定められる建物の高さや日当たりの制限についての解説となりますが、この規制には
- 高度地区
- 斜線制限
- 絶対高さの制限
- 日影規制
以上の4つの種類があります。
※各種制限の詳細については別記事「建物の高さ制限と日当たりに関する制限について」にて解説しております。
それぞれに建物の高さを制限したり、日当たりを確保するためのルールが定められていますが、用途地域ごとに制限の内容が大きく変わりますので、敷地が「高度地区」「斜線制限」「絶対高さの制限」のボーダーをまたいでいる場合には、そのラインを境界に規制を受けることになります。
つまり、土地の30%が第一種低層住居専用地域に属していれば、そこに定められた「高度地区」「斜線制限」「絶対高さの制限」を受けることになり、残りの70%が第二種中高層住居専用地域なら、こちらはこちらの高さ制限を別々に受けるということです。
但し、「日影規制」についてだけは、またがる各用途地域に定められたルールの中で最も厳しいものが土地全体に適用されることになっています。
防火地域と準防火地域について
防火地域と準防火地域は火災の被害を最小限に抑えるための建築制限となりますが、こちらも用途地域ごとにエリア分けがなされることが少なくありません。
※防火地域と準防火地域の詳細については別記事「防火地域・準防火地域とは?わかりやすく解説いたします!」にて解説しております。
なお、土地が防火地域と準防火地域をまたいでいる場合には、土地全体により厳しいエリアの制限が適用されるルールです。
スポンサーリンク
不動産の用途地域まとめ
ここまで、各用途地域の特性や用途地域の違いによってもたらされる建築制限の概要について解説を行ってまいりました。
漠然と「用途地域の種類とその違いを頭に入れる作業」は非常に苦痛ですが、このように『街並みをイメージしながら学んでいく』ことで、地域性の違いや雰囲気の差も掴みやすくなったのではないでしょうか。
そして物件選びに際しても、「図面に書かれている用途地域の種類から、ある程度の街並みが想像できる」ようになれば、より効率的な物件探しが可能となるはずです。
なお、マイホームの購入に際して「物件の周辺環境」と「用途地域のイメージ」に差が生じている場合には、充分な注意が必要となります。
例えば、今はまだ「住宅街の雰囲気」を保っている地域でも、準工業地帯や工業地帯では「後から大きな工場や商業施設が建てられる可能性」が充分にありますし、第二種住居地域なら「隣の土地にパチンコ屋が開業する」ことも、『可能性がない訳ではない』のです。
このように用途地域を「単なる法令上の説明事項」と捉えるのではなく、「物件を選択する上での重要な検討材料」と考えることができるようになれば、マイホーム探しの大きなヒントとなるのではないでしょうか。
ではこれにて、不動産の用途地域と種類、注意すべき点などについての知恵袋を閉じさせていただききたいと思います。