不動産の売買を行う際、取引の仲介を行う者が最も力を入れなければならないと言われるのが「物件調査」です。
なお、物件調査には「物件の所在地で行う現地調査」と「行政機関で行う役所調査(行政調査)」という、大きく分けて2つの種類がありますが、本日は最も基本となる不動産の現地調査に関する記事をお届けしたいと思います。

不動産仲介業者の責任
宅地建物取引業法(宅建業法)の35条にて定められているのが重要事項の説明であり、不動産業者が仲介取引を行う際には「必ずこの説明を行う必要がある」のは、当然皆様もご存知のことと思います。
そして、この重要事項の説明においては「その事実を知っていたら、この物件を買わなかった!」という情報について、仲介業者が告知を行わなっかった場合には『説明義務違反』が成立することとなり、損害賠償等を求められることになるのです。
また、不動産仲介を行う際には媒介契約をお客様と結ぶのが通常ですが、この契約によって仲介業者は「取引に対する注意義務」を負うことになりますから、「物件に関する重大な事実を見落としていた」という場合にはこちらの『注意義務違反』でも責任を追及されることになるでしょう。
更に宅建業法では、重要事項の説明に不備があった場合に「行政罰が課される旨」も定めていますから、これはなかなかに厳しいものがありますよね。
もちろん、「可抗力によって告知するべき事項に気付くことができなかった」という場合には、『過失なし』と判断され、責任の追及を逃れることができるでしょうが、仲介業者は「不動産のプロフェッショナル」という立場ですから、こうした酌量を受けるためのハードルは非常に高いものとなるでしょう。
例えば、繁忙期のみに騒音を発生させる工場が売買対象物件の周辺に存在していたとしても、音が出ていない時期に取引が行われれば、仲介業者も騒音被害の事実を知ることはできませんよね。
しかしながら、訴訟などに発展した場合には「近隣で聞き込みをすれば、工場の騒音に気が付くことができたはずだ」と判断される可能性が高いですから、こうしたケースでは『仲介業者に過失有り』とされてしまうのです。
このように重要事項説明における仲介業者の責任は、「不条理といっても過言ではない程に重いもの」となりますので、取引上のトラブルを回避するために徹底した調査を行う必要があるでしょう。
周辺環境に関する現地調査
さて、現地調査においてまず注意するべきは、住環境に影響を与える施設についての確認です。
そこでまずは、騒音や振動の原因となる工場や線路、道路などが近くにないかを徹底的にチェックをしていきます。
また、工場等の中には埃や臭気を発するものもありますし、物理的な被害はないものの、お墓や葬儀場などは嫌悪施設(精神的に嫌悪感をもたらす施設)と判断されますので注意が必要でしょう。
※嫌悪施設に関しては別記事「不動産の嫌悪施設についてお話してみます!」にて更に詳しい解説を行っております。
なお先程の事例でも触れましたが、ここで気を付けなければならないのが「問題となる施設の全てが継続的な音や振動、臭気などを発生させている訳ではない」という点です。
戸建ての一階部分を改造して作業場としているような工場は「土日は稼働していないケース」が多いですし、昼は喫茶店なのに「夜になると大音響でカラオケの音を轟かせるスナック」などもありますから、こうした施設は見逃してしまうリスクが非常に高いでしょう。
よって、調査に行く時間や曜日を充分に考慮した上で、複数回に分けて現地の様子を観察しに行くべきです。
ちなみに、競馬場などのギャンブル施設の近くでは、勝負に敗れたおじさん達が大挙して通過していく道路に取引対象の物件が面しているケースもあるでしょうし、
新興宗教の施設に近接する物件では「土日に多くの信者が詰めかけて迷惑している」といったクレームが発生することもありますので要注意となります。
そして更に怖いのは、暴力団事務所、そして組員や組長の自宅などとなるでしょう。
組事務所については警察などへのヒヤリング調査である程度は対応が可能ですが、個人宅は人権問題との絡みから、警察からも情報提供を受けられないケースが殆どです。
このように住環境に影響を及ぼす施設は実に様々なものがあり、通常の手段では発見できないケースもありますが、ここで威力を発揮するのが「近隣への聞き込み調査」となります。
但し、突撃インタビューをしても怪しまれるだけですから、売却依頼を受けた時から、近隣の方と挨拶・雑談などを交わしながら、顔見知りを増やしておくのが得策でしょう。
これにより、騒音おばさんのような危険人物の存在も事前に察知できる可能性が高まりますので、試す価値は充分にあるかと思います。
★当ブログ管理人執筆の電子書籍(kindle)のご紹介!是非ご一読ください!★
 | 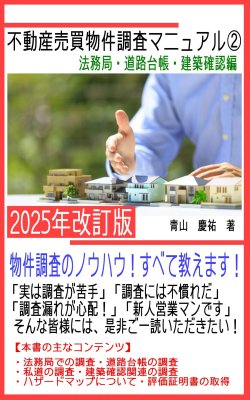 | 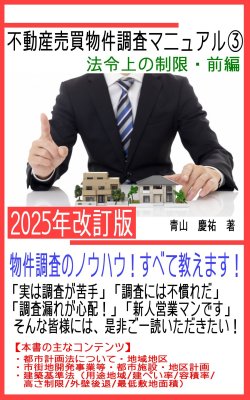 | 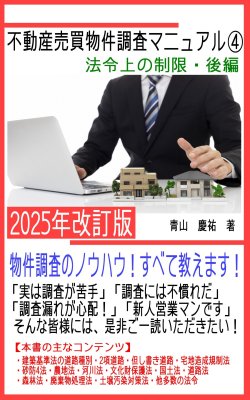 |
土地に関する現地調査
さて続いては、物件自体に潜む問題を調査していきます。
ここでは主に以下の点が重要な調査ポイントになるはずです。
インフラ設備の確認
現地調査においては、水道や下水、ガスといったインフラ設備の状況も重要なチェック項目となってきます。
よって、まずは敷地内を見回して
- 水道メーターと止水栓
- 下水の枡
- ガス管の杭
以上の設備の有無を確認しましょう。
そして、「水道メーターと止水栓」と「ガス管の杭」が発見できれば、これだけで水道とガスの引込みが完了している旨と、引込管のおおよその位置が把握できるという訳です。
※重要事項の説明においては引込管の管径などの情報も必要となりますが、これらの情報は役所(行政)調査にて明らかになりますので、現地調査では上記の概要のみ確認できれば十分です。
一方、下水については役所調査においても図面等を確認することができませんので、現地調査で得られた情報が非常に重要となってきます。
なお「下水調査の具体的な方法」と、インフラ設備関連で最も問題となる「越境に関する事項」については、次項で解説させていただきます。
境界と越境についての調査
不動産の売買において最もトラブルに発展し易い問題の一つが、この境界と越境に関するトラブルとなります。
土地の境界線や越境問題に関する記事でも解説いたしましたが、古い分譲地や借地が連なる地域では境界標が失われていたり、ブロック塀が境界線を斜めに横切るように設置されているのを見掛けるものです。
こうしたケースでは、土地家屋調査士に依頼して測量と境界確定を行った後、売主と隣地所有者へ「ブロック塀の所有者が誰なのか」の確認を行った上で越境等の覚書を交わすなどの対応が必要となるでしょう。
よって現地調査においては、まずは境界標の位置を確認した上で、越境物の有無を確かめることが重要となります。
※地積測量図等の資料がある場合は「図面に示された境界標が紛失していないか」のチェックを行うことになりますが、資料がない場合でも任意に設置された「刻み」や「鋲」の存在を確認しておきましょう。
また、「自分の目線の高さ」にばかり気を取られていると見過ごしがちなのが、空中越境です。
隣接地の「電話線や電線が物件上空を横切っていないか」、また「隣家の屋根や軒がこちらの土地を侵害していないか」、そして「庭木の枝が伸びて越境していないか」も重要なチェックポイントとなります。
※電線の越境に関しては別記事「電線が敷地上空を横切る場合の契約内容を解説!」にて解説を行っております。
そして一番厄介なのが、地中の越境物です。
両隣りや裏のお宅の水道管や下水管が取引対象の土地を通過しているケースもありますし、反対に取引する物件の配管が隣地に越境している場合もあります。
水道であれば、対象地と近隣の止水栓の位置から、おおよその経路の見当が付くケースもありますし、水道局には敷地内の配管経路を示した資料が保存されていますので、調査は比較的簡単なはずです。
これに対して下水は、下水局にも私有地内の配管に関する資料は残されていませんので、下水枡の蓋を開けて「どの方向から排水路が伸びているか」を確認する作業に加え、時には色の付いた水を流してもらい、汚水の流れる方向を調査することも必要でしょう。
※配管調査については別記事「地中配管調査の方法について!(不動産売買重要事項説明用)」にて、地中埋設物に関しては「地中埋設物の瑕疵について考えてみます!」にて詳細な解説を行っております。
工作物等に関する調査
前項の境界と越境の調査にて「ブロック塀」のお話が出ましたが、不動産の現地調査においてはこうした工作物に関してもチェックが必要となります。
なお、ブロック塀以外にも高低差のある地勢の地域では、土留めを目的とした擁壁や地下車庫といった工作物が設置されていることも珍しくありません。
そして、こうした工作物については『設置時に建築確認や宅地造成許可、開発許可などを取得しているか否か』が非常に重要なポイントとなりますので、
- 工作物の設置場所
- 工作物の寸法等の概要
- 工作物の写真
- 工作物の破損の有無
などをしっかりと記録しておきましょう。
ちなみに、「建築確認等を取得しているか否か」については役所調査(行政調査)にて明らかになりますが、上記の調査資料が揃っていれば、役所との打ち合わせもスムーズですし、擁壁の高さなどの情報は隣地との高低差など「地勢の特色」を知る意味でも重要なデータとなります。
土地の履歴
現地調査においては、取引対象の土地の履歴を知ることも重要なポイントとなります。
そして最も怖いのが土壌汚染の問題であり、過去に工場や作業所、クリーニング屋などがあった土地では、汚染が発生している可能性を視野に入れておく必要があるでしょう。
なお、土地の履歴を知るためには売主さんや近隣住人への聞き込みも大切ですが、最寄の図書館などに行けば「古い年代の住宅地図を閲覧できるケース」もありますから、労力を惜しまず足を運ぶことをおすすめします。
また土地の履歴とは少々方向性が異なりますが、古くからの地主さんの敷地ではお稲荷さんや井戸等の存在にも注意が必要でしょう。
地中埋設物
不動産の取引においては「地中に埋もれたもの」がトラブルの原因となることも少なくありません。
例えば、以前に建っていた建物の基礎が地面に埋まっており、その撤去に法外に費用が掛かる場合もありますし、今では公共下水が整備されている場所でも、土地に浄化槽などが埋められたままになっていることも少なくありません。
もちろん、目視で地中の状況を把握することはできませんが、注意深く物件を観察することで異変に気が付くことができるケースもありますから、5感を総動員して調査に臨む必要があります。
接面道路の確認
ここまでの調査で土地自体のチェックはほぼ完了したはずですので、続いては接面道路の調査を行います。
接面道路の調査においては、まず道路の幅員を測った上で、路面上の設備をチェックしていきましょう。
なお、チェックすべき設備は
- 道路上の境界標や杭
- マンホール、側溝
- ガードレール、歩道
- 歩道がある場合は道路との段差
- 道路標識、電柱、街路樹
- ゴミ捨て場
以上の事項となります。
境界標や杭は、公道であれば官民境界、私道であれば民地同士の境界を表しますので是非チェックしておくべきですし、マンホールや側溝の位置は道路内の下水配管の状況を把握するのに役立ちます。
また、敷地の前面にガードレールがあれば、自動車の出入りのために一部を撤去する必要がありますし、歩道があり、車道との段差が生じている場合には、「歩道の切り下げ」が必要となりますので、この点もしっかり確認しておきましょう。
更に、道路標識・電柱・街路樹についても敷地からの出入りの障害となる場合には移設が必要ですし、ゴミ捨て場に至っては「僅かに位置を動かすだけ」でも近隣からクレームが来る可能性がありますのでご注意ください。
※道路上の設備については別記事「歩道切り下げ、電柱の移動などについて解説いたします!」をご参照ください。
一戸建てにおける建物の現地調査
新築住宅に関してはあまり注意する点はありませんが、取引対象が中古住宅の場合には「建物本体と設備の調査」に力を入れる必要が出てくるでしょう。
なお、かなりの年数を経た物件であり、個人間での売買であるならば、「契約不適合責任免責の特約」(雨漏りや躯体の腐食などに売主が責任を負わない旨の特約)を契約書に組み込んでしまえば問題なし!」とお考えの方も多いことと思います。
確かにこれは非常に安心な特約ですが、築年数が浅い物件ではなかなか買う側が納得しないでしょうし、あまりに甚大な被害が発生している場合には、この特約だけでは責任の追及を逃れられないケースもありますので注意が必要です。
ちなみに近年では、中古住宅の売買に際してインスペクション(住宅検査)を受け、瑕疵保険に加入するのが当たり前になりつつありますが、売主さんの中にはどんなに必要性を説いても、これを受け入れてくれない方もいらっしゃいますよね。
そして、このような場合には買主さんサイドにて設計士や工務店に物件の状況を確認してもらう方法が有効なのですが、これさえも難しいケースでは仲介業者が自ら物件のチェックを行う他はありません。
そこで以下では、管理人が行っている中古戸建ての瑕疵調査方法をご紹介してみたいと思います。
- 外壁を隈なく見て回り、塗り壁のクラック、サイディング材の割れや隙間をチェック
- 物件内部の天井、サッシ回りなどに雨漏りの痕跡がないかを確認
- 天袋や収納などを空け、壁と天井の継ぎ目から雨漏りの跡が無いかをチェック
- 天井や壁のクロスにひび割れ等がないかを確認
- 窓や建具の開閉に問題がないか
- スーパーボール大の鉄球を数個を用意して、各階の床(数か所)にこれを置き「転がり」がないかを確認
- 洗面台や風呂場、キッチンの水を流したままの状態で、漏水の有無をチェック
これらは非常に手軽な調査方法であるため、拍子抜けしてしまった読者の方も多いかと思いますが、実はこれらのチェック方法は「瑕疵保険利用時の物件調査でも行われている検査」となりますので、決して侮ることはできません。
もちろん本格的な建物検査の内容には程遠い精度ではありますが、これだけでも「やらないよりは遥かにマシ」なはずです。
※インスペクションや瑕疵保険の詳細については別記事「インスペクションと瑕疵保険について解説いたします!」をご参照いただければと思います。
分譲マンションでの現地調査
さてここまで、土地や一戸建てを前提に現地調査の説明を行ってまいりましたので、ここでは分譲マンションにおける調査についてお話ししていきましょう。
分譲マンションの現地調査においても、まずは敷地内を見て回るのが基本となりますが、戸建てなどのように越境や境界標の紛失などの「権利関係に係わる問題」が潜んでいることは殆どありません。
また、もしもこうした問題が生じたとしても、これに対処すべきは管理組合の仕事となりますから、買主が直接負担を強いられるケースは滅多にないはずです。
但し、敷地内にある付属建物や公園、駐輪場に駐車場などについては、その利用方法や管理規約上の扱いなどに関する説明が必要となるケースもありますので、しっかりと状況を確認しておく必要があるでしょう。
更に、エントランスや廊下などの共用部分についても隈なく見て回り、取引対象となるお部屋の両隣はもちろん、上下階や周辺のお部屋について問題点がないかをチェックしていきます。
※管理人は過去に「下の階のお部屋のバルコニーがゴミ屋敷状態になっていた」、「斜め下の階の住人が玄関ドアの外側に過激な政治的ポスターを掲示している」といったケースに遭遇したことがあります。
そして、この巡回で異変を察知した場合には、売主様に詳細にご事情をお聞きして、重要事項説明書へ反映させる必要があるでしょう。
なお、専有部分(室内)については「雨漏りの痕跡」や「クロスのひび割れ」など、前項『一戸建てにおける建物の現地調査』でのチェックポイントを参考に確認作業を進めることになります。
ちなみに、売主様が管理組合の過去の総会議事録を保管していない場合には、管理人室に保管されている議事録を閲覧することになりますし、管理人さんは物件に関する重要な情報源となりますので、現地調査においては必ず管理人室を訪れておくべきです。
売主へのヒヤリング調査
そして、最後に行うのが売主様へのヒヤリング調査となります。
当然ながら売主様は「物件について最も詳しい存在」となりますから、一戸建て、分譲マンションを問わず、この調査は非常に重要なものとなるでしょう。
但し、漠然と「住んでいて気になる点はありますか?」などと尋ねても、情報を得ることは難しいでしょうから、
- 周辺環境や近隣問題
- インフラ設備の状況
- 境界と越境について
- ブロック塀等の工作物について
- 土地の履歴
- 地中埋設物について知っていること
- 接面道路の施設について
- 建物や設備の不具合
といった具合に、これまでの現地調査の項目について順番に質問した上で、調査中に気になった事項についてもヒヤリングを行っていくと、思わぬ有益な情報を引き出せることもあるはずです。
スポンサーリンク
物件調査(現地)まとめ
さてここまで、不動産仲介時の現地調査について解説してまいりました。
少々長めの記事となりましたが、実はこれでも「現地調査に際して必要なノウハウの半分もお伝えできていない」とうのが実情です。
そして、より深く詳細に現地調査のテクニックを学びたいという方については、管理人が執筆いたしました下記の電子書籍(アマゾン・Kindle本)にてガッチリと解説を行っておりますので、是非お目通しをお願いできればと思います。

そして、最後に申し上げておきたいのが「現地調査の最大のコツは、物件全体をとにかく見渡すことである」という点です。
警察の捜査の極意を表す言葉に「現場百遍(げんばひゃっぺん)」というものがありますが、不動産の現地調査においてもこの感覚が非常に重要となります。
『可能な限り現場を訪れる』、『現場に行ったら物件の周囲を何度も回って、とにかく全体を見渡す』といったアクションを行うことで、パッと見ではわからない重要な告知事項に気付けることも多いですから、調査経験の少ない方は是非ともお試しいただければと思います。
物件調査は非常に奥の深いものとなりますから、不動産業者となって日の浅い方はもちろんのこと、中堅営業マンさん・ベテラン営業マンさんであっても、決して油断することなく調査に臨んでいただきたいところです。
ではこれにて、不動産の現地調査についての知恵袋を閉じさせていただきたいと思います。