マイホームの購入や売却といった不動産取引のクライマックスとなるのが、「売買契約の締結」というイベントとなります。
このようなお話をすると「物件探しや引渡しの方が山場(やまば)なのでは?」というお声も聞こえて来そうですが、契約をする前であれば、物件にどのような問題点が発見されても「嫌なら契約しなければよい」で済むことですが、
これが契約後となれば、時には訴訟などにも発展しかねない「大変な問題」へと発展してしまいますから、売買契約は取引の結末を「天国」にするか「地獄」にするかのボーダーラインとも呼べる重要なイベントなのです。
そこで本日は「不動産売買契約の注意点や流れを解説いたします!」と題して、売買契約締結の流れやポイントについてお話しさせていただきたいと思います。
なお、記事の前半は一般の方々(売主・買主)に向けて契約の注意点のご説明を、後半は不動産業者の目線にて契約の流れと気を付けるべき点を解説してまいります。

一般の方々(売主・買主)における不動産売買契約の注意点
ではまず、一般の方々(売主・買主)に向けての不動産契約の注意点についてご説明していきましょう。
そもそも契約とは「当事者同士の合意」によって成立するものですから、実は必ずしも『書面(契約書)』を作成する必要はありません。(口頭での契約も有効と解される)
但し、不動産取引は非常に高額の金銭が動きますし、売主・買主が互いに守らねばならない決め事も多数存在しますので、取引上の問題が発生した場合に「どのような約束の元に取引が行われたか」について明確な証拠を残しておく必要があるのです。
そこで作成されることになるのが売買契約書となりますが、「契約書に記載された事項は非常に強い証拠力を持つ」ことになりますので、
- 契約書の内容が様々な意味に解釈できる
- 売主・買主どちらか一方に極端に不利な内容となっている
- 売主・買主が契約内容を正確に理解していない
というような契約書を取り交してしまうと、非常に厄介な事態が発生することになってしまいます。
もちろん、売買契約書の作成に当たっては仲介に入る不動産業者が原案を作成することになりますから、とんでもない内容の契約書が出来上がる可能性は低いですが、一般の方もしっかりとその内容を確認し、相手方に有利な点が多いようなら内容の訂正を求めるなどの作業が重要になってくるのです。
また、不動産の売買契約を行う前には重要事項の説明というものが行われますし、物件状況報告書、付帯設備表、媒介契約書などの取り交しもありますので、これらの書類についても注意が必要となってきます。
売主・買主が重要事項説明で注意すべき点
重要事項説明は宅地建物取引業法35条の定めにより、「売買契約の締結前に仲介業者が買主に書面を交付した上で、物件に関する重要な事項を説明するイベント」となります。
※近年では法改正により、「ネット通信を利用した重要事項の説明」や「説明書の電子交付」が可能となっています。
よって通常は、仲介業者が買主に対して重要事項の説明を行うだけで、売主は一切説明に関知しないのが当たり前なのですが、売主もしっかりと重要事項説明書の内容に目を通しておくことが肝心です。
こうすることによって、仲介業者が見落としている「説明すべき事項」を発見することが可能となり、後々のトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
ちなみに重要事項の説明内容は大きく分けて、
- 物件の概要(所在地や面積)
- 取引の流れ(引渡し日等)
- 法令上の制限(法律で定められた制限等)
- 契約書の主な内容の確認
- 対象物件固有の説明事項や容認事項
上記のようになっています。
もちろん、その全てが取引における重要な事項となっていますので、買主はその内容をしっかりと把握し理解する必要がありますが、売主が特に注目すべきは「対象物件固有の説明事項や容認事項」となるでしょう。
この説明事項においては
と言った、売主にしか分からない内容や、説明文の微妙なニュアンが問題となってくる事項が数多く組み込まれていますので、仲介業者に全てを任せるのではなく、売主が自ら積極的にチェックを行うべきなのです。
そして、こうした売主の立場が理解できれば、説明を受ける側の買主も重要事項説明の「要点」が自ずと見えてくるのではないでしょうか。
なお、買主としては、次項で解説する契約書の読み合わせの際に「物件の概要(所在地や面積)」や「取引の流れ(引渡し日等)」「契約書の主な内容」については繰り返し確認をすることができますが、「法令上の制限(法律で定められた制限等)」については重要事項の説明でしか取り扱われることがありませんので、聞き逃しのないように気を引き締めて臨みましょう。
不動産売買契約について一般の方が注意すべきポイント
さて、重要事項の説明が終われば、次はいよいよ契約書の読み合わせを行い、署名捺印を行うことになりますが、契約に際して最も重要なことは「契約の席に着く前に、契約書のひな型を入手してその内容を徹底的に理解し、中身に問題があるようなら納得できるまで条件の調整を行うこと」となります。
では、具体的に契約書のチェックポイントを見て行きましょう。
取引対象と売買価格
契約書の冒頭では取引される土地の地番や面積、建物の家屋番号に床面積等の情報が表示され、取引される物件の特定が行われるとともに、売買価格が提示されることになります。
なお、不動産の取引においては公簿売買(登記簿上の面積での売買)と実測売買(物件の実寸による売買)の2通りがありますので「対象の取引がどちらであるのか」、そして「実測面積と公簿面積の間で差が出た場合にどのように処理が行われるのか」といった点が重要なポイントとなってくるでしょう。
売買契約上のスケジュール
続いては、契約のスケジュールについての条項に注目をして行きしょう。
不動産の契約書には「いくつかの期日」が記載されており、そのどれもが非常に重要なものとなります。
例えば、引き渡し期日は「その日までに物件の受け渡しを完了しなければならない締切日」ですし、「手付金の支払いの時期(通常は契約時)」や「中間金支払いの期日」、そして「物件の欠陥について売主が責任を負う期間(契約不適合責任を負う期間)」などがこれに当たります。
更に、次項で解説いたしますが不動産の契約には「いつまでなら契約が解除できる」という解除条項(解除の期日)が何件が記載されることになりますので、こちらにも大いに注意が必要です。
こうした重要な期日については、そのスケジュール設定が「無理のあるものではないか」「自分や相手にとって極端に不利なものではないか」という点に注目し、気になる部分があれば契約前に仲介業者としっかりと打ち合わせをしておくべきでしょう。
不動産売買契約の解除
不動産の契約書において非常に大きなウェイトを占めているのが、『解除(当事者どちらかの意思表示によって、遡って契約を無かったことにする)』に関する条項であり、契約書の中には
- 手付解除/手付金を放棄することで可能となる解除
- ローン解除/購入資金に対する融資が否認された場合の解除
- 物件の滅失による解除/火災等で引渡しが不能になった際の解除
- 債務不履行による解除/相手方に契約違反があった際の解除
- 契約不適合責任による解除/物件に欠陥があった場合に可能となる解除
以上、5つの解除条項が定められています。
そして各々の解除条項には、
- 解除が可能となる条件
- 解除が可能な期間
- 解除された場合のペナルティー
などが記されていますので、その内容をしっかりと把握しておくことが重要です。
ちなみに別記事「不動産売買契約の解除について解説いたします!」では、各解除条項について詳細な解説を行っておりますので、こちらも是非ご参照ください。
契約不適合責任について
前項でご説明した5つの解除条項の1つでもある「契約不適合責任」は、売買される不動産に欠陥があった場合の取り決めとなります。
一般的な契約書においては一定の期間(一般の方が売主なら3~6ヶ月間程度、不動産業者が売主なら中古で2年間、新築で10年間)、売主がその責任を負う旨が記されており、
- 修補(修理)
- 損害賠償(売主に責任がある時のみ)
- 解除(欠陥が重大である場合)
※不動産業者が売主の場合は、法令の定めにより責任の負い方が表記とは異なります。
以上のような方法で、問題が解決されます。
但し、物件が古い場合には売主の希望によって「契約不適合責任は一切負わない(免責)」とする場合もありますし、「責任の負い方についても様々なカスタマイズが加えられる」ことがありますので、事前に条文を確認して相手方と交渉を行う必要があるでしょう。
なお、契約不適合責任については別記事「契約不適合責任とは?わかりやすく解説いたします!」にて詳細な解説を行っておりますので、是非ご参考になさってください。
売買契約の特約事項
そして、契約書の中でも最大のポイントとなるのが特約事項となります。
特約とは「通常の条文よりも上位に位置付けられる特別な約束」という意味であり、ここでは物件固有の免責事項や容認事項が記されることが多いので注意が必要です。
例えば中古物件などでは、「物件に雨漏りが発生しているが、買主はこれを承知の上で買受けるものとし、売主は契約不適合責任を負わない」といった条文が入ることもあるでしょう。
もちろん、ここに書かれた取り決めを買主が承知で購入するのならば問題はありませんが、「契約時に初めてこの条文の存在を知った」「事前に聞いていた条件と異なる条文が入っている」となると非常に厄介ですので、しっかりと事前に確認しておくことが重要です。
但し、事前に万全の打ち合わせをしていたにも係わらず納得のできない条文が組み込まれており、相手方に譲歩する気もないのであれば、契約締結を拒否する勇気を持つことも大切です。
なお、売買契約書の特約に関しては別記事「不動産契約書特約条項の書き方、参考例をご紹介!」でにて解説をおこなっておりますので、ご興味がある方は是非ご一読ください。
不動産売買契約におけるその他の書類
売買契約の場においては、売買契約書や重要事項説明書以外にも
- 物件状況報告書/売主が建物の雨漏りや傾き、土地の履歴など物件状況を告知する書面
- 付帯設備表/売主が給湯器や床暖房、給水設備などの設備状態に関して告知を行う書面
- 媒介契約書/仲介業者への依頼を行う契約書
- 仲介手数料支払い承諾書/仲介手数料の支払いを確約する承諾書
- 住宅ローンの申込書/売買契約締結後に行う住宅ローンの本申込み用の書面
以上のような書面が取り交されることになります。
なお、ここで最も重要となるのが「物件状況報告書」と「付帯設備表」であり、売主の場合であれば『どんなに些細なことであっても物件について知っていることを包み隠さずに告知すること』が必要となりますし、
買主の立場であれば『告知の内容をしっかりと把握し、少しでも気になる点があれば売主に徹底的にヒヤリングを行っておくこと』が大切です。
※媒介契約に関する詳細は別記事「不動産媒介契約の種類と運用について解説!」をご参照ください。
★当ブログ管理人執筆の電子書籍(kindle)のご紹介!是非ご一読ください!★
 | 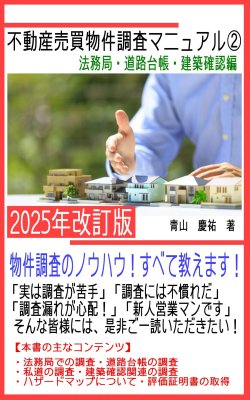 | 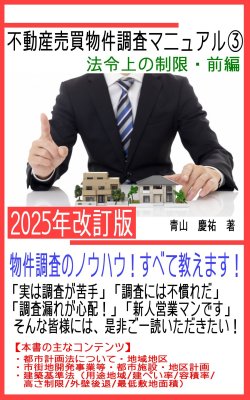 | 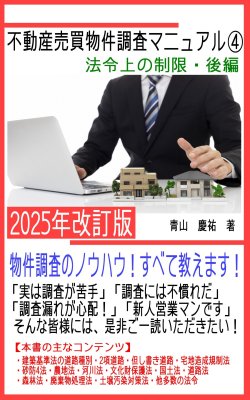 |
不動産業者(仲介業者)の目線で見た売買契約の流れと注意点【建売売買のケース】
さてここからは不動産業者(仲介業者)の目線に立って、売買契約の流れと注意点を見て行きましょう。
以前にも「不動産売買の仕事内容」の記事において、売買契約の注意点などについてお話ししましたが、「契約時の流れについて、更に詳細に説明をして欲しい」とのご要望を多く頂戴いたしましたので、改めてここでお話しさせていただきたいと思います。
※ここからは新築一戸建ての売買契約について、仲介業者の目線にてご紹介してまいります。
売買契約書と重要事項説明書の準備
ご紹介していた物件に対して、お客様が購入意思を固め、買付証明書が売主に受理されれば、その次に待っているのが売買契約の締結というイベントとなります。
冒頭でも申し上げた通り、契約前なら「取引上の重要な注意点」や「物件の瑕疵」についてお客様が把握していなくとも、大きな問題にはなりませんが、契約の場において『誤解を生じさせる説明』や『伝えるべき情報の不告知』があった場合には、後々非常に面倒な事態を招くことになりますから注意が必要です。
なお、こうしたトラブルを防ぐためには「適切な重要事項の説明」と「隙の無い契約書の作成」が最も重要なポイントとなりますので、この2点は契約の事前準備の中でも『最大限に力を注ぐべき事項』といえるでしょう。
そして重要事項説明書に関しては、現地調査と役所調査を納得いくまで行った上で、収集した情報を漏れなく説明書に盛り込んで行きます。
一方、売買契約書に関しては、お客様の購入条件(手付金の額、融資の申込み先金融機関名、引渡し希望日)をしっかり反映させた原案を作成することになりますが、ここでのポイントは、作成した重要事項説明書と契約書を『まずは売主(建売屋さん)に確認してもらう』ことです。
※重要事項説明書の作成方法については別記事「不動産重要事項説明書作成について!」を、契約書作成については「不動産売買契約書の作り方について解説いたします!」の記事をご参考になさってください)
当然ながら、売主である建売屋さんもプロの不動産業者ですから、提示する原案については様々なツッコミを受けることになりますが、大切なのは手数料をもらう立場だからと言って、売主の言いなりにはならないということです。
もちろん売主もお客さんなので、譲るべきことは譲らなければなりませんが、「後々トラブルになりそうな問題を隠して欲しい」「買主に極端に不利になるような契約条項を加えて欲しい」などの要望については、「無理なものは無理!」としっかり伝えましょう。
そして、こうしたやり取りを経て完成した重要事項説明書と売買契約書の原案を、最終的に買主に確認してもらいます。
この際、ドサッと書類を渡すだけでは読んでくれない買主さんも多いですから、要点は口頭でしっかりと説明を加えることも忘れないようにしましょう。(ここで重要事項の説明を行ってしまうのも、一つの方法です)
※新築戸建の場合(建売物件の場合)には、契約書に建物の消費税額を明記する必要がありますので、こちらも事前に売主から教えてもらいましょう。
なお、契約書・重要事項の説明以外にも用意すべき書類や準備は多々あります。
不動産売買契約に必要なその他書類の用意
売買契約に際して必要なその他の書類は、下記の通りとなります。
媒介契約書
売主からは「売却の依頼」を、買主からは「購入の依頼」を受けたことを証する書面です。
よって、「売主と仲介業者」間で交わす書面、「買主と仲介業者」間で交わす書面を2通ずつ作成する必要があります。
なお媒介契約には一般・専任・専属専任がありますが、建売物件にお客様を付けた場合(客付けの場合)は、売主用・買主用共に一般媒介となるのが通常でしょう。
仲介手数料支払い承諾書
決済時に頂く仲介手数料の支払いを確約してもらう書面となります。(契約時に仲介手数料を頂いてしまう場合には不要)
こちらについても、売主分・買主分それぞれを作成する必要があるでしょう。
なお、仲介手数料は物件の売買価格から建物の消費税額を引いた金額をベースに算出します。
また、書面を作成したら「手数料額に間違いがないか」を売主・買主に確認してもらう作業も忘れないようにしましょう。
物件状況報告書
物件に関する売主からの告知事項(雨漏りや、シロアリの被害、近隣との紛争の有無など)を記載してもらう書類となります。(建売の場合は新築ですのから、告知事項がないケースが殆どですが)
この書類には重要事項説明書と重複する内容も多く含まれるはずですが、売主が説明を行い、買主が承諾したことを証する書面となりますから、取引においては非常に大きな意味を持つものとなり、売主・買主署名捺印の上、互いに一部ずつを保管することとなります。
なお、契約の場で物件状況報告書を売主に書いてもらうのは手間なので、雛形をメールなどで事前に送り、記載済みのものを契約に持って来てもらうようにしましょう。
付帯設備表
売買対象となる物件には土地や建物以外にも、様々な設備や工作物などが含まれることになりますので、付帯設備表では「どのような設備等が存在しているのか」「その故障の有無」などを明らかにすることになります。
「設備等」と言っても、あまりピンッと来ない方もおられるかもしれませんが、建物に備えられたインターフォンや給湯器、テレビアンテナなどが設備として扱われ、門柱やカーポートの土間、車止めなどが工作物です。
売買完了後、建物本体には問題がないものの、使えると思っていた給湯器が故障していた場合などには、買主は想定外の費用を負担することになりますから、売主は契約の段階でこうした設備等の有無、故障の程度などを、付帯設備表を用いて告知しておく訳です。
なお、2020年の民法改正以降は、たとえ付帯設備について契約不適合責任を免責にしていても、売主が知っていた設備の故障を告知しない場合には「契約不適合責任を負わねばならない」のがルールですから、付帯設備表を必ず作成した上で、知りうる設備の不具合を全て記入することが重要でしょう。
但し、今回は売主が不動産業者ですから設備のアフターサービス基準を基に付帯設備表を作成することになります。
手付金の領収書
売買契約では手付金の授受が行われますが、新築の建売物件は売主が不動産業者となりますので、仲介業者が用意せずとも売主が自分で手付金の領収証を用意してくれます。
これに対して、一般の方が売主の中古物件の売買においては領収証の準備は仲介業者の役目となりますので注意が必要です。
領収書の作成においては、金額の記載や収入印紙の貼付まで済ませ、契約時には署名・捺印をもらうだけの状態にしておきましょう。
収入印紙の購入
契約に係わる書類の準備が整ったら、続いては売買契約書に貼付する収入印紙を準備することになります。(印紙税に関する詳細は別記事「不動産の印紙税について解説致します!」をご参照ください)
買主に対しては必要な印紙代を知らせ、その費用を契約時に現金でお持ちいただきくことになりますが、印紙自体は仲介業者が事前に購入しておくのが通常です。(一般の方が売主の場合は、売主分も同様に準備する)
なお今回は売主が建売業者ですから、印紙代節約のため契約書を2部作らないケース(原本を買主が保有し、売主はコピーのみを受け取るパターン)も多いので、事前の確認を必ず行うようにしましょう。
ちなみに2部作る場合でも、売主分の印紙を「仲介業者に用意して欲しい」という建売屋さんは稀です。
売買契約の事前打ち合わせ
契約日を迎えるに当たっては、下記の事項についても打ち合わせを行っておく必要があるでしょう。
契約時間の設定
売買契約締結においては、重要事項の説明を終えた後に、契約書の読み合わせを行い、これに売主と買主が署名・捺印を行うという段取りになります。
但し、重要事項の説明には売主が立ち会わないのが通常ですから、例えば18時からの契約予定なら、17時には買主に来店をお願いして重要事項を説明を開始し、18時までにこれを終えましょう。
そして18時に売主が登場して、契約書の取り交わしを行うというのが一般的な流れとなります。
契約時の持ち物の確認
契約日時が決まったら、持ち物についての連絡を行いましょう。
- 認印
- 手付金/現金または預金小切手
- 仲介手数料/契約時に支払いがある場合のみ
- 写真付き身分証明書
- 契約書に貼付する収入印紙/または印紙代
以上が契約時の売主・買主の主な持ち物となりますので、事前に書面などで通知するようにしましょう。
なお、近年では手付金を振込みで支払うケースも増えつつありますので、この場合は買主が契約前に売主の口座に振込みを行い、振込控えを契約に持参することになります。
買主への説明事項についての事前打ち合わせ
重要事項説明は仲介業者の仕事となりますが、建売屋さんが売主の場合には、売主も重要事項説明書の説明者として署名・捺印を行います。
また説明する内容によっては、「売主が直接買主に説明した方がスムーズな事項」もありますので、例外的に重要事項説明に売主が立ち会ったり、契約書の読み合わせの前に売主から説明が行われる場合もあるでしょう。
なお建売住宅の場合には、瑕疵(建物の欠陥)に関する保険に加入するのがルールとなっていますが、保険に関する説明は売主が自ら行うことも多いため、「どの説明を誰が何時のタイミングで行うのか」も、売主と事前に打ち合わせておくとスムーズです。
一方、売主が一般の方である場合には仲介業者が全ての説明を行いますが、近隣との申し合わせ事項や建物の不具合については売主しか知らない事項も多いため、契約前に徹底したヒヤリング調査を行い、説明に漏れがないよう注意しましょう。
ローン借入れ先金融機関との打ち合わせ
買主が住宅ローンを利用する場合、不動産の売買契約書には借入れ先の金融機関の名称や支店名、融資額や借入れ期間などを記載することになりますので、契約前の銀行との打ち合わせも必須となります。
また、住宅ローンの本審査は売買契約締結後に行われることになりますが、契約の条件次第では融資の承認が降りないケースもありますので、「境界確定を行わない」「建物の増築未登記部分をそのまま引き渡す」などの特殊な条項が契約書に入る場合には、銀行の担当者と綿密な打ち合わせが必要です。
なお、買主はこうした作業に不慣れですから仲介業者は銀行との打ち合わせに同席したり、直接交渉の窓口となることも珍しくありません。
重要事項の説明
こうして契約締結の当日を迎えたら、最初に行うべきは買主に対する「重要事項の説明」となります。
まずは宅地建物取引士証を提示し、「宅建業法35条における重要事項説明を行います」と宣言した上で、重要事項説明書を読み上げて行くことになるでしょう。
この際、単に文言を読んでいくだけの方も多いようですが、大切なのは後でトラブルにならないことです。
いくら正確に記載し、これを大きな声で読み上げても、お客様が理解していなければ意味がありません。
よって、説明書の文言を自分の言葉で噛み砕き、誰が聞いても誤解のない説明を心掛けましょう。
また、不明点があるのに話が先に進んでしまうと「お客さんはなかなか言い出せない」ものですから、一定のスパンで説明を区切り、質問が無いかを確認しながら話を進めましょう。
なお、自分が知らない点を買主にツッコまれた場合には適当な回答はせず、「売主さんが到着したら聞いてみましょう」などの言葉で切り抜けるのがおすすめです。
※契約時に取り交わす書類は山程ありますので、売主の到着が遅れたり、重要事項説明が早く終わってしまった時には、買主が行うべき署名・捺印をできる限り済ませておくのが得策でしょう。
不動産売買契約書の読み合わせ
重要事項の説明が終わり、売主が到着すれば売買契約書の読み合わせとなります。
こちらも重要事項の説明と同じく、文言を読み上げるだけではなく、契約内容を正確に理解してもらうことが重要です。
よって、一つの条項を読み上げたら、自分なりの言葉で簡単に契約条項の要点を解説するなどの方法がおすすめでしょう。
そして読み合わせが終わり、買主からの質問が無いようなら、各書類(売買契約書・重要事項説明書・媒介契約書・仲介手数料支払い承諾書・物件状況報告書・付帯設備表・手数料領収証)の署名・捺印作業に取り掛かります。
なお、取り交わすべき書類はかなりの数に及びますので、売主・買主の手が止まらないように「次々と書類を回して行く」のがスムーズな進行のコツとなるでしょう。
また、まずは全ての書類に「署名だけ」を頂き、次に「捺印だけ」を頂くという順序で効率的に署名・捺印の作業を完了させてください。(一つ一つの書類に順番に署名・捺印を行っていると非常に時間が掛かります)
ちなみに、仲介業者はこの際に売主・買主の本人確認書類(免許証・会社謄本)などのコピーを取ることも忘れないようにしましょう。
※売主からの媒介契約書・仲介手数料支払い承諾書への署名捺印作業は、買主からなるべく見えない場所で行いましょう。売主・買主両者から手数料をもらうことに不満を感じる買主も存在します。
手付金の受け渡しと解散まで
売買契約書等の書類への署名捺印が完了したら手付金の支払と、領収証の受け渡しを終えて契約は終了です。
なお、手付金が現金の場合には必ず売主に「現金を数えて確認」してもらうようにしましょう。
そして書類の受け渡し等が完了したなら、このタイミングで少し談笑を行って売主・買主間の距離を縮めつつ、融資関係書類を金融機関に持ち込む予定日や建物の内覧会の日程打ち合わせなどを行なって、解散となります。
但し、売主はここで退席しますが、買主は住宅ローンの本申込み書類の作成などが残っていますので、申込み書類への記入と金銭消費貸借を行う日取りの打ち合わせをして、買主も退席という運びになります。
スポンサーリンク
不動産売買契約の流れ・注意点まとめ
さてここまで、不動産売買契約の流れや注意点を解説してまいりました。
冒頭でもお話した通り、契約前であればいくらでもやり直しが効くことが、契約締結後は取り返しのつかないことになってしまうケースも少なくありませんから、しっかりと気を引き締めて当日に臨んでいただければと思います。
ではこれにて不動産売買契約の注意点や流れについての知恵袋を閉じさせていただきます。