不動産を「買う人」「売る人」共に避けて通ることができないのが、 売買契約の締結というイベントですよね。
そして、本ブログでは以前に不動産業者さんへ向けた売買契約書のポイント解説記事をお届けしましたが、「一般の方に向けた記事も書いて欲しい」とのご意見も多数いただいておりました。
そこで本日は、売買契約書の中でも最も解り辛く、重要度も高い「契約解除」に関する条文を一般の方向けにわかりやすく解説していきたいと思います。
では不動産売買契約解除の知恵袋をスタートさせましょう。

不動産売買契約には5種類の解除が定められている
さて、読者の方の中には「契約の解除と聞いても、今一つピンとない」という方もおられることでしょう。
そもそも契約とは「約束ごと」という意味になりますが、その約束を『当事者の一方の意思表示によって(契約時に遡って)消滅させること』が契約の解除となります。
さて、この契約解除ですが不動産売買の契約書には、5種類もの解除に関する条項が盛り込まれているのです。
ちなみに売買契約書全体を見渡してみれば、その条項数は16条程度が平均であり、多いものでも20条を超えないものが殆どですから、契約書全体の20%~40%が解除に関する条項で占められていることになります。
なお、この5つの解除条項が1条、2条、3条と並んで書かれていることは稀であり、通常は「バラバラに散りばめられた状態(5条、9条、12条といった具合)」で盛り込まれることになりますから、説明を受ける内に頭がパニックになってしまうのも当然のことでしょう。
そこでまずはこの5つの解除条文を個々に解説して行くことにいたします。
不動産売買契約の手付解除
こちらの解除条文は、売買契約を締結した際に支払った手付金を放棄することで、売主・買主は契約を解除することができるという内容のものです。
なお、この手付解除には「解除可能な期限」が設けられるのが通常であり、売主が不動産会社でない場合には契約締結から7日~14日程度の期間は解約ができると定められることが多いでしょう。(これを手付解除の期日と呼びます)
そして、この期間内であれば買主は支払った手付金の放棄することで、また売主の場合は既に受け取っている手付金を買主に返還した後、同額を改めて買主に支払うことで契約の解除が可能となります。(手付の倍返し)
但し、売主が不動産業者である場合には、手付解約の期日を設けることが法令で禁じられているため、「売主・買主のどちらかが契約の履行に着手するまで」という文言が、手付解除期日の代わりに書き込まれることになるでしょう。
さて、ここで気になるのが業者売主のケースにおける「履行の着手」が何時の時期であるかということですが、実はこれに明確な答えはありません。
もちろん裁判などになれば、個々の案件ごとに取引のどの段階が履行の着手であったかの判定がなされますが、判例を見ても「中間金を支払ったタイミング」であったり、「土地を分筆」した際であったりと状況によって様々であるため、あまり参考にはならないのです。
なお私の経験上から言えば、建売物件の売買の場合はお客様(買主)名義で建物の表示登記を申請した時、又はお客様の好みで建物にカスタマイズ(建物変更工事)を加えたタイミングなどが、『履行に着手した時期』であると判断されるケースが多いように思われます。
不動産売買契約の住宅ローン解除
買主が金融機関の住宅ローンを利用する場合に加えられるのが、こちらの解除条項となります。
住宅ローンの申請は売買契約締結後にしか本申込みができませんので、融資の審査に落ちた場合には、売買契約を白紙解約することができるという内容です。(手付金も売主から買主に返還される)
ちなみに住宅ローンの審査は通常7日間もあれば結果が出て来ますので、契約締結から10~14日後の日付にて、ローン解約の期日が設定されることが多いでしょう。(近年はネット銀行の利用者が増えたため、1ヶ月程度の期間が設定されることも多くなりました)
なお、「実際は融資の承認が下りているのに、虚偽の申し出によってローン解約に持ち込んだ」というケースでは、後述する違約解除と判断されペナルティーを負わされることもあります。
こうした事情から、住宅ローンの解除条項には「利用する金融機関の名称と支店名」、そして「融資の申込みを行う金額」なども記されることが多く、状況によっては売主側の仲介業者が『本当に融資が否認されたかの確認を金融機関に行う場合』もあるのです。
★当ブログ管理人執筆の電子書籍(kindle)のご紹介!是非ご一読ください!★
 |  |  | 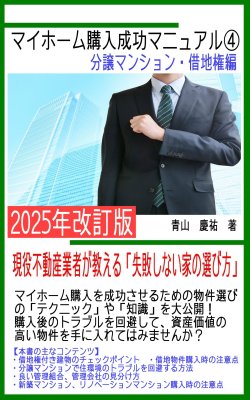 |
不動産売買契約の物件の滅失による解除
買主・売主どちらの責任でもなく、売買対象物件が滅失してしまった場合の解除条項です。
建物であれば放火によって燃えてしまった、地震で倒壊してしまった場合、土地であれば地割れが生じて今後の土地利用ができないケース等で、この解除条項が適用されることになります。
滅失解除となった場合には、契約は白紙解約となり、手付金などの受け渡し済みの金員も返還されることになります。
ちなみに2020年の民法改正以前は、この解除条項が記されていない契約書で物件の滅失が発生した場合、民法の定めにより「滅失した物件を買主が予定通りの価格で買取らなければならない」という解釈でしたので、滅失解除は買主保護のために組み込まれていた条項だったのです。(民法改正後は滅失解除条項がなくとも買主からの解除が可能)
なお、滅失解除は「売主・買主共に責任がない滅失」であることが条件となりますから、売主の寝たばこが原因の火災などにおいては管理義務(売主には契約を結んだ物件を引き渡すまで、管理を行う義務がある)に違反したという理由で、次項で解説する債務不履行解除が適用される可能性もあります。
不動産売買契約の債務不履行(違約)による解除
売主・買主のどちらかが契約違反をした場合の解除条項となります。
売主であれば「売買代金を受け取ったにも係わらず、物件を引き渡さない」、買主の場合であれば「残代金を支払わない」ケースなどで、債務不履行解除が適用されることになるでしょう。
但し、債務不履行による解除は催告(履行を促す行為・催促)をした後でなければなりませんので、約束違反が即解除に結び付く訳ではありません。
なお、違約金の金額は契約ごとに異なりますが、売買価格の10%~20%程度に設定されるのが一般的でしょう。
以前は違約金の額を売買価格の20%とするのが一般的でしたが、実際に20%の違約金の支払いを求めた裁判において、裁判所は10%の違約金支払いしか認めなかった判例があり、これ以降は10%と定める契約書を多く見掛けるようになりました。
また、債務不履行解除においては「この条項で定めた違約金を、違約金の最高限度額とする」のが通常です。
よって、債務不履行によって生じた損害が違約金の額(売買代金の10%や20%)を上回る場合でも、契約書に定めてた以上の違約金を請求することはできません。
ちなみに違約金が発生するのは、違約した側の当事者に帰責事由(明確な落ち度)があった場合に限りますので、この点にはご注意ください。
不動産売買契約の契約不適合責任による解除
不動産売買においては、引き渡しが済んだ後で建物や土地に大きな欠陥(雨漏りや土壌汚染など)が明らかになることも珍しくありません。
そして、こうしたトラブルが発生した場合には売主が契約不適合責任(契約の主旨に反する物件を売ってしまった責任)を問われることになるのですが、こうしたケースでは買主に損害賠償や代金減額請求、追完請求などに加えて、契約を解除する権限も与えられることになります。
但し、契約不適合責任については特約を結ぶことで、ある程度自由な取り決めを行うことが可能ですから、契約書によっては「物件購入の目的が果たせない場合にのみ、契約を解除することが可能」といった条項が定められている場合もありますのでご注意ください。
ちなみに不動産業者が売主の場合には、宅地建物取引業法により「民法よりも不利な内容の取り決めは無効」というルールがありますので、契約不適合責任に関する条文のカスタマイズはほぼ不可能となっています。
※契約不適合責任についての詳細は別記事「契約不適合責任とは?わかりやすく解説いたします!」をご参照ください。
スポンサーリンク
不動産売買契約の5つの解除要件と時期のまとめ
さて、ここまで解説をしてまいりました5つの条項が、売買契約書に記載される基本的な解除条項となります。
なお更に厳密に言えば、「契約当事者が暴力団関係者であった場合などに適用される解除条項」もありますが、少々特殊な解除条項となるため、今回はご説明を省かせていただきました。
ちなみに、これまでのお話にて「5種類の解除がある」ということはご理解いただけたことと思いますが、「それぞれの解除条項同士がどのような関係あるか?」という点については、今一つ把握できていないという方も多いことでしょう。
そこで次項では、これらの解除条項の相関関係を解り易くまとめてみたいと思います。
解除可能な時期によるまとめ
5種の解除条項の関係を理解する上では、契約の何時の段階で解除が可能なのかを知ることも重要なポイントとなりますので、時系列順に解説を加えて行きましょう。
但し、個人間売買と不動産業者が売主の売買では、若干異なる点もありますので、それぞれのパターンに分けてお話しして行きます。
個人間での売買の場合
契約締結日→手付解除可能期間(7~14日後まで)→ローン解除(10~14日後まで)→違約解除(引渡し完了まで)→契約不適合責任による解除(主に引渡し後)
※滅失解除は契約締結から引渡し完了直前まで何時でも解除が可能
建売等の場合(売主が不動産業者の場合)
契約締結日→ローン解除(10~14日後まで)→手付解除可能期間(表示登記申請・建物変更工事まで)→違約解除(引渡し完了まで)→契約不適合責任による解除(主に引渡し後)
※滅失解除は契約締結から引渡し完了直前まで何時でも解除が可能
ペナルティー別のまとめ
続いては、解除によって発生するペナルティーという切り口にて解説を行います。
- 手付解除 ・・・手付金放棄
- ローン解除 ・・・ペナルティー無し
- 物件の滅失による解除 ・・・ペナルティー無し
- 債務不履行による解除 ・・・売買価格の10~20%の違約金(帰責事由が必要)
- 契約不適合責任による解除・・・買主が受けた損害に応じて解除と共に損害賠償請求が可能(帰責事由が必要)
このように条文を分類しながら整理してみると、これまで「今一つピンと来なかった解除条項の内容」について理解を深めることができたのではないでしょうか。
マイホームの購入は一生に一度の大切なイベントですから、契約書の内容をしっかりと理解し、トラブルのない取引を目指したいものです。
ではこれにて、不動産売買契約解除に関する事項をご説明!する知恵袋を閉じさせていただきたいと思います!