不動産の取引において、一つの山場となるのが重要事項説明・売買契約の締結というイベントとなります。
「重要事項の説明」が、取引上のトラブルを回避するために物件について詳細な説明を行うものであるのに対して、
『売買契約書』は取引条件を明文化することによって、後々のトラブルを回避し、売買をスムーズに進めるための書面となりますから、その重要性は改めてご説明するまでもないでしょう。
しかしながら、重要な約束ごとをギッチリと条文に盛り込むとなれば非常に難解な文言となってしまうのは当たり前のことであり、一般の方である売主・買主にとってはもちろん、場合によっては仲介に入る不動産業者にとっても、その内容をすんなりと理解できないケースがあるものです。
そこで本日は、「不動産売買契約書の作り方について解説いたします!」と題して、契約書作成のポイントや注意点についてご説明していきたいと思います。

不動産売買契約書の内容解説と作り方のポイント
では実際に、一般的に用いられる不動産の売買契約書の内容を解説しながら、ポイントとなる部分についてお話をしてまいります。
売買対象・価格の表示
多くの売買契約書のひな形においては、その冒頭で取引対象となる「不動産の概要」と「売買価格」、そして「誰が売主・買主であるか」等の表示がなされているはずです。
土地であれば、
- 地番/土地の筆ごとに振られた番号
- 地積/土地の面積、公簿面積と実測面積の2種がある
- 地目/登記簿上の土地の種類
- 持分/所有権の割合 等
などとなりますし、
建物に関しては、
- 所在地/建物の所在地
- 家屋番号/建物ごとに振られた番号
- 種類/居宅、店舗などの建物の種類
- 構造/木造、鉄骨造等の構造
- 床面積/1階部分●●㎡、2階部分●●㎡、合計●●㎡といった建物面積の表示 等
が主な記載内容となるでしょう。
なお、ここでご注意いただきたいのが土地や建物に関する情報のソースをはっきりとさせることです。
対象が建物であるならば「公簿(登記簿に記載されたもの)なのか、建築確認によるものであるのか」、土地ならば「実測面積であるのか、公簿面積でなのか」等をしっかり明記しておきましょう。
そして売買対象の特定が完了したら、「売主は買主に対して、物件を●●●●万円で売り渡します」という契約の目的が記されることになります。
売買対象面積
前項において、取引対象となる物件の定義は完了しましたので、この条項においては「売買対象面積を明確にする」ことが目的となります。
先程もお話しましたが、土地ならば登記簿上の面積である「公簿」と、実際に測量を行った結果の「実測」という情報ソースの違いによって、その面積に差異が生じることも珍しくありません。
また建物についても「公簿面積」と「建築確認上の面積」では違いがあるものです。(公簿面積ならば建物の内法の面積となり、建築確認では壁芯【壁の中心から測った】面積となる)
そこでこの条項では、取引の前提が「公簿であるのか(公簿売買)」、あるいは「実測であるのか(実測売買)」を限定することとなります。
なお、公簿売買を選択した場合には「公簿面積」と「実測面積」の間に差異が生じた場合の対処方法を定めておくことも重要です。
さて、このようにご説明すると「公簿と実測に差が出るの?」というお声も聞こえて来そうですが、古い年代では測量技術も未発達でしたし、残地(分筆後に残された)に至っては公簿面積と実測面積が符合するケースの方が稀と言って良いでしょう。
よって通常は、後々のトラブルを避けるために『公簿免責と実測面積に差異が生じても精算は行わない上、売主は面積(数量)の差異については契約不適合責任を負わない』との文言が条文に加えれることになります。
更に契約不適合責任においては「取引対象の品質・種類・数量」について売主が責任を負うことになりますから、「謄本上の建物の種類」と「建築確認上の建物の種類」に違いが生じた場合に備えて、『建物の種類について売主は、契約不適合責任を負わないものとする』という文言を加えておけば完璧でしょう。
ちなみに、『公簿面積と実測面積に差が生じた際に精算を行う場合』には、想定外の「値上げ」や「値下がり」によって取引上のトラブルに発展するケースもありますから、事前の説明を充分に行っておく必要があります。
※宅地建物取引業法40条の定めにより、不動産業者が売主の場合には「数量以外についての契約不適合責任免責特約は無効」となります。
売買代金の支払時期
売買代金の総額は「売買対象・価格の表示」にて謳っているはずですが、手付金や中間金が発生する取引では、今後の支払スケジュールについても明文化しておく必要があります。
金額を記載することはもちろんですが、「手付金は契約時」「残代金は●月●日まで」など、日程についてもしっかりと記載するようにしましょう。
手付金と手付解除
不動産売買の代金支払い方法については、「一括払い」というパターンも無くはありませんが、殆どの場合は契約時に手付金を支払い、決済時に残代金を支払うという形式が執られます。
そしてこの条項では、手付金の定義と手付放棄による契約解除についての取り決めがなされます。
なお、多くの契約書では「手付金の定義」と「手付解除」を別々の条項で謳うのが通常ですが、今回は混乱を避けるために一気にご説明してしまいます。
「手付金の定義」については、「金額」と「支払時期(通常は契約締結時)」、そして「後に残代金の一部に充当される」こと及び、「手付金が売主に渡された後も利息が付かない」旨を取り決めるのが一般的です。
一方「手付解除」については、「●月●日までなら買主・売主共に手付金を放棄することで、契約を解除することできる」旨が謳われます。
また、実際に手付解除となった場合には、買主は売主に手付金を預けていますから、改めてアクションを起こさずとも「手付の放棄で解除は完了」となりますが、
売主が解除する場合は「一旦受け取った手付を買主に返還し、同じ額を改めて買主に支払う」という、俗に言う「手付の倍返し」という方法が執られます。
ちなみに、売主が不動産業者である場合には、「●月●日までなら手付の解除が可能」という期間の定めを記載することが禁じられておりますので、
「売主・買主のどちらかが契約の履行に着手するまでは解除が可能」という曖昧な表現が用いられることになるでしょう。(「履行の着手」と見なされるタイミングについては、個々の取引によって判断が分かれることになります)
※手付解除の詳細については「不動産売買の解除」に関する記事をご参照ください。
所有権の移転と引渡し
こちらも「所有権移転登記」と「引渡し」など、別々の条項で取り扱われるケースが多いのですが、まとめて解説をしてしまいます。
取り決めを行う内容としては「何時の段階で」、そして「どのような状態で引渡しを行うか」、また「登記費用は誰が負担するか」などを定めることになるでしょう。
引渡し時期
引渡し時期については、買主からの「残代金全額の支払い」と同時に、売主が「引渡しを行う」のが原則です。
なお、ここいう引き渡しとは「物件の引渡し」と「買主への所有権移転登記」の両方を指します。
引渡しの状態
土地の境界を売主が明示した上で、抵当権や質権等、「買主の物件利用を邪魔する権利」を外しておく(権利を抹消する)ことが通常の条件です。
また、「物件の使用・収益も引渡しの日をもって、買主がこれを行うことが可能となる」と定めるのが一般的です。
登記費用の負担区分
「所有権移転登記」は買主の負担となる一方、「分筆や合筆等表示に係る登記」が必要な場合には、売主がその費用を支払うのが一般的な条件となります。
公租公課の精算について
物件が引渡される際に、売主・買主間で授受される精算金について取り決めを行う条項となります。
この精算の対象となるのは「固定資産税」「都市計画税」、そして「電気代」「ガス代」「水道代」等が主なものとなるでしょう。
但し、分譲マンションの場合には、これに加えて「管理費」や「修繕費」、投資物件なら「賃料」や「敷金」等が対象となります。
※具体的な精算内容については過去記事「固定資産税の計算方法や課税の仕組みについて解説いたします!」をご参照ください。
なお、固定資産税・都市計画税の精算に関する起算日は、関東が1月1日、関西で4月1日という取引慣習上の違いがある点も注意しておきたいところです。
住宅ローンによる解除
買主が物件購入に際して、住宅ローンを利用する際に追加される解約条項となります。
内容的には「住宅ローンが否認されれば売買契約は白紙解約となり、手付金も買主に返還される」というものになりますが、ポイントは『虚偽のローン解約を防止する内容を盛り込んでおく』という点でしょう。
買主の中には、「他に良い物件が見付かったので、ローンが否認されたことにしてしまえ」という不届き者もおりますから、どこの銀行・支店にいくらのローンを申し込んだかを契約書に明記するようにしましょう。
買主から「ローンの審査に落ちた」との知らせがあった場合には、申し込み先の金融機関に問い合わせを行い、真偽の程を確認するのも仲介業者の大切な仕事となります。
また、契約書上ではローン解約の期日(ローン解除がいつまで可能であるか)も記載することになりますが、必要以上に長い期日は設定しないようにしましょう。(通常は契約から2~3週間程度の期間となります)
なお、ローン解約条項には「解約権があるのは買主だけ」という契約書のひな形も多いのですが、これではローンが否認されているのに、売主からは何もアクションを起こせないことになってしまいます。
よって、売主の保護を考えるのであれば「売主・買主、共に契約を解除することができる」という文言にしておくべきでしょう。
物件の滅失による解除
売主・買主、どちらの責任にもよらない火災や自然災害などにより、物件の引き渡しが困難になってしまった場合の解除条項となります。
この条項でのポイントは、売主・買主互いに損害賠償の請求ができないという点と、これに該当する事態が発生した場合には手付の即時返還が行われる点になるでしょう。
なお、契約書作成時には他の解除条項と同様、売主・買主共に解除権を設定しておくのが賢明です。
また建売屋さんが売主のケースでは、「修復可能であるならば、売主は修繕を行った上で物件を引き渡すものとし、この場合には買主からの契約解除はできない」などの文言を契約書に加えて欲しいとの要望が出ることもありますが、買主にとって不利な内容となりますから、条文の解釈を巡って訴訟などに発展した際には「無効」と判断される可能性が高いでしょう。
よって、このような条文の追加を求められた場合には、丁重にお断りするべきかと思います。
※2020年の民法改正以前は、この「物件の滅失による解除」の条項が契約書に組み込まれていない場合には、「買主からの契約解除は認められず、滅失した物件に対して予定通りの代金を売主に支払わねばならない」というのが民法上の解釈でしたので、この条文は契約上非常に大きな意味を持っていました。
※放火などによって物件が滅失した場合には、この条項が適用されますが、売主の煙草の不始末などが原因の場合には後述する債務不履行解除が適用されるケースもあります。
★当ブログ管理人執筆の電子書籍(kindle)のご紹介!是非ご一読ください!★
 | 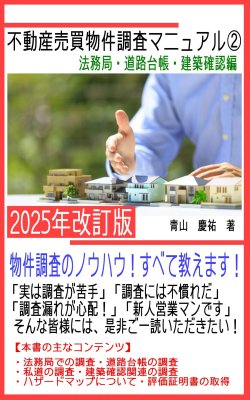 | 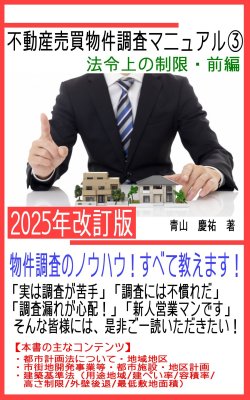 | 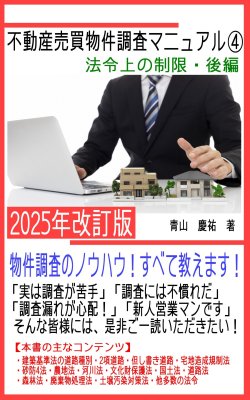 |
債務不履行による解除
解除に関する条項が続きますが、こちらは「債務不履行」、つまり契約上の約束違反があった場合の解約条項となります。
契約を締結したにも係らず、「買主が期日までに残代金を支払わない」「売主が物件を約束通りの状態で引き渡さない」といった事態が発生した際には、この条項が適用されることになるでしょう。
ちなみにこの条項では「違約金の額」を定めることになりますが、ひと昔前なら売買代金の20%、最近では10%という違約金の額が相場となりつつあるようです。
※「不動産売買における20%の違約金の正当性」について争われた裁判において、裁判所が「10%が妥当である」との判断を下したため、この判例の影響により違約金を10%とするケースが増えています。
また、この違約金を請求するには「相手方に帰責事由(故意や重大な過失)がある」ことに加え、「催告(契約を守りなさいという催促)」が必要となります。(民法上、催告なしでの違約金の請求は認められないのが原則であるため)
※違約金の請求には帰責事由が必要ですが、解除自体は帰責事由がなくとも可能です。
なお、違約金については「損害の大小に係らず●●%を違約金の額とする」という文言も入れておくべきでしょう。
これは、トラブルが発生した場合に「私の損害は●●%などでは収まらない!」などと主張されるのを防ぐ目的の文言であり、売主・買主双方を保護するためにも違約金の上限は定めておくべきです。
更に、次項で解説する「契約不適合責任による解除」と明確な区別を付けるために、『契約不適合については、本項に定める解除は適用されないものとします』との文言を加えておけば完璧でしょう。
※売買契約書における解除条項については、別記事「不動産売買契約解除に関する事項をご説明!」にて詳細な解説を行っております。
契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)
ご存じの方が多いと思いますが、瑕疵とは「物件の隠れたキズ(欠陥)」を指す言葉です。
そして、こうしたキズに関して売主が買主に対して負う責任のことを「契約不適合責任」と呼んでいます。
契約不適合責任の免責と期間の定め
さて、このに契約不適合責任に係わる条文を作成するに当たって、まず問題となるのは「売主が責任を負う期間」ということになりますが、一般の方が売主の場合には3ヶ月から半年程度が通常となるでしょう。
※一般の方が売主で、物件の老朽化が進んでいる場合には「瑕疵担保免責」という特約が定められることもあります。
一方、売主が不動産業者の場合で、売買対象が中古物件のケースでは「引渡しから2年間責任を負う」となるのが一般的でしょう。
実は、売主が不動産業者の場合には「引渡しから2年間」との特約を明記しなければ、瑕疵の存在を知った時から1年(たとえ引渡しから何年経っても、知った時から1年間)という超長期間の契約不適合責任を負わされてしまうのがルールとなっているため、2年間とせざるを得ないのが現実です。
ちなみに2年間より短い期間を設定した場合には、法律上は「知った時から1年」と解釈されてしまうので、お気を付けください。
※契約不適合責任の時効は「賠償請求等が可能であることを知った時から5年」、「請求ができる時から10年」となっていますので、この期間を経過すれば責任を逃れることが可能です。
なお、建売(業者売主の新築物件、新築分譲マンション)の場合には「構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分」、つまり建物の骨組みや基礎、雨漏りに関する部分については10年間の契約不適合責任を負うこととなっています。
ではここで一旦、契約不適合責任の免責と期間の定めについて整理をしておきましょう。
- 一般の方が売主の物件・・・瑕疵担保免責の契約が有効、期間を定める場合は3~6ヶ月とするものが多い。
- 不動産業者売主の中古物件・・・引き渡しから2年以上の瑕疵担保責任を負う期間を定める必要あり。
- 不動産業者売主の新築物件・・・建物の主要な部分は10年以上、その他の部分については2年以上の期間、瑕疵担保責任を負う必要がある。(但し、消耗品などについては2年以下とすることも可能)
※契約不適合責任の詳細については別記事「契約不適合責任とは?わかりやすく解説いたします!」をご参照ください。
契約不適合責任条文のカスタマイズについて
民法上、契約不適合責任について、買主は売主に
- 契約解除/軽微な瑕疵でなければ解除可能
- 損害賠償請求/売主に帰責事由があれば請求可能
- 追完請求/物件の修補(修理)、不足分の引渡しの請求
- 代金減額請求/価格の値引き
上記の4つの方法により、責任を負わせることができると定められています。
但し、この民法の定めをそのまま契約書に反映してしまうと、実際にトラブルが発生した際に「選択肢が多過ぎて、どの方法を選択すべきか」が非常に難しい判断となりますし、「売主と買主の間で意見が分かれる(売主は修理を希望するが、買主は代金減額を求める等)」ことも想定されます。
また、一般の方が売主である場合には「民法上の定め」を特約によって自由に変更することが可能となりますで、通常の売買契約書においては下記のようにカスタマイズされた条文となっているケースが多いはずです。
- 買主は修補の請求をすることが可能
- 売買の目的が達成できない場合においては契約解除が可能
- 売主に帰責事由があるときのみ損害賠償請求が可能
- 「解除+損害賠償請求」「修補+損害賠償請求」も売主に帰責事由があれば可能
なお、これはあくまでも一般的なひな型となりますから、取引の態様や物件の特性に合わせて条文を変更されている可能性は充分にありますし、取引の相手側から条文の変更を求められるケースもあるでしょう。
ちなみに、不動産会社が売主の場合には「民法よりも不利な特約は無効」という宅地建物取引業法40条の定めがありますので、こうした契約書のカスタマイが行われることはありません。
物件状況と付帯設備について
売買契約の締結に当たっては、
- 物件状況報告書/土地の履歴(水害の被害等)や建物の欠陥(雨漏り等)などの物件状況を確認する書面
- 付帯設備表/給排水設やインターフォン、給湯器などの設備の故障の有無を確認する書面
上記2つの書面にて、売主が物件状況と設備についての告知を行いますので、『売主は買主に物件状況報告書を交付して、物件状況の告知を行うものとします』といった条項を加えておく必要があるでしょう。
一方、付帯設備については『付帯設備表に基づいて設備の引渡しを行うものとします』という書き方になりますが、付帯設備の不具合まで契約不適合責任の範囲に含めてしまうと、引渡し後のトラブルの原因となりますので、『但し、売主は付帯設備の不具合や故障について契約不適合責任を負わないものとします』との特約を入れるのが一般的です。
※不動産業者が売主の物件では表記のような免責特約は認められませんので、アフターサービスの基準を買主に伝えることになります。
但し、契約不適合責任においては「売主が知っていた不具合については免責特約が無効になる」というルールがありますので、免責特約を盛り込んでも付帯設備表を作成して、知っている不具合は全て告知することが重要となります。
瑕疵保険
建売住宅などでは買主保護の観点から、前項で解説した売主の負う「10年間の契約不適合責任」に対して、売主自ら保険に加入することを義務付けられています。(瑕疵保険に加入しない場合には、所定の供託金を納める必要があります)
また、このルールが定められたことに伴い、売買契約書においても「売主の加入する瑕疵保険の内容を明記すること」が義務付けられることになりましたので、この条項では売主が加入する保険内容の説明がメインとなります。
但し、ここで注意すべきは「売主が倒産した等の事情」がない限り、瑕疵保険によって保険金が支払われる相手はあくまでも売主であるという点です。
よって、「瑕疵が発見されも、売主の会社が健全な状態である場合には、買主に保険金が入ることはなく、売主が自己の責任と負担で契約不適合責任の補償にあたること」を覚えておいてください。
契約書作成費用
契約書には売買価格が記載されているため、印紙税の課税対象となります。
よって通常は、「契約書は2通作成し、売主・買主はこれを一部ずつ保有し、各々印紙代を負担する」という条項が必要となるはずです。
但し、売主が建売屋さんである場合には、原本はお客様のみ、売主はコピーを保有することにして、契約書を一通しか作成しないケースもあります。(印紙を貼付しなければならないのは原本のみ)
よって、「契約書の原本を何通作るか」によって文言の内容は変わって来ますので、この点には注意が必要です。
なお、1通作成なら原本を持つ者が印紙代を負担、2通以上作成なら印紙代を各々負担するのが通常となります。
反社会的勢力についての条項
まずは条項の冒頭で、売主・買主が反社会的勢力の構成員、またはそれに類する団体に所属していないことの確約を行います。
なお、法人契約の場合もありますから「役員等が反社会的勢力でないこと」と、「名義貸し」の契約でない旨の確約も同時にとっておきましょう。
そして、『この確約が破られた場合や物件を暴力団事務所として使用した場合の契約解除に関する定め』を盛り込んでいきます。
反社会勢力の問題が何かとクローズアップされる昨今ですから、必ず入れておくべき条項となりますが、
- 無催告解除が可能
- 違約金は売買価格の100%
- 解除に対する損害賠償は不可
- 物件の返還、所有権の抹消登記を行う義務
といった厳しいペナルティーを課しておいて損はないかと思います。
その他の条項
「管轄裁判所の取り決め」「諸規定の継承」「信義則」などの条項がこれにあたりますので、以下で簡潔に解説してまいります。
管轄裁判所の取り決め
物件の売買を巡って紛争となった場合に「事件を管轄する裁判所を定める条項」であり、通常は『物件所在地を管轄する裁判所とする』と記することになります。
諸規定の継承
不動産を購入するということは、物件に課せられる「法令上の制限(国や自治体などが定める建築や土地利用に関するルール)」や「近隣との打ち合わせ事項」なども受け継ぐことになりますので、契約書においては「買主は諸規定を継承するものとする」という条項が必要となります。
信義則
「売主・買主お互いに誠意を持って取引に臨む」という、契約の基本ルールを定めた条項となります。
特約事項
そして契約書の最後に記されるのが特約事項(それぞれの取引に個別に設定される約束事)となります。
なお特約事項に関しては、説明にかなりの文章的なボリュームが必要となりますので、別記事「不動産契約書特約条項の書き方」にて、改めて解説をさせていただきます。
スポンサーリンク
売買契約書の作り方まとめ
さて以上が、不動産売買契約書を作成する際のポイントとなります。
ひな形をベースに契約書を作っていると何気なくスルーしてしまいがちな条文も、このように要点をまとめることで「改めて気付かされる点」が多かったのではないしょうか。
また、一般の方にとっても、契約時にサラリと読み流されていく条項にどのような意味があるかを知ることは非常に重要なことかと思いますので、不動産の取引に際しては是非とも本記事をご活用いただければと思います。
不適切な内容で契約を取り交わしてしまうと、後々とんでもないトラブルに発展するケースもありますから、じっくりと練り込まれた売買契約書で失敗の無い取引を目指していただきたいものです。
ではこれにて、不動産売買契約書の作り方についての知恵袋を閉じさせていただきたいと思います!