一生に一度の大きな買い物と言われるのがマイホームなどの不動産の購入ですが、「不慣れ」な上に「重要な買い物」となれば『取引の流れくらいは事前にしっかり把握しておきたい!』と思うのは当たり前ですよね。
そこで本日は『物件探し』から『契約』、そして『引渡し』に至るまでの不動産購入の流れについて解説させていただきたいと思います。

マイホーム購入の希望条件を整理
マイホームの購入に際しては、まず「どのような物件を購入するか」を検討しなければなりません。
戸建てにするのか、分譲マンションにするのか、そして新築物件か中古物件かとその選択の余地は様々ですし、「マンションと戸建て両方を視野に入れて物件を探す」といった選択肢もあるでしょう。
なお、分譲マンションのご購入をお考えの方については別記事「分譲マンションのメリット・デメリットを解説!」を、新築戸建て(建売住宅)なら「建売の後悔しない選び方を解説!」、
中古戸建ては「中古戸建て購入の注意点について!」、そして新築・中古でお悩みなら「新築・中古どっちが得か?について解説します!」の各記事にて詳細な解説を行っておりますので、是非ご参考になさってください。
また、ここでポイントとなってくるのが売主が不動産業者である物件と、売主が一般の方である物件の違いについてとなります。
不動産業者が売主の物件
戸建てとマンション、そして新築・中古を問わず、マイホーム探しをしていると「売主が不動産業者である」という物件に数多く遭遇するものです。
新築物件については分譲主が不動産会社であるのが当たり前ですが、近年では中古のリノベーションマンションや戸建ての販売を行う不動産業者も少なくありません。
そして、こうした不動産業者売主物件を購入する場合には
- 売主から直接物件を購入する取引形態(仲介業者なし)
- 売主とは別の不動産業者を介して購入する取引形態(仲介業者あり)
のどちらかとなるはずです。
なお仲介業者が介入せず、売主と直接売買をするならば仲介手数料は不要となります。
一般の方が売主の物件
これに対して、一般の方(エンドユーザー)が売主の物件を購入する際には、仲介業者を介して物件を購入するのが通常です。
また、同じ仲介業者が介在する取引であっても
- 売主・買主間を1社が仲介するパターン
- 売主側の業者、買主側の業者と2社以上の仲介業者が介在するパターン
の2通りがあります。
このように不動産の購入に際しては、様々な「物件の種類」と「取引の態様」がありますので、まずは『自分が欲しい物件のイメージをしっかりと絞り込むこと』と『希望する物件がどのような取引態様で流通しているか』を把握することが重要となります。
マイホーム購入の資金計画を立てる
こうして購入希望物件のイメージが固まったなら、次はマイホーム購入に際しての資金計画を立てていきましょう。
まずは「現金でどれくらいの予算が準備できそうか」、そして「勤め先からの補助はあるのか」、「親からの援助や借入は可能か」といった点を整理していきます。
マイホーム購入となると、まずは住宅ローンの借入可能額や金利のチェックを行う方が多いですが、いくら金利が安いと言っても借金は借金ですから「それなりのリスク」もありますし、返済時には元本の1.5倍以上の金額を支払うことになりますから、資金計画を立てる上では『いかに住宅ローンの利用額を減らせるか』という点を重要視するべきです。
※個人が売主の物件については原則としてリフォームが必要となりますので、資金計画を立てる際には工事費用も計算に含めておいてください。
そして、物件を購入するために「どうしてもこれくらいの借り入れは必要だ」という金額がイメージできたら、銀行のローンシュミレーターなどを利用して『借入上限額を超過していないか』『月々の返済額に無理がないか』といった点をチェックしておきましょう。
なお、住宅ローンについては当ブログでも「住宅ローンの基礎知識をお届け!」、「住宅ローンの注意点を解説致します!」等の記事を公開しておりますので、融資を利用する際の基礎知識や注意点もしっかりと押さえておくべきです。
物件情報の収集と仲介業者選び
さて、ここまでの準備が整ったなら具体的な物件探しをスタートさせましょう。
物件探しの方法については「不動産業者の店舗に出向いて、希望条件を伝えて探してもらう」「ネット検索で物件を探し、内見の申込みを行う」「現地販売会を巡って物件を選ぶ」など、人それぞれの好みがあるかと思います。
そして、どんな方法であっても「自分にピッタリの物件を見付ける」ことができれば問題はないのですが、情報を提供してもらう不動産会社の選び方によっては『物件情報の質に大きな違い』が出る可能性がありますし、紹介してもらった物件を購入するとなれば『その会社が仲介を担当する業者となる』ので、不動産会社の選定だけはしっかりと行っておきたいところです。
なお、過去記事「不動産会社の選び方(購入時)について」でもご説明いたしましたが、同じ不動産屋さんでも「物件を売るのが得意な業者」もいれば、「マイホームの購入に特化した業者」もおりますから、不動産会社を探すに当たっては『目指す取引に適した業者を選択すること』が重要でしょう。
また、同じ「マイホームの購入に特化した業者」でも、未公開物件の情報量などについては会社ごとにかなりの違いがあるものです。
ちなみに未公開物件の情報入手方法については、別記事「未公開物件の情報を入手する秘訣をご紹介!」にて詳しく解説をしていますが、物件の種類(新築であるか、中古であるか等)によって情報を保有する業者の種類も変わってきますので、物件探しを依頼する不動産会社の業態をしっかりと見極める必要があるでしょう。
物件の内覧と買付証明書の作成
さて、情報提供を受ける不動産会社の選別が完了すれば、その後は気になる物件に対して内覧を行うことになりますが、
- 不動産業者が売主の物件(新築・中古を問わず)/いつでも内覧が可能で、空室の状態を見ることができる
- 個人が売主の物件(中古のみ)/居住中の場合が多いので原則時間は要相談、家人が生活する中で内覧を行う
以上のような違いがあることは是非頭に入れておいてください。
こうしてお気に入り物件を見付けることができたなら、次に行うべきは「物件購入の意思を売主側に伝えること」となります。
そして、不動産取引においてはこの意思の表示を「買付証明書(購入申込書)」という書式で行うこととなっており、『購入希望金額・購入時期・融資の条件』などを記載した書面を作成し、売主へこれを送付することになるのです。
なお時折、この買付証明書を書くことを躊躇されるお客様(購入の意思は固まっているが、買付証明書を書いたら後戻りができないのではないかと不安に感じるお客様)もおられますが、法的な拘束力のある書式ではありませんので、あまりビクビクする必要はありません。(法的な拘束力がないからといって、完全に意思が固まっていないのに「とりあえず買付証明書を書く行為」は道義的に問題ありますので差し控えるべきでしょう)
また、売買価格の値引き交渉(業界的には「差値【さしね】」といいます)を行うのは、このタイミングとなりますがあまりに法外な値引きを求めると買付証明書が受理されない可能性もありますから、仲介業者のアドバイスを聞きながら記載する購入希望価格を決定しましょう。
※最初に思い切った値引き交渉を行い、徐々に購入価格をつり上げて行くような行為は、売主からは非常に嫌悪されます。
※同じタイミングで似たような条件の購入希望者から買付証明書が届けば『早いもの順』になることもありますので、悩み過ぎているとチャンスを逃してしまうこともあります。
ちなみに買付証明書を送る際、住宅ローン事前審査に合格していると売主も安心して物件を止めることができますので、積極的に事前審査は受けておきましょう。
住宅ローンの事前審査は
- 身分証明書
- 収入を証明する資料(源泉徴収票等)
- 物件資料(販売図面等)
などが揃っていれば気軽に受けることが可能です。
但し、事前審査に落ちてしまうと他の銀行に再度審査を申し込む必要などが出てきますので、事前審査を受ける前には「カードローン等を完済しておく」などの配慮が必要となります。
★当ブログ管理人執筆の電子書籍(kindle)のご紹介!是非ご一読ください!★
 |  |  | 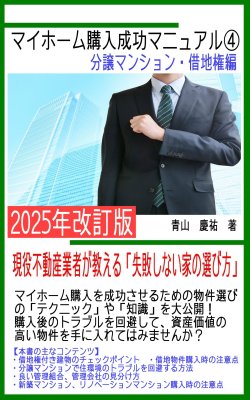 |
不動産売買契約の締結
買付証明書が売主に届き、価格・条件等で合意がなされれば、後日、日程を調整して売買契約を締結することになります。
そして、売買契約時の買主の持ち物は
- 認印
- 手付金/現金または振込
- 仲介手数料/仲介業者と契約時に支払いの約定がある場合
- 写真付きの身分証明書
- 売買契約書へ貼付する印紙
以上のものとなります。
売買契約は仲介業者の事務所にて行われるのが通常であり、買主は「重要事項説明」を受けるために、売主よりも一時間程度早い時間に呼び出されることになるでしょう。
ちなみに重要事項説明とは、宅地建物取引業法35条に定められたルールであり、売主が不動産業者である場合や取引に仲介業者が介在する際に『契約締結前に物件に関する重要な事項について説明を受ける』というイベントとなります。
そして、この説明の内容に買主が納得できるのであれば、売主同席の下で「契約書の読み合わせ」を行い、「売買契約書への署名捺印」を済ませて「手付金の受け渡し」という手順で契約は進むことになるでしょう。
なお、重要事項説明では購入の意思を左右されるくらいのビッグな告知(この段階まで知らなかった物件の問題点に関する告知など)を受けることもありますので、少なくとも契約の前日までには重要事項説明のフォーマットを手に入れ、その内容を確認しておくと共に、
どうしても承服できない内容が含まれている場合には、勇気を出して契約をキャンセルすることも必要でしょう。
また、契約においては契約書や重要事項説明書以外にも、
- 物件状況報告書/売主が建物の欠陥(雨漏り等)や、過去の災害履歴などの物件状況を告知する書面
- 付帯設備表/売主が住宅設備(給湯器、床暖房、給水設備など)に関して不具合の有無を告知する書面
- 媒介契約書/仲介業者へ媒介の依頼を行う契約書
- 仲介手数料支払い承諾書/仲介業者へ仲介手数料の支払いを確約する承諾書
以上の書面を取り交わすことになります。
こうして全ての書面とやり取りが完了したら手付金を売主へ支払って、領収証を受け取ることで売買契約は終了します。
なお、売買契約については別記事「不動産売買契約の注意点や流れを解説いたします!」にて詳細な解説を行っておりますので、是非こちらもご一読ください。
住宅ローンの申込み(融資利用の場合)
売買契約の締結が完了したら、次のステップは住宅ローンの本申込みとなるでしょう。
契約締結前に行われるローンの事前審査などを既に通過している買主も多いでしょうが、正式な金融機関の審査が行われるのは、あくまでも売買契約締結後となります。
そして当然のことながら、この本審査の段階において『融資を断られる』こともあり得るのです。
こうした「住宅ローンの不承認」というアクシデントに備えて、売買契約書においては『●月●日までに住宅ローンの承認が得られない場合には契約を白紙解約することができる条項(融資特約)』が設けられていますから、違約金などのペナルティーを課せられることは原則ありません。
なお、この住宅ローン解約期日が経過するまでは、売主も解約される可能性が高いため、引渡しの具体的な準備には着手しないのが通常です。
ちなみに住宅ローンの本申込みに当たっての必要書類等は
- 住民票
- 実印
- 印鑑証明書
- 写真付き身分証明書
- 源泉徴収票等の収入証明
- 売買契約書
- 重要事項説明書等の物件資料
以上が一般的なものとなるでしょう。
また仲介業者や売主業者の提携ローンを利用する場合などは、その手続きを各業者が代行してくれるケースが多いでしょうが、それ以外のケースでは買主が自ら本申込みの手続きを行う必要があります。
※不動産業者売主物件で仲介業者を介さない取引では、売主が住宅ローンの手続きをサポートするのが通常です。
住宅ローンの金銭消費貸借契約の締結(融資利用の場合)
住宅ローンの本申込みが完了して、融資の承認が得られたなら、次は金融機関との「金銭消費貸借契約(住宅ローンを借入れるための契約)」に臨むことになります。
仲介業者と銀行に赴き、お金を借りるための契約を締結することとなりますが、この日に借入れができる訳ではなく、引渡し日に向けての事前契約といった内容になるでしょう。
なお、金銭消費貸借契約の持ち物は前項にてご紹介した本申込み時の持ち物とほぼ同様であり、これに加えて
- 金銭消費貸借契約書に貼付する印紙(代)
- 銀行に支払う手数料
- 融資実行を受ける口座の通帳と届出印
などとなります。
表示登記・内覧会の開催(新築戸建ての場合のみ)
さて無事に住宅ローンの借入れ手続きが完了すれば、今度は具体的な引渡し準備が開始されます。
まず必要となって来るのが表示登記と呼ばれるもので、建物を新築した際には「速やかにこの登記を行うこと」が義務付けられています。
登記する内容としては「建物の用途」や「床面積」、「構造」などと共に「建築主の名前」を届け出るものとなりますが、新築物件の場合には「購入者の名義で登記を行う」ために、買い手が決まるまで表示登記の申請を保留してあるのが通常です。(本来は建物を建築した建売屋さんの名義で登記をするべきなのですが、敢えて建築主の名義を「購入者」とするのは建売屋さんのサービスと解釈してください)
なお表示登記以外にも、物件の現地説明や境界標の明示、そして建物内部の傷やサッシの建て付け等を確認する「内覧会」なども売主・買主立合いで行われます。
ちなみに内覧会の際に発見した傷は、引渡しまでに売主が補修してくれますので、「可能な限り細かくチェックする」ようにしたいところです。
※表示登記の必要書類は「認印を押した表示登記委任状」「住民票」などとなります。
中古物件のリフォーム見積もりについて
購入するのが中古物件であり、居住開始前にリフォームが必要とあるという場合には引渡し前にリフォーム費用の見積もりを取っておかねばなりません。
なお、『リフォーム費用は住宅ローンで賄う』というケースでは売買契約締結前に見積もりを取得しておき、「ローン特約の融資申込額にリフォーム費用を加えておく必要があります」のでこの点にはご注意ください。
一方、『引渡し前にリフォーム費用の見積もりを取る』という場合でも、物件に売主が居住中のケースでは十分な気遣いが必要となります。
よって、なるべく早い時期に見積もりを取りに行く日程を伝え、可能であれば一日で全ての見積もりを作成できるように工事業者と事前の打ち合わせを徹底しておくべきです。
決済・引渡し
そして最後に行われるのが、不動産売買の総仕上げとも言える「決済」というイベントとなります。
決済においては、売買代金の残金(手付金を差し引いた残額)の支払いと、土地・建物の所有権移転(名義変更)を同時に行うこととなり、これにて引渡しが完了することになるです。
なお決済が行われる場所に関しては、買主が住宅ローンを利用する場合は融資を行う銀行の応接室などが使用され、当日中に確実に所有権移転登記を行うため、平日の午前中に行われるのが一般的でしょう。
そして決済の場には、売主・買主、仲介業者に加えて登記を代行する司法書士が同席し、まずは司法書士が所有権移転に必要な書類を確認することになります。
ちなみにこの際には買主が持参すべき持ち物は
- 住民票
- 実印/ローン利用の場合のみ
- 印鑑証明/発行より3ヶ月以内のもの
- 銀行届出印
- 残代金、固定資産税等の精算金
- 写真付きの身分証明書
- 仲介手数料/契約時に支払っていない場合
- 登記費用/現金にて所有権移転登記費用
以上となります。
こうして書類が揃っていることが確認できたなら、売主・買主共に登記に必要な委任状を司法書士に預けた上で、買主は売主に対して残代金を支払うことになります。(住宅ローンはここで初めて実行されて、一旦買主の口座に振り込まれた後、売主の口座へと入金されます)
ちなみにこの際、固定資産税等の精算に加え、「建物の鍵」などの受け渡しも行われ、取引は完了となります。(決済に関しては別記事「不動産決済日の流れについて」にて、より詳細な解説を行っています)
※新築物件の場合には建物や設備の保証書、建築確認申請副本、瑕疵保険付保証明書などの書類も引き渡されます。
スポンサーリンク
不動産購入の流れまとめ
さてここまで、マイホームの購入の流れを解説してまいりました。
本記事で取り上げた、契約や決済などの「売買上のイベント」に関しては、詳細に説明しきれなかった部分もあるかとは思いますが、今回は購入までの流れをご理解いただくために、あくまでも解りやすさ重視で解説を行っております。
なお、各イベントの詳細については、本文中に『詳細な説明を行っている記事へのリンク』を設置してありますので、是非そちらもご一読ください。
また、管理人が執筆した下記のアマゾン・Kindle本(電子書籍)では、失敗しないマイホーム購入のテクニックを公開しておりますので、ご興味をお持ちの方は是非こちらもご購読いただければ幸いです。

ではこれにて、不動産購入の流れに関する知恵袋を閉めさせていただきたいと思います!