「マイホームとして一戸建てを購入しよう!」と決心した際、避けて通れないのが「建売住宅の購入」という選択肢です。
ただ、建売住宅の購入に際しては「欠陥住宅の心配はないのか」、「分譲会社は信頼できるか」などといった不安が頭を過るものですよね。
そこで本日は「建売の後悔しない選び方を解説!」と題して、物件選びのポイントや注意点についてお話ししてみたいと思います。

建売購入の失敗事例をご紹介
ではまず最初に、現役の不動産業者である管理人がこれまでお客様からお聞きしてきた建売購入の失敗事例についてお話ししてまいりましょう。
建売購入失敗事例⓵ 物件の立地と周辺環境
物件の購入で「失敗をした!」という方々のお話の中で非常に多く耳にするのが、物件の立地や周辺環境に関する問題となります。
立地に関しては
- 思っていたより駅までの道のり遠かった
- 覚悟していた以上にバス通勤が苦痛である
- 最寄りのスーパーが引越し直後に閉店し、買い物に苦労している
といった理由で後悔をされているようです。
一方、周辺環境につきましては
- 道路や鉄道の音や振動が想定以上に激しい
- 近隣の飲食店が原因と思われる虫害に悩まされている
- 新興宗教の施設が近隣にあり、不安を感じている
- 深夜、隣の公園に若者がたむろして煩い
- 想定以上に日当たりが悪いのが不満だ
以上のような失敗談を耳にしたことがあります。
建売購入失敗事例⓶ 間取りと設備の問題
続きましては、間取りと設備に関しての失敗事例のご紹介です。
間取りについては
- リビングにトイレの入り口があり、音が気になる
- 窓の位置が悪く、隣家から丸見え
- 収納スペースが小さ過ぎる
等のご意見をよく耳にいたします。
また、設備に関しては
- 床暖房が暖かくない上、メンテナンスが面倒
- 換気扇から虫が入ってくる
- キッチンの高さが低過ぎて、腰が痛い
といった後悔をされている方が多いようです。
建売購入失敗事例⓷建物の品質と不具合
そして最後にご紹介するのが建物の品質と不具合についてとなりますが、こちらはより深刻なお悩みが多いようです。
- 収納内の結露が激しくカビが生える
- 外壁に細かいひび割れが無数に出来た
- 激しい家鳴りに悩まされている
- 引渡し後、半年で雨漏りした
- 地盤が沈下しているようだ
- 下水が逆流してくる
等々、こちらに関しては枚挙に暇がありません。
このように建売住宅の購入に際しては様々な後悔が付きまとうことになりますから、事前に可能な限りの知識を身に付け、失敗のない物件選びを行う必要があるのです。
建売選びのポイントや注意点
ここまでの解説にて、建売を購入した方々がどのような点で後悔しているかがお解りいただけたことと思いますので、本項では具体的な物件選びのポイントや注意点をお話しして行くことにしましょう。
建売の立地と周辺環境について
ではまず最初に、建売を選ぶ際の立地と周辺環境のチェックポイントを見ていきましょう。
マイホームを探していて気になる物件が見つかったなら、まずは
駅やバス停、最寄りのコンビニやスーパー、そして通うことになりそうな病院や学校などへ、実際に足を運んでみる
ことが重要です。
近年では「ストリートビューで経路だけを確かめて終了」という方も多いようですが、実際に行ってみることで道幅やアップダウン、通行量に行き交う人々の雰囲気などを感じ取ることができますから、これは是非実践してください。
※通勤等に際して、駅までバスでの移動が必須ならば実際にバスに乗ってみることも重要です。
さて続いては周辺環境のチェックとなりますが、
ここでは日当たりの良さや嫌悪施設と呼ばれる住環境に影響を与える施設の存在、そして困った隣人が住んでいないかといった点を確認する
ことになります。
日照については朝・昼・夕方で状況がかなり変わってきますし、夏と冬でも日の入り方が異なりますので、想像力をフルに発揮しながら「どのくらい太陽の恩恵を受けられる物件であるか」を確かめることが重要です。
なお、騒音・振動を発生される幹線道路や鉄道、そしてお墓やパチンコ店などの嫌悪施設に関しては一度物件を訪れるだけでも発見することができるでしょうが、「土日は操業を停止している町工場」や「夜間のみ開店するカラオケパブ」などは見落とすことが多いですから、周辺環境の確認や立地の下見は『曜日や時間帯を変えて、複数回行うべき』でしょう。
また学校や神社などは、むしろ「プラスの印象となる施設」であるように感じますが、登下校時に大騒ぎをする学生や、お祭りに初詣などで近隣住人が迷惑を被る可能性もありますので、この点には注意が必要となります。
ちなみに、近所への嫌がらせを繰り返す厄介な住人や、ゴミ屋敷等の存在を知らずに物件を購入してしまうと、後々非常に面倒なことになりますから、契約の意思を固めたなら、近隣住人への聞き込みなどの調査も行っておくのがおすすめです。
※嫌悪施設等に関する詳細は別記事「不動産の嫌悪施設についてお話してみます!」をご参照ください。
建売の間取りと設備の問題
続いては間取りと設備について確認していくことになりますが、間取りについては物件が完成しているか否かによって大きくチェック方法が変わってきます。
物件が既に完成済みであれば、家族で物件に出向いて生活のシュミレーションを行ってみるのがベストです。
ただ、漠然とシュミレーションを行なうと言って、何をして良いかわからないでしょうから、
- 出勤前にいつも行っている一連の行動
- 洗濯機を回してから洗濯物を干すまでの動き
- 夕食の準備と片付け
など、検証するテーマを定めて、動線や間取りの使い勝手などを確認していきましょう。
また物件が未完成の場合には、間取り図を入手して自宅でそれを再現しながらシュミレーションを行う方法がおすすめです。
例えば、マスキングテープなどを床に貼ってお部屋や収納の大きさを再現したり、「今の家にあるキッチンや風呂場がどれくらい大きくなるか」といった具合に比較を行っていけば、未完成物件でもある程度のイメージを掴めるはずです。
一方、設備については下調べを万全にすることが何よりも重要となります。
身近に対象の設備を導入済みの方がいれば、使い勝手についてお話を聞くのも良いでしょうし、システムキッチンやユニットバスであれば建材メーカーのショールームに出向いて実物を確認してみると安心です。
建売物件の面積や地形
物件選びをする上で、注意しなければならないのが「建物が建つ土地」についての問題です。
マイホームを決めるとなると、ついつい間取りや駅までの距離などを最優先に考えてしまいがちなものですが、
物件の基盤となる土地についてもしっかりと吟味する必要
があります。
そこでまず注目するべきは、土地の「形状」と「面積」に関する問題となるでしょう。
建売物件の中には、やたらと長細い形状をしていたり、三角形や非常に歪な形をした土地も見受けられますが、あまりに不整形な土地は資産価値に大きな影響を及ぼす可能性があります。
なお詳しくは別記事「土地の形状について解説いたします!」にて解説していますが、少なくとも5m以上(専用通路の場合は2.3m以上、可能であれば2.5m以上)の間口が確保できており、なるべく形の整った物件を選ぶべきでしょう。
また土地の面積については50㎡以上を確保することが重要です。
近年では価格勝負の40㎡台の土地面積しかない建売物件も少なくありませんが、売却に際しては非常に人気が低い上、建て替えとなっても従前の建物と同じような間取りしか入らないなどの問題が生じるため、あまりお勧めはできません。
※土地の面積については別記事「マイホームの土地の広さや面積について解説いたします!」にて詳しく解説しておりますので、こちらも是非ご覧になってください。
★当ブログ管理人執筆の電子書籍(kindle)のご紹介!是非ご一読ください!★
 |  |  | 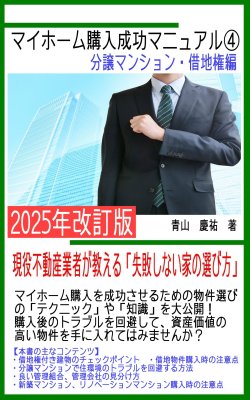 |
建売物件の権利関係の問題
続いて注意すべきなのが近隣との権利関係の問題です。
近年では建売を商品化する段階で、分譲業者が「近隣との権利関係を調整してから物件を引き渡す」のが当たり前になって来てはいますが、まだまだ不完全な物件を引き渡す業者が存在するのも確かです。
例えば隣りのお宅との境界線上に建てられているブロック塀が共有物であるにも係らず、今後の処理についての取り決めが行われていないといったケースや、
お隣の屋根の敷地越境について「越境しています」という簡単な説明のみで引渡しが行われるのは非常に危険な取引となります。
ブロック塀を例に挙げれば、将来的に劣化が進んだ際には「誰がどれだけ費用の負担を行って改修や撤去を行うのか」という問題が生じたり、「地震で倒壊して怪我人が出た際に、誰が責任を負うか」について揉め事となる可能性も出て来るでしょうし、
物件を売却しようと考えた際にも処理方法の定まっていない共有物の存在はマイナス評価となることは間違いありません。
更には越境物についても、下水配管や水道管などの場合には配管トラブルが生じた際に「自分の土地(他人の土地)を掘り返さなければならない」という事態も考えられますから、これは非常に厄介です。
よって、本来であれば「後々トラブルに発展する可能性のある権利関係の問題が存在する場合にはこれを解決(共有物なら撤去してしまう、越境物ならそれを解消する等)した上で引き渡してもらう」のがベストなのですが、
それが叶わない場合でも、少なくとも
『今後の処理についての取り決め(覚書等の取り交わし)くらいは済ませてある物件』を選ぶべき
でしょう。
ちなみに、明らかに権利関係の問題が存在するにも係わらず「何の取り決めも行っていないケース」では、隣家の人間が話し合いに応じてくれない「やばい人」である可能性も濃厚ですから、くれぐれも慎重に判断を下す必要があります。
※越境問題の詳細については別記事「不動産・境界越境問題について解説いたします!」にて、地中埋設物に関しては「地中埋設物の契約不適合責任(瑕疵)について考えてみます!」の記事にて詳しく解説しておりますので、ご心配な方は是非参考になさってください。
建売物件の分譲主の質を見極める
土地の問題についてのチェックが完了したら、続いては分譲業者(建売屋さん)を精査して行きましょう。
物件を購入する前に、分譲主の口コミなどをネットで検索するのは当たり前かと思いますが、更に慎重を期すならば
分譲主が会社を構える地域の自治体に出向いて情報を集める方法
がお勧めです。
不動産業者は各都道府県から免許を取得して営業を行っていますから、「これまで取引上で起こした事故の記録」や「免許更新時に申告した決算内容」といった情報が行政機関に保存されており、希望者には閲覧も許されています。(国土交通省免許の場合は国交省が窓口となります)
そして、こうした情報を確認しておけば売主となる建売屋さんの「業者としての質」や「財務状態」まで確認することができますから、これは非常に安心感を得られるはずです。
※質の高い不動産会社を選ぶコツについては、過去記事「悪徳不動産会社の見分け方について解説いたします!」にて詳しく解説しております。
建売物件の施工メーカーと工法
さて、分譲主となる不動産会社を調べたならば、建物の建設を請け負ったハウスメーカーについても調査をしておきましょう。
もちろん、誰が聞いても知っているような大手建築会社なら話は別ですが、建売の場合はあまり名前を聞いたことのない工務店が仕事を請け負っているケースも少なくありません。
なお建物に欠陥が見付かった場合、その責任を負うのはあくまで分譲業者となりますが、評判や経営状態の悪い施工会社が建てた物件は不具合も多いものですから、やはりハウスメーカーのチェックも欠かすことはできないでしょう。
ちなみに不動産業者と同じく、
建設業者も国土交通省か各都道府県の免許を受けて営業をしていますので、分譲主を調べるのと同様の方法で行政処分の内容等の確認が可能
となります。
一方、建物の工法に関しては、殆どの物件が「在来工法」か「2×4工法」のどちからかで建てられていることでしょう。
どちらの工法もそれなりのメリット・デメリットはあるものですが、物件価格が極端に安い場合には2×4工法を選んでおくのが得策であるかと思います。
実は2×4工法は、間取りやデザイン性の自由が利かない代わりに「腕の悪い職人が施行しても欠陥が発生し辛い」のが特徴ですから、建築費を切り詰めている可能性が高い物件ではこちらを選ぶ方が安心なはずです。
※在来工法と2×4工法の違いに関する詳細は「在来工法と2×4工法について解説いたします!」の記事をご参照ください。
建売住宅の保証(アフターサービス)とインスペクション
建売住宅の購入に当たっては「建物等についてどのような保証をしてくれるのか」という点が気になるところですが、新築物件の売主は雨漏りなどについて
10年間瑕疵担保(契約不適合)責任を負う
ことが法令で義務付けられています。
また、これに加え瑕疵保険への加入も義務付けられることとなりましたので、万が一分譲業者が倒産したとしても、建売購入者は10年に渡って建物の重大な欠陥について保険金の受け取りが可能です。
但し、配管の水漏れなど建物の構造に係らない不具合については2年程度の保証が一般的ですし、こうした不具合に関しては保険対象外という契約を結んでいる建物もありますから、購入に当たってはアフターサービスや保険の内容を詳細にチェックしておきましょう。
なお、近年では地盤沈下に対する保険への加入を行なっている物件も多いですから、この点についても合わせて確認をしておくべきです。
一方、中古住宅にて行われるインスペクション(住宅検査)を新築住宅で行うケースも増えつつあります。
当然、費用は買主負担となりますが、専門の検査員が第三者の目線で建物をチェックしてくれますので、施工不良が心配という方にとってはおすすめの方法です。
*インスペクションについての詳細は別記事「インスペクションと瑕疵保険について解説いたします!」をご参照ください。
建売を取り巻く状況
ここまで建売の購入の必勝法についてお話ししてきましたが、古来より「彼を知り己を知れば百戦殆うからず」などという言葉もある通り、成功を収めるためには情報収集が何よりも大切な作業となります。
そこで本項では、現在の「建売分譲の市場動向」や「これを取り巻く状況」などについてお話ししてみましょう。
一般の方が土地を購入できない
現在、不動産業界においては「一般の方が土地を購入できない時代である」と言われています。
皆様もご存じの通り、建売事業とは不動産業者が土地を買い取り、新築戸建てを建築して転売するビジネスを指す言葉です。
よって建売に加工する物件はそれなりの安価で仕入れを行う必要があり、「対象になる物件は非常に限られて来る」というのがこれまでの常識でした。
しかしながら、近年の建売業者(業界では「建売屋さん」と呼ばれています)は、
海外に木材供給用の現地法人を設けたり、ハウスメーカーを買収して自社施工を可能にするなどの方法により、建築コストを極限まで圧縮することに成功
しています。
そして、こうした手法で力を蓄えた建売屋さんの中から「パワービルダー」と呼ばれる大手業者が台頭することとなり、年間数百棟にも及ぶ建売住宅を供給し始めたのです。
そして、このような状況が続けば「パワービルダー同士での建売用地の争奪戦が激化する」のは当然の結果でしょうし、全国各地には数千社にも及ぶ中小規模の建売屋さんが存在していますから、不動産市場はまるで戦国時代のような『建売用地の確保合戦』が展開されることとなって行きした。
その結果、土地の価格は高騰を繰り返し『建売に向かない形の悪い土地』や『売主の希望で価格が高過ぎる土地』を除いては「一般の方が土地を買えない時代」になってしまったという訳です。
※建売屋さんについての詳細は、別記事「建売とは?戸建て分譲の仕組みや舞台裏を解説いたします!」をご参照ください。
向上する建売の品質と安全性
前項の解説にて「戸建てを手に入れよう」とすれば、建売物件を買う以外に選択肢が少ないことはご理解いただけたことと思いますが、ここで気になるのが『物件の品質について』となるでしょう。
先の説明にて「建築費を極限まで抑えている」などという表現を致しましたので、『とんでもない欠陥物件が量産されているのでは?』と不安になった方もおられるはずです。
そこでまず結論から申し上げてしまえば、
建売物件の品質はむしろ向上傾向にある
というのがその答えとなります。
さて、「建築費を抑えているのに建物は良くなっている」というのは、酷く矛盾したお話にも聞こえますが、現実にこうした逆転現象が発生しているのです。
なお、こうした状況となっている最大の要因は「建売物件に対する法整備の充実」に他ならないでしょう。
既にお話しした通り、新築物件は主要な部分について10年間、売主が責任を負い、瑕疵保険へ加入することが義務付けられていますので、現代は『建売というビジネスが誕生して以来、最も買い手のリスクが少ない時代』と言えるのです。
また、前項でお話した建売屋さん同士の物件獲得競争も、結果的にはライバル会社よりも「より良い建物を建てなければならない」という競争意識に通ずることとなり、設備や仕様の充実度も驚くべきレベルに達しています。
但し、こうした状況でも「質の低い建売屋さん」はどうしても存在するものですから、やはり買い手も『しっかりと物件を選ぶ目』を持つべきでしょう。
スポンサーリンク
建売の後悔しない選び方まとめ
さてここまで、後悔しない建売物件購入のポイントを解説してまいりました。
そして、記事の中でご紹介して来た注意事項を踏まえた上で物件を選んでいただければ、後々「失敗した!」などという悲しい想いをせずに済むはずです。
なお、「避けるべき物件はわかったが、どんな物件が望ましいかについては説明してくれないの?」というお声も聞こえて来そうですので、本項では『まとめ』としてこのポイントを解説してみたいと思います。
これまで管理人は多くの方々に建売物件を供給してまいりましたが、「住宅選びに成功した!」と心から喜んで下さるお客様に共通しているのは『資産価値の高い物件を選んでおられる』という点です。
「建売の資産価値」と言われてもピンッと来ない方も多いかもしれませんが、不動産は同じ値付けが行われていても、「実際はその価値に大きな差が存在する」ことも少なくありません。
例えば30坪(100㎡)という同じ大きさの土地を購入しても、8m×12.5mという形の良い土地を購入するのと、5m×20mという不整形な土地を買うのでは、その資産価値に大きな差が生じてしまいます。
また同じような立地で、同じ面積、価格も近い物件同士でも一方の容積率が150%、もう一方は300%といったケースにおいては、明らかに後者の資産価値が高いことになるでしょう。
ちなみに、このようなお話をすると『土地を売って儲けるつもりはないんだけど・・・』などとて思われるかもしれませんが、たとえ売る気がなくても「価値ある物件を選ぶことは非常に大切」です。
将来的にどうしても資金が必要となり、「自宅を担保に入れてローンを組まなければならない」という事態が『絶対に起きない』とは誰も断言できないはずですし、万が一「家の買い換え」をしなければならい状況になれば、売却する物件の評価額は非常に大きな意味を持ってくることになるでしょう。
更には、容積率や建ぺい率の高い土地であれば、建替えの際に3階、4階と建物を上に伸ばすことで「一部を賃貸物件として貸し出す」といった利用法も可能なはずです。
よって、マイホームの購入を「単なる住宅ローン地獄のスタート」とするか、「人生の基盤(資産)造りの第一歩」とするかは、『選ぶ物件の資産価値次第』ということになりますから、是非この重要な選択を誤ることの無いようにしていただきたいものです。
ではこれにて、「建売の後悔しない選び方を解説!」の記事を締め括らせていただきたいと思います。