不動産取引の現場において、時折目にするのが「念書」や「覚書」と言った書面を取り交わすシーンとなります。
さて、このようなお話をすると「契約書があるのに、どうして別途書面を交わす必要があるのだろう?」といった疑問を持たれる方も多いことと思いますが、実はこの「念書」や「覚書」は不動産の取引において欠かすことのできない便利なアイテムとなっているのです。
そこで本日は「念書と覚書について解説いたします!」と題して、不動産の運用や管理における覚書・念書の活用術についてご説明をしてみようと思います。
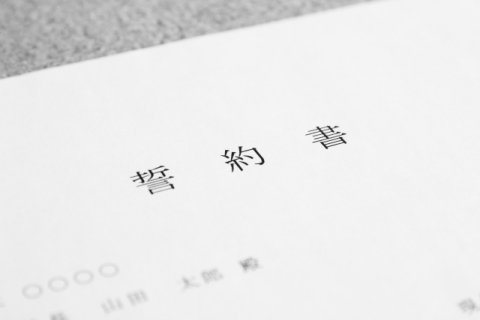
「念書」「覚書」とは
アパート経営を行っている大家さんであれば、入居者等と様々な約束を交わすことがあるものです。
例を挙げるならば、入居時に取り交わした賃貸借契約の内容変更に、退去時の原状回復費用に関して後から特別な取り決めを行う場合など、その枚挙には暇がありません。
また、土地を保有している方であれば、近隣住民と境界線上に設置されたブロック塀の扱いについて新たな協定を結んだり、土地の測量を行った際に建物の越境が発覚し、今後の取り扱いについて約束事をするといったケースもあるはずです。
そして、こうした約束を書面に残しておきたい際に、非常に重宝する書式が「覚書」や「念書」といった文書となります。
念書と覚書はどちらも
約束事の証拠として作成される書面であり、適切な内容が記載されていれば法的にも有効と判断される文書
となります。
なお約束事を記する書面といえば、まず頭に浮かぶのが「契約書」となりますが、念書や覚書は複雑でボリュームのある約束事には不向きな書式となりますから、
- 契約書に関する補助的な事項の取り決め
- 契約内容の変更
- 契約書を作成するまでもない、単純な内容の取り決め
などに際して用いられるのが通常です。
例えば、既にスタートしている契約に変更点が生じた場合には、改めて契約をやり直す訳にも行きませんから、元の契約(原契約などと呼ばれる)の内容はそのまま活かしつつ覚書などで「原契約第●条の内容をAからBに変更する」などといった形式で取り決めを行うことになります。
また一方、「土地の境界線上にあるブロック塀の取り扱い」や「建物の越境についての合意事項」など、わざわざ契約を結ぶ程の内容ではない場合に念書や覚書が単体で作成されることも少なくありません。
ちなみに念書と覚書の最大の違いは、
- 念書/取り決め事の「当事者一方」から指し入れられる書面
- 覚書/両当事者が署名・捺印を行った上、取り交わされる書面
という点です。
そして次の項では、より詳細に念書と覚書の特性について解説してまいります。
念書とは
前項でも申し上げた通り、念書は当事者の一方から指し入れられる形式の文書となります。
そして多くの念書の雛形に「念のため本書を差し入れます」という表現が組み込まれていることからもわかる通り、
「相手方に対して、念書を差し入れる側が一方的に約束をする書式」
となるのです。
なお、こうした特性を持つが故に
- 「約束を取り交わす双方に義務がある内容」には利用し辛い
- 裁判などにおいては、一方的な書面であるために「若干、証拠力が低い」
という弱点があります。
但し、書面の作成が非常に手軽に行える上、指し入れる側も割り合い気軽にサインできるというメリットもあるため、不動産業の実務で利用される頻度は非常に高いものとなるでしょう。
また念書を書くことで、文字通り相手方に「念押し」をして、約束を破り辛くさせる効果も期待できますから、どちらかと言えば「教育的な意味合い」で使用されることも多い書式です。
ちなみに、念書の書式としては
- タイトル/「●●に関する念書」
- 指し入れる相手方の氏名/「■■殿」
- 頭書/「▲▲▲に関して下記のとおり確約し、念のため本書を貴殿に差し入れます」
- 本文/「取り決めるべき内容」の記載
- 日付/「書面作成日時」の記載
- 署名・捺印/「念書を差し入れる者」の署名と捺印
以上の内容で書面が作成されることが多いでしょう。
スポンサーリンク
覚書とは
さてこれに対して覚書は、約束を交わす両当事者が署名捺印を行った上で取り交わすという性質上、原則2通以上を作成する必要があります。(覚書を交わす相手が複数なら、枚数は更に増える)
また、覚書においては「AがBに対して責任を負う」「BがAに●万円支払う」等の自由な取り決めが可能となりますから、
複雑な内容の約束を取り交わす際には、念書より覚書の方が望ましい
と言えるでしょう。
更には当事者が全員署名・捺印を行うことで、訴訟などに発展した場合にも証拠能力が高くなりますから、『これは重要!』という約束事には覚書を利用するのがおすすめです。
ちなみに書類の書き方としては、
- タイトル/「●●に関する覚書」
- 頭書/「▲▲▲(約束の対象、例・共有ブロック塀の取り扱い等)に関して●●(当事者の名前)と■■(当事者の名前)は下記のとおり合意するものとする。また、その証として本書2通を作成し署名押印の上、各々その1通を保有するものとする」
- 本文/「取り決めるべき内容」の記載
- 日付/「書面作成日時」の記載
- 署名・捺印/「当事者全員」の署名と捺印
以上のような構成となるのが一般的でしょう。
なお覚書の約束事項の最後には、「本覚書に記されていない事項については、民法やその他の法令及び、商習慣などに従い、両当事者協議の上で取り決めを行うものとする」といった文言を入れておくのがベターです。
スポンサーリンク
覚書・念書まとめ
さてここまで、不動産の管理等で非常に重宝する念書や覚書の活用方法などについて解説してまいりました。
賃借人や近隣の土地所有者と簡単な約束事を取り交わす際などには、是非念書や覚書をご活用いただければと思います。
なお、既に存在する契約に対して覚書や念書を交わす際は、
既存契約を「原契約」と表現し、「●●(当事者の名前)と■■(当事者の名前)は▲年▲月▲日付け賃貸借契約(以下 原契約)について下記の事項を確認する」
といった文言を文書の冒頭に入れるとスマートでしょう。
また、過去記事「不動産の印紙税について解説いたします!」においてもご説明しておりますが、こうした覚書や念書でも賃料以外の返却されない金銭の授受の決め事が記されている場合には、印紙税の課税対象となる可能性がありますから、この点にも注意が必要です。
更に不動産における約束事は「将来に向けた長いスパンの取り決め」となることも少なくない(建物の越境に対して、建替えの際に越境の解消を約束する場合等)ため、こうした長期に及ぶ念書や覚書を取り交わすケースにおいては、
『なお、本件不動産が相続された場合、あるいは第三者に譲渡された場合についても、本状の取り決めを承継するものとします』
といった条項を加えておくべきでしょう。
不動産に係るトラブルは将来的に「非常に面倒な厄介事」へと発展するケースも少なくありませんので、相手方と上手に約束を交わしてスムーズな運用を心掛けて行きたいものですよね。
ではこれにて、「念書と覚書について解説いたします!」の知恵袋を閉じさせていただきたいと思います。