どのような買い物をするのにしても、本体価格以外に様々な諸費用が掛かってくるのは世の常ですよね。
そしてその対象が、マイホーム等の不動産となれば諸費用のボリュームも自ずと大きくなるはずですから、これから物件を購入しようとお考えの方にとっては非常に気になる問題のはずです。
そこで本日は、「不動産売買の諸費用計算について解説いたします!」と題して、購入や売却の前に是非知っておきたい諸経費についてお話しさせていただきます。

物件の売買に掛かる費用
不動産の営業マンをしていると、お客様から「マイホームの購入や売却にはどれくらいの諸経費が掛かるの?」という質問を頂くことがよくあります。
そして、マイホームの購入であれば
- 新築物件の場合/物件価格の3~6%
- 中古物件の場合/物件価格の6~10%
といった目安はあるものの、これでは少々『ザックリ過ぎる』という印象ですよね。
そこでまずは、必要になってくる諸費用の項目を挙げながら、ご説明を加えて行くことにいたしましょう。
仲介手数料(購入・売却共に必要)
不動産売買に際して仲介業者が取引に介入した際に発生するのが仲介手数料となり、売主・買主共に必要となってくる費用となります。
なお、一般の方が自力で購入者を探すことは困難でしょうから、「原則として必要になる経費」と言えるでしょう。
仲介手数料の金額計算は物件の価格よって変わってきますが、下記の計算式に当てはめれば自力での計算も可能です。
- 売買価格200万円以下 ・・・売買価格×5%+消費税
- 売買価格200万円超~400万円以下・・・売買価格×4%+2万円+消費税
- 売買価格400万円超 ・・・売買価格×3%+6万円+消費税
ちなみにこの計算式は仲介手数料の上限額の求め方となりますが、特段の理由がない限りは「上限額の請求を受けるもの」とお考えください。
但し、仲介業者の中には「売主や買主の自己発見については仲介手数料が半額」等のサービスを行っている会社もあります。
契約書印紙代(購入・売却共に必要)
不動産の売買契約書には当然ながら「売買価格」が記されていますが、金銭の授受を証する書類には印紙を貼るのがルール(印紙税を収めるのが義務)です。
そして不動産売買については、以下のような税制が売買価格に応じて定められていますので、売買価格に応じた印紙を契約書に貼付することになります。(令和5年現在の軽減措置適用時)
- 500万円超~1000万円以下 ・・・5000円
- 1000万円超~5000万円以下・・・1万円
- 5000万円超~1億円以下 ・・・3万円
なお、印紙税に関する詳細は別記事「不動産の印紙税について解説いたします!」をご参照ください。
ローン諸費用(購入の場合のみ)
そしてマイホーム購入に際して住宅ローンを利用するとなれば、様々な諸費用が必要となってきます。
銀行へ支払う事務手数料に火災保険料、保証料などが主なものとなるでしょう。
これらの費用は「住宅ローンをいくら借り入れるか」によって必要な金額も変わって来ますが、本項では3000万円は30年返済で借り入れた場合の試算をしてみます。
- 銀行手数料3.5万円
- 火災保険(契約内容によりますが)25万円
- 保証料(30年借入)60万円
※この他にも団体信用生命保険(返済義務者が死亡した際に支払われる保険であり、この保険金によってローンの完済が可能となる)の保険料が必要ですが、通常こちらは月々の返済額に上乗せする形で支払われますので、本項では計算に加えません。
※保証料についても月々の返済に上乗せすることが可能ですが、本記事では一括払いを前提に解説を行います。
登記費用(購入・売却共に必要)
登記とは『国家が個人や法人の権利を証明する制度』であり、物件の売買に際しては「権利の移動」等を確実なものとするために登記が行われ、それに伴って費用も発生します。
登記費用の中には、登記に要する税金(登録免許税)に加え、登記手続きを行う司法書士や土地家屋調査士の報酬なども含まれます。(登録免許税の詳細は「不動産の登録免許税について解説いたします!」の記事をご参照ください)
なお、不動産売買に伴って行われる主な登記は以下の通りとなります。
- 所有権移転登記費用(購入時のみ)・・・土地、建物の固定資産税評価額の2%(マイホーム購入の場合は軽減税率0.15%が適用される)
- 新築建物の表示登記(購入時)・・・新築建物を購入する際に必要となる登記であり原則無税ですが、担当する土地家屋調査士に10万円程度の報酬を支払う必要があります。
- 新築建物の所有権保存登記(購入時)・・・・・・建物の固定資産税評価額の0.4%(マイホーム購入の場合は軽減税率0.1%が適用される)
- 抵当権設定登記費用(購入時)・・・抵当権設定価格の0.4%(マイホーム購入の場合は軽減税率0.1%が適用される)
- 抵当権抹消登記費用(売却時)・・・抵当権が設定されている場合のみ必要となる登記であり、登録免許税は1物件につき2000円となります。(土地・建物の2物件なら4000円)
- 司法書士報酬10万円・・・土地家屋調査士が担当する「表示登記」以外の登記を行う場合には、別途こちらの司法書士報酬が発生します。
※所有権移転登記費用は原則買主の負担となります。
※新築建物を売買する場合には、通常建物の所有権移転登記は行われず、後述する表示登記と所有権保存登記をすることになります。
固定資産税や都市計画税の精算金(購入に必要)
固定資産税や都市計画税は、その年の1月1日現在で土地や建物を保有している所有者に対して課せられる税金であり、地方税に分類されます。
そして、1月1日現在の所有者が課税されるというこの税金の性質上、たとえ年の途中で売買が行われても売主が一年分の税金を全額負担する(売主に請求が行ってしまう)ことになってしまうのです。
そこで不動産取引においては固定資産税等を日割計算して、決済時に買主が売主へ精算金を支払うのが原則となります。
ちなみに、固定資産税等の精算金の起算日は地域の商慣習によって異なり、関東では1月1日とするケースが多いのに対して、関西では6月1日となるのが一般的であるとのことです。
※固定資産税等についての詳細は別記事「固定資産税の計算方法や課税の仕組みについて解説いたします!」をご参照ください。
不動産取得税(購入時に必要)
不動産の購入に際しては、買主に不動産取得税という地方税が課税されることになります。
なお税額の計算は原則として固定資産税評価額に標準税率4%を掛けて計算されますが、地方税であるが故に自治体毎に独自のルールが存在していますが、
土地の場合で固定資産税評価額の1/2に対して3%、建物については住居で評価額の3%、それ以外の建物で評価額の4%が課税されるという方式を採用している自治体が多いようです。
※不動産取得税に関する詳細は別記事「不動産取得税とは?という疑問にお答えします!」をご参照ください。
引っ越し費用等(購入・売却共に必要)
マイホームを購入するにせよ、売却するにせよ、住み替えを行う以上は引っ越し代は必ず発生してくる費用となります。
なお、費用の相場についてはプランや業者にもよりますが、20万円~30万円くらいが一般的でしょう。
ちなみに、マイホームの買い替えにおいて売却を先行した場合には、「新居の引き渡し時期の問題」で一時的に仮住まいをしなければならないケースもあるでしょう。
こうしたケースでは短期で賃貸物件を借りることになりますので、前家賃に敷金・礼金、仲介手数料などかなりの出費を覚悟する必要があります。
建物の消費税(購入時のみ必要)
土地は消費税の課税対象ではありませんので、一戸建てやマンションの場合でも土地については消費税を支払う必要はありません。
一方、建物についても売主が個人であれば消費税は課税されませんが、不動産業者が売主の場合には中古・新築を問わず消費税の課税対象となる点には注意が必要です。
なお、消費税額については売買契約書に必ず記載されることになります。
水道加入金(購入時のみ必要/地域による)
新築戸建てや土地を購入した際に発生する可能性があるのが、「水道加入金」などと呼ばれる費用です。
水道メーターの設置などに際して、水道局へ支払う納付金等を指す言葉となりますが、地域によって呼び名も微妙に異なる場合がありますし、自治体によっては「そもそも無料」というケースもあります。
また、新築戸建てにおいては売買価格に含まれているというパターンも増えつつあるようです。
中古物件ならではの費用
ここまで様々な不動産に係わる諸費用を見てまいりましたが、「中古物件の売買ならではの費用」となるのが以下のものです。
- インスペクション(建物状況調査)費用/売却時のみ必要
- 瑕疵保険料/売却時のみ必要
- リフォーム、リノベーション費用/購入時のみ必要
中古物件売買における最大のリスクは、何と言っても「建物の欠陥(について売主が負う契約不適合責任)」となります。
せっかく新居を購入したにも係わらず、雨漏りやシロアリの被害が明らかになれば、取引上のトラブルとなるのは不可避ですよね。
そこで近年では、中古物件の売買に際して第三者機関におけるインスペクション(建物状況調査)を実施して、プロの目線で物件の不具合や欠陥の確認作業を行うのが常識となりつつあります。
なお、インスペクションの調査費用については売主が負担するのが通常ですが、どうしても調査を拒む売主も存在するため、買主が自費でこれを行う場合も稀にあります。
また、インスペクションの実施に加えて、建物の欠陥が明らかになった際に保険金の給付を受けることができる「瑕疵保険」に売主が加入するケースも少なくありません。
ちなみにインスペクションの費用が数万円程度、瑕疵保険の保険料は10万円弱というのが一般的ですから、2つを合わせても20万円程度の出費となるでしょう。
※インスペクションについては別記事「インスペクションと瑕疵保険について解説いたします!」をご参照ください。
一方、中古物件を購入する買主は建物のリフォーム費用やリノベーション費用について十分な検討が必要になります。
工事の内容については物件の状態、買主のこだわりなどによって千差万別でしょうが、工事費用は非常に高額になる可能性が高いので綿密な資金計画が必要となるはずです。
ちなみに購入対象が中古物件の場合には、リフォーム費用も必要となります。
仮に、床面積が100㎡(30坪)くらいの戸建てにおいてクロス全面張り替えとルームクリーニングを行うと、通常50万円程度が必要となるでしょう。
これにシステムキッチン入替え、ユニットバス交換を入れれば、更に250万円程度は必要になる点も注意したいところです。
分譲マンションならではの費用
分譲マンションの売買においては固定資産税等の精算金に加えて、月々支払うこととなる
- 管理費の精算金/購入時のみ必要
- 修繕積立金の精算金/購入時のみ必要
- 専用使用料の精算金/購入時のみ必要
が必要です。
さて、このようにお話しすると「分譲マンションだから当たり前だよね」と思われるでしょうが、ここにも注意すべき点は存在します。
まず問題となるのが、所有者が管理費・修繕費等を自動引き落としにしている場合であり、決済日よりかなり早めに「引き落とし停止の手続き」をしなければ、管理費等の二重払いが発生する可能性があるでしょう。
また、マンション管理会社によっては2ヶ月分、3ヶ月分の管理費等をまとめて引き落としている場合もありますから、こうしたケースでは更に厄介なことになります。
ちなみに、このようなトラブルを回避するためには、売買前にマンション管理会社の引き落としシステムの詳細を充分に確認しておくことが重要ですし、
契約上の都合(買主の住宅ローンの承認がなかなか下りない場合など)で早めの手続きが行えない場合には、決済時に2ヶ月分、3ヶ月分の管理費等をまとめて精算しておくのがベターでしょう。
なお管理費等の他にも、ルーフバルコニーやアルコープの専用使用料などを精算しなければならい物件もありますので注意が必要です。
そして、最も厄介なのが売主が管理費や修繕積立金等を滞納しているケースとなります。
通常は売買代金などで滞納分を精算する方法が執られますが、遅延損害金などが定められている場合もありますから、こちらも管理会社と入念な事前打ち合わせをしておくべきでしょう。
収益物件ならではの費用
不動産投資における収益物件においては、
- 賃料、管理費の精算金/売却時のみ必要
- 敷金、保証金の精算金/売却時のみ必要
が必要となります。
ちなみに、分譲マンションで賃貸中の物件(オーナーチェンジ物件)を売買するとなれば、更にここに管理費・修繕費の精算が追加されますから、最も精算金の種類が多い取引となるはずです。
なお、賃料については引渡し日で日割り精算をすることとなりますが、問題となるのが滞納者がいる場合の処理です。
可能であるならば、引渡し日までに滞納者からの徴収を済ませたいところですが、不可能な場合には買主と相談の上、処理方法を決定することとなります。
また、敷金についてはあくまでも入居者からオーナーが預かっている金員となりますから、売買の際には「売主から買主にそのままスライドされる金銭」となります。
しかしながら、実際に売主から買主への敷金受け渡しが行われることは稀であり、売買代金から敷金分を差し引いて(相殺して)決済を行うのが通常です。
スポンサーリンク
諸費用計算のケーススタディー
前項では、不動産売買に必要な諸経費の概略についてお話ししましたが、本項ではより理解を深めていただくために、具体的な物件の例を挙げて諸費用の計算を見ていきしましょう。
新築建売住宅購入時の諸費用計算
では、まず最初に新築建売住宅購入時の諸費用計算をシュミレーションしてみます。
なお、諸費用計算の対象となる物件は
- 売買価格5000万円
- 土地面積100㎡(30坪)
- 建物面積95㎡(28.7坪)
- 土地固定資産税評価額3500万円
- 建物固定資産税評価額1000万円
- ローン借入れ額4000万円(期間35年)
とします。
そして、この物件を購入する際の諸費用をシュミレーションしてみると
- 仲介手数料・・・171.6万円(5000万円×3%+6万円+消費税)
- 印紙代・・・1万円
- ローン諸費用・・・116.5万円 ※事務手数料3.5万円+保証料83万円+火災保険30万円=合計116.5万円
- 登記費用・・・30.25万円 ※土地所有権移転登記5.25万円+建物表示登記10万円+建物所有権保存登記1万円+抵当権設定登記4万円+司法書士報酬10万円=合計30.25万円
- 不動産取得税・・・0円 ※土地の不動産取得税(税額52.5万円-【土地評価額3500万円×1/2×床面積の2倍190㎡×3%】=0円)、建物の不動産取得税(建物評価額1000万円-1997年以降の建物控除額1200万円=0円)、共に減税措置により「課税なし」となる。
- 固定資産税等清算金・・・6万円
- 引っ越し費用・・・30万円
以上のようになりますので、表記物件の購入時諸費用合計は約355万円となります。
中古マンション購入時の諸費用計算
続いては、中古マンション購入時の諸費用計算をシュミレーションしてみます。
シュミレーションの対象となる物件は
- 売買価格3000万円
- 築年1990年
- 建物面積66㎡(20坪)
- 土地固定資産税評価額500万円
- 建物固定資産税評価額600万円
- ローン借入れ額2000万円(期間10年)
とします。
この物件の購入に必要な費用は以下の通りとなりますから
- 仲介手数料・・・105.6万円(3000万円×3%+6万円+消費税)
- 印紙代・・・1万円
- ローン諸費用・・・40.5万円 ※事務手数料3.5万円+保証料17万円+火災保険20万円=合計40.5万円
- 登記費用・・・13.65万円 ※土地所有権移転登記0.75万円+建物所有権移転登記0.9万円+抵当権設定登記2万円+司法書士報酬10万円=合計13.65万円
- 不動産取得税・・・0円 ※土地の不動産取得税(税額15万円-【土地評価額500万円×1/2×床面積の2倍132㎡×3%】=0円)、建物の不動産取得税(建物評価額600万円-1989年~1997年までの建物控除額1000万円=0円)共に減税措置により「課税なし」となる。
- 固定資産税等清算金・・・5万円
- 管理費、修繕積立金精算金・・・2万円
- リフォーム費用・・・100万円
- 引っ越し費用・・・20万円
購入時の諸費用合計額は約288万円となります。
中古戸建て売却時の諸費用計算
そして最後に、中古戸建てを売却した際の諸費用計算をシュミレーションしてみます。
シュミレーションの対象となる物件は
- 売買価格4000万円
- 築年2000年
- 土地面積60㎡(18坪)
- 建物面積98㎡(29坪)
- 土地固定資産税評価額1500万円
- 建物固定資産税評価額800万円
- ローン残債額1000万円
とします。
そして、この物件の売却に際しては以下の諸費用が必要です。
- 仲介手数料・・・138.6万円(3000万円×3%+6万円+消費税)
- 印紙代・・・1万円
- 登記費用・・・13.65万円 ※抵当権抹消費用0.4万円+司法書士報酬10万円=合計10.4万円
- インスペクション、瑕疵保険料・・・20万円
- 引っ越し費用・・・30万円
よって、表記中古戸建て売却時の諸費用合計額は約203万円となります。
※不動産の売却に当たって、利益が生じた場合には別途「不動産譲渡所得税」が課税されます。
そして次の項では、「如何にこれらの諸費用を圧縮するか」について考えてみたいと思います。
諸費用を如何に節約するか
これまで見て来た通り、不動産の売買には「かなり高額な諸費用」が発生します。
その中でも特に大きなウェイトを占めているのが、仲介手数料・ローン諸費用・リフォーム費用の3点となりますから、これらを圧縮する方法を中心に経費削減の手法について解説してまいりましょう。
仲介手数料を圧縮
物件の購入において仲介手数料を圧縮する一番の方法は、不動産業者が売主の物件を探し、売主から仲介業者を介さずに直接物件を購入することです。
但し、「建売会社の仕事」の記事でもお話しましたが、自分が分譲している物件について積極的な販売活動を行わない建売屋さんも多いため、こうした物件を探すのには少々労力を要するかもしれません。
このタイプの物件を見つけ出すコツとしては、街で見かける建売メインの不動産屋さんに問い合わせをしまくるか、建築途中の現場を見付け出して、「建築確認の表示」に記載された施主の不動産会社に問い合わせを入れてみるというのが有効な方法となるしょう。
また、最近の仲介業者の中には、売主が不動産業者の場合は買主の手数料不要を謳っている会社や、お客が自分で見つけた物件は仲介手数料半額などのサービスを行っているところもありますから、こうした業者を利用するという手もあります。
一方、不動産の売却に当たっても「売却依頼のお客様については仲介手数料半額」などを謳っている業者も多いですし、自分自身で購入者を発見して「仲介業者に契約関係書類だけを作成してもらう」のであれば、仲介手数料を大幅に値引きしてもらえる可能性があるでしょう。
ローン諸費用の抑える
以前、住宅ローンに関する記事でも書きましたが、失敗しないローンの組み方のコツは「とにかく借入額を少なくすること」です。
今回のローン諸費用計算を見てみても、「借入額が少なければ、それに比例して諸費用も安くなる」ことがお解りいただけたことと思いますので、あらゆる手段を用いて借入額の圧縮を目指しましょう。
リフォーム費用を精査する
中古物件最大のネックが、このリフォーム費用となります。
内覧した時はあまり気にならなかった箇所も、「いざ住む」となった段階や、リフォーム業者に見積もりを取った段階で、「やっぱり工事をしたくなる」のはよくあることです。
こうした状況を回避するためには、売買契約締結前にリフォーム業者同伴でしっかりと物件の下調べをしておくか、不動産業者が売主となっているフルリフォーム済みの物件を購入するのが一番の解決策でしょう。
ちなみに「ご自分でリフォーム業者を手配する」という際には、別記事「リフォーム業者の選び方について解説いたします!」をご参考に業者の選定を行うことで工事費用を圧縮することができるかもしれません。
火災保険料を調整する
住宅購入時には火災保険へ加入される方が殆どとなりますが、この保険料には圧縮の余地があるものです。
同じ火災保険でも雹災や風災など、保険の対象となる災害を選択することで、保険料は変わってくるものですし、地震保険に加入するか否かによる費用の違いはかなり大きなものとなるでしょう。
但し、全国的に大地震の危険性が叫ばれていますし、異常気象による様々な自然災害が発生する昨今ですから、保険の商品選びは慎重に行うべきであると思われます。
繁忙期を回避して引越費用を圧縮する
こちらは「僅かな費用の圧縮」となってしまうでしょうが、1~4月の引っ越し業者の繁忙期を避けて住み替えを行えば、それなりに費用を抑えられるはずです。
★当ブログ管理人執筆の電子書籍(kindle)のご紹介!是非ご一読ください!★
 |  |  | 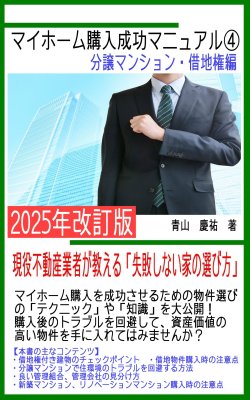 |
売買の諸費用計算まとめ
さて以上が、不動産売買の諸費用計算についての解説となります。
不動産の購入にあたっては、どんぶり勘定で契約へ突き進むことなく、綿密な計算を行った上で無理のない取引を目指したいものです。
一方、売却にあたっては、購入の時ほどは費用が発生しないものの、譲渡所得への課税に対しては充分な注意を払う必要があるでしょう。
また物件によっては、売却に際して土地の分筆・合筆登記、地積更正登記等、建物については解体や滅失登記などを売主の費用負担で行わなければならないケースもありますので、こうした場合には更に出費がかさむことになります。
ではこれにて、売買諸費用の知恵袋を閉じさせていただきます。