マイホームの購入・売却から収益物件の取引に至るまで、あらゆる不動産売買において「最も注意を払わなければならないこと」の一つに挙げられるのが、瑕疵担保責任に関する事項です。
なお、瑕疵とは「物件の隠れた傷(欠陥)」を意味する言葉であり、建物であれば「雨漏り」や「柱の腐食」、土地であれば「土壌汚染」や「物件利用の障害となる埋設物」などがこれに当たります。
そして、『これらの欠陥を保障(担保)する責任』を「瑕疵担保責任」と称しており、不動産取引においてはその責任の所在が非常に重要になって来るという訳です。
ちなみに、2020年の民法の大改正においてはこの「瑕疵担保責任」という概念が消滅し、これに代わって「契約不適合責任」が登場することになりましたが、民法改正前の契約によって生じたトラブルについては時効を迎えるまで瑕疵担保責任によって紛争の解決が図られることになりますから、未だ現役の概念と呼ぶことができるでしょう。
※「瑕疵担保責任」と「契約不適合責任」の違いについては別記事「契約不適合責任とは?わかりやすく解説いたします!」にて詳細な解説を行っております。
さてこの瑕疵担保責任、売買契約においては「一定の期間は売主がその責任を負う」という取り決めになっていることが殆どですが、買ったばかりのマイホームでこうした問題が発覚すれば「買主はあらゆる意味で負担を強いられることになる」でしょうし、売却した方にとっても「大きな悩みの種となる」のは確実です。
そこで本日は「瑕疵担保責任とは?わかりやすく解説いたします!」と題して不動産取引における瑕疵の考え方やこれを巡る諸問題などについて解説してみたいと思います。

瑕疵担保責任のおける「瑕疵の種類」と「契約上の取り扱い」について
瑕疵の意味については既に冒頭で触れましたが、本項ではより具体的に「瑕疵の種類」と「契約上の取り扱い」について解説してまいります。
なお、瑕疵の発生状況は物件種別によって異なりますし、「新築物件であるか、中古であるか」でも契約上のルールが変わって来ますので、以下ではその違いにも着目しながら解説を進めて行くことにいたしましょう。
中古物件における瑕疵担保責任
不動産の取引において「最も瑕疵が問題となる物件」といえば、これはやはり中古物件ということになるはずです。
そもそも建物は非常に複雑な構造をしていものとなりますし、長年住み続けていれば様々な部位に劣化が生じるのは当たり前のことですから、中古物件でのリスクが高まることは致し方のないことでしょう。
なお、その家に実際に暮らしている売主であれば、こうした建物の瑕疵を発見できそうな気もいたしますが、「密かに進行するシロアリの被害」や「お部屋の内部に症状の現れていない雨漏り」などに気付くのは意外に困難なものですから、売買終了後に問題となるケースも少なくありません。
そして、中古物件で一般の方が売り手の場合には、瑕疵担保責任について「引渡しの日から1ヶ月~3ヶ月は売主が責任を負う(期間については売主・買主が協議して定めるが、長くても3ヶ月程度)」とする契約書が一般的ですから、この期間内に問題が発覚すれば『売主はその責任を逃れることはできない』ということになります。
但し、あまりに古い建物が売買対象の場合などには、売主からの希望で「瑕疵担保責任免責(売主は瑕疵に対する責任を負わない)」が契約条件となることも少なくありませんので、この点には注意が必要でしょう。
ちなみに、定められた期間内に瑕疵が発見された場合には、売主・買主立会いの元で状況の確認を行い、その後の「補修工事」や「損害賠償」などについて話し合いを進めて行くことになります。(買主が物件を購入した目的を達せられない場合には契約を解除することができるケースもあります)
一方、同じ中古住宅でも「売主が不動産業者」であるリノベーション物件などでは、瑕疵担保責任を負う期間を引渡しから2年以上に設定しなければならないルール(「以上」とはいうものの殆どの不動産業者は2年と定めています)となっていますから、買主とっては非常に有利な条件となるでしょう。
新築物件における瑕疵担保責任
さて、このようにご説明すると「建物の瑕疵はまるで中古住宅のみの問題」であるように思われるかもしれませんが、たとえ新築であっても雨漏りなどが発生する可能性は充分にあります。
そして新築住宅の場合には、売主が不動産業者であることが前提となりますから、瑕疵担保責任については中古住宅以上に厳しい条件が付加されることとなるのです。
なお、こうした新築住宅に関する瑕疵担保責任についてのルールは、平成11年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により定められたものであり、雨漏りや、建物の基礎・骨組みといった重要な箇所に生じた瑕疵に関して「引渡し後10年間」に渡って売主が責任を負うことになっています。
但し、新築においても表記の建物の重要な部分以外(配管や内装など)については「2年間のみ売主が責任を負う」のが通常です。
土地や住環境に係わる瑕疵担保責任
ここまで主に建物に関する瑕疵について解説してまいりましたが、不動産取引で問題になる瑕疵にはまだまだ様々なパターンがあります。
例えば中古住宅でも新築住宅でも、取引の対象には『土地』が含まれていますので、土壌汚染や地中埋設物(以前にあった建物の基礎が残っていたり、隣地の水道管が敷地を通過している場合など)といった問題が明らかになることは少なくありませんし、変わったところでは地下の水脈なども瑕疵として扱われる可能性があるでしょう。
また、近隣にお墓や葬儀場などがあれば住環境に影響を及ぼす嫌悪施設となりますし、過去に陰惨な事件が発生した物件では、その事実を売主が告知していないことによって心理的瑕疵として問題になることもあります。
更には、都市計画法や建築基準法等における法令上の制限(法令によって定められる土地利用や建築上の制限)を知らずに土地を購入すれば、後になって「制限があることを知っていたら買わなかった」といったクレームになる可能がありますし、
売主的には『自分の所有地である』と思っていた部分について、後日お隣の方から「そこは私の土地だ!」などの主張を受ければ、これも瑕疵として扱われることになるでしょう。
スポンサーリンク
瑕疵担保責任の法律知識
さてここまで、実務における瑕疵担保責任の取り扱いについて解説してまいりましたが、本項では改めて「この責任の法律上の扱い」についてお話しさせていただきます。
瑕疵担保責任は特別法定責任
これまでの解説をお読みになれば、「瑕疵担保責任とは欠陥品を売買してしまった場合の責任の取り方のお話」であることはご理解いただけたことと思います。
ただ、法律に詳しい方の中には「欠陥品については債務不履行責任が追及されるはずでは?」という疑問をお持ちになられた人もおられるはずです。
例えば自動車などを売買して、それが不良品であった場合に売主が問われるのは「債務不履行責任」であり、『瑕疵担保責任』ではありません。
そして、こうした違いが生じる理由として挙げられるのが「取引の対象となる不動産や建物は、自動車などの不特定物ではなく、この世に一つしかない特定物である」という点となります。
確かに自動車などであれば「欠陥があった場合には新品と交換する」という選択肢もありますが、不動産の場合には交換が不可能ですから、債務不履行とは異なる独自の考え方が必要となり、その結果生み出されたのが瑕疵担保責任における「特別法定責任」という概念なのです。
ちなみに、瑕疵担保責任が及ぶ範囲は「信頼利益」のみとされていますから、売主が責任を負うのは当該取引の範囲に限定されることとなり、「瑕疵がなければ買主が転売で利益を上げられた」といった損害については責任を負う必要がありません。
瑕疵が明らかになった場合の処理
さて、売買された物件において欠陥が明らかになった場合の対処方法については、基本的に買主には「欠陥の修補請求」または「損害賠償の請求」をすることができることになっていますが、あまりにも瑕疵が酷く、物件購入の目的が達成できない場合には「契約の解除」も可能です。
なお、買主が瑕疵を発見した際には「1年以内に権利を行使しなければならない」ことに加え、「引渡し後10年で権利自体が消滅時効を迎える」ことになります。
さて、このようにご説明すると「買主に不利な内容」にも聞こえるかもしれませんが、あくまで「発見してから1年、時効まで10年」ですから、結果的には『10年間いつでも権利が行使できる』こととなり、実は買主に非常に有利な法律となっているのです。
そこで実務上では、特約(法律の定めとは別の特別な取り決めを行うこと)にて瑕疵担保責任を負う期間を1~3ヶ月に短縮することで、売主と買主の権利のバランスを調整することとしているのです。
※瑕疵担保責任の消滅時効は10年ですが、瑕疵が重大である場合には不法行為責任を追及するされる可能性があり、この場合の消滅時効は20年となりますのでご注意ください。
瑕疵担保の免責について
前項において瑕疵担保責任を負う期間について解説いたしましたが、築年数の古い物件などでは「そもそも瑕疵担保責任は負わない」という免責の特約を結ぶケースもあります。(不動産業者が売主の場合には法令により瑕疵担保免責特約は無効となります)
ただし、瑕疵担保責任においては「売主が瑕疵を知らなかったこと」が前提となりますので、『瑕疵があるのを知っていたが、黙って引渡してしまった』というケースでは、免責特約は「無効」との判断をされてしまいます。(責任を負う期間を短く設定しても同様です)
一方、売主が契約の際に「物件に問題がある旨」を告知していれば、瑕疵担保の範囲からは除外されることになりますので、買主は引渡し後の責任追及を行えないこととなるのです。
更には、「契約時に発生していなかった問題」も瑕疵担保の対象外となりますから、引渡し後に新たに生じた雨漏りなどは「売主からの保証を受けることはできない」ことになります。
なお、これまでご紹介してきた特殊なケースを除けば、契約書上に瑕疵担保免責と記せば原則として売主はその責任を回避できますが、土壌汚染など買主が想定不能な瑕疵が存在していた場合には「免責されないケース」もありますのでご注意ください。
実務における瑕疵担保責任の諸問題
これまでの記事をお読みくだされば瑕疵担保責任についてはかなりご理解を深めていただけたことと思いますので、本項では実務における瑕疵担保責任の諸問題についてお話をさせていただきます。
既にお話しした通り、不動産の売買において売主は瑕疵担保責任を負うことになりますが、そのリスクが最も高いのは「中古戸建て」であると言われています。
もしも新築であれば、たとえ瑕疵が明らかになっても売主である不動産業者や建築会社がその責任を負うことなりますし、現在の建設技術を考えれば「それ程酷い瑕疵は滅多に生じない」ものです。
また、同じ中古物件でも分譲マンションの場合には、雨漏りと原因となる「外壁」や「屋上」、そして建物の傾きを生じさせる「基礎」などが、管理組合の守備範疇となる『共有部分』であるため、売主個人に修繕などで大きな負担が降り懸かるケースはあまり多くありません。
これに対して中古戸建てでは、全ての部分について売主が責任を負わされることになりますし、築年数が古くなればなる程にシロアリなどのヘビーな瑕疵が潜んでいるリスクも高まる訳です。
なお、こうしたリスクを抱えたままでは中古戸建ての売買が活発に行えるはずもありませんので、近年では国土交通省が中心となり「建物のインスペクション」の活用を積極的に呼びかけています。
インスぺクションについての詳細は別記事「インスペクションと瑕疵保険について解説いたします!」にて解説していますが、簡単に申せば「建物診断」のことであり、売却前にこれを受けることで瑕疵を事前に察知し、
問題が生じた場合にも瑕疵保険に加入することで、売主・買主の双方を保護を図る試みとなりますから、今後は瑕疵担保責任による取引上のトラブルが減少方向に転じる可能性が高いと思われます。
★当ブログ管理人執筆の電子書籍(kindle)のご紹介!是非ご一読ください!★
 |  |  | 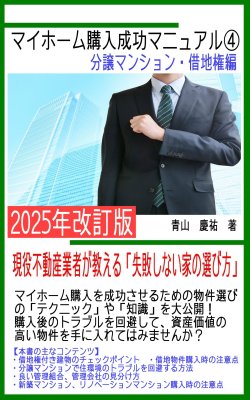 |
瑕疵担保責任まとめ
さてここまで、不動産の取引における瑕疵担保の問題についてお話ししてまいりました。
マイホームの購入は多くの方にとって一生に一度の大きな買い物となりますから、売る側も買う側もできる限りの注意を払って瑕疵に係わるトラブルを回避したいものです。
ちなみに物件の購入に際しては、仲介に入る不動産屋さんを精査することでトラブル回避の確率を高めることができるはずです。
また売却にあたっては、「物件に関して気になること」があれば包み隠さず仲介業者に打ち明けることと、積極的にインスペクションを活用することが紛争回避のポイントとなるでしょう。
なお、「瑕疵」と聞くだけで身がすくむ思いがする方も多いでしょうが、不動産の売買では避けて通れないものとなりますので、正しい知識を身に付けて適切な対処をして行くことが重要でしょう。
ではこれにて、「瑕疵担保責任について考えてみます!」の知恵袋を閉じさせていただきたいと思います。