アパート経営を行っていて痛感させられるのが、『賃貸借契約においては、大家さんが非常に不利な立場に立たされている』という問題です。
一度お部屋を貸し出せば、貸主から解約を行うことはまず不可能となりますから、これは非常に厳しいルールと言えるますよね。
そして、こうした状況を背景に2000年から導入されることになったのが更新なしでスッパリと契約を終了できる定期建物賃貸借契約という新たな契約形態となります。
そこで本日は「定期建物賃貸借契約とは?わかりやすく解説いたします!」と題して、この制度の概要や注意点、実務における活用法などについてご説明してまいりましょう。
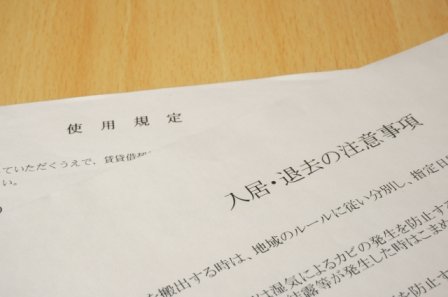
定期建物賃貸借契約はここが違う
さて、定期建物賃貸借契約の内容をご説明するにあたり、まずは通常の賃貸借契約との違いを比較しながら解説を進めていきたいと思います。
契約更新について
さて、冒頭でもお話しした通り定期建物賃貸借契約の最大の特徴と言えるのが、「更新のない契約である」という点です。
一般的にお部屋を貸す際に締結する契約は、正式には「普通借家契約」と呼ばれるものであり、貸主側から更新を拒絶する場合には正当事由(やむを得ない理由)が必要とされていました。
但し、この正当事由については「大家さんが自ら建物を利用したい」「建物が老朽化してきた」くらいの理由では、到底解約が認められないのが通常となります。よって、普通借家契約においては
- 一度契約を結んでしまうと更新を拒絶することが非常に困難となる
- 更新契約を締結しない場合は、法定更新となって半永久的に契約が継続していくことになる
という状況となってしまうのです。
※もちろん、契約違反になる程の迷惑者(刑事事件を起こす者等)や、倒壊寸前で居住者の身に危険が迫っている場合には正当事由が認められる可能性は高いですが、紛争に発展した場合にはその判断を裁判所に委ねるしか方法はありません。
これに対して定期建物賃貸借契約では、
取り決められた期間でバッサリと契約を終了することができる
というルールになっていますので、物件オーナー様にとってはかなり有利な内容と言えるでしょう。
なお、定期建物賃貸借契約には更新という概念がありませんが、契約終了後に再契約を行うことは可能となりますので、新たに契約を結び直すことで入居を継続させることができます。
契約期間について
契約期間については、
- 契約期間の上限なし
- 最短契約期間は1年以上とする必要あり
- 契約期間が1年に満たない契約を締結すると「期間の定めのない(期間永遠という意味)賃貸借契約」とみなされる
というのがルールでした。
これに対して、
- 契約期間の上限なし
- 1年未満の契約期間も認められる(解約通知は不要)
と定められており、短期の賃貸借契約が認められるようになったのです。
中途解約について
中途解約に関しては
- 貸主・借主共に原則として中途解約は不可
- 特約があれば中途解約は可能
- 貸主からの中途解約には正当事由が必要
- 貸主からの中途解約には6ヵ月の期間と正当事由が必要
- 借主からの中途解約には3ヵ月の期間が必要
と定められていました。
これに対して定期建物賃貸借契約においては
- 貸主・借主共に原則として中途解約は不可
- 貸主からの中途解約は特約と正当事由が必要
- 借主からの中途解約は特約が必要
- 居住用物件については「床面積200㎡未満」「やむを得ない事情がある」ことを要件に、特約がなくても1ヵ月後に借主からの中途解約が認められる
というルールになっています。
賃料の改定
賃料の改定については、普通建物賃貸借において
- 借地借家法の定めにより増額・減額が共に認められる
- 賃料増額禁止の特約は有効
- 賃料減額禁止の特約は無効
であるのに対して、定期建物賃貸借では
- 借地借家法の定めにより増額・減額が共に認められる
- 賃料増額、減額禁止の特約は共に有効
というルールになっているのです。
★当ブログ管理人執筆の電子書籍(kindle)のご紹介!是非ご一読ください!★
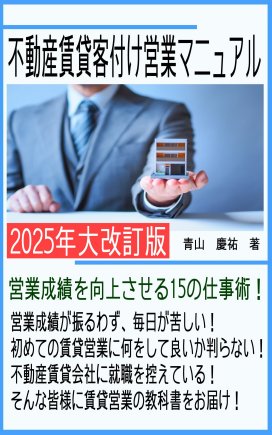 | 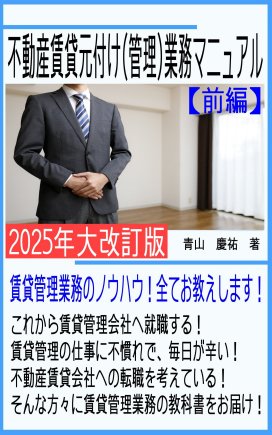 | 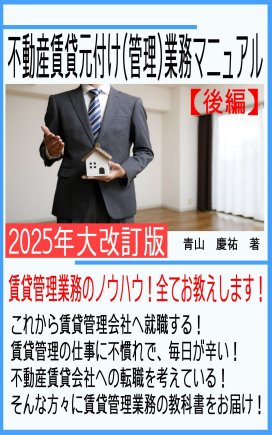 |
定期建物賃貸借契約のポイントと注意点
さてここからは、実際に定期借家契約を締結する際のポイントと注意点を解説してまいりましょう。
賃貸借契約書の内容
まずは契約書に書いておくべき内容ですが、基本的には以前に解説した一般的な賃貸借契約書の作り方と同様のもので問題はありません。
但し、契約書のタイトル(表題)には定期建物賃貸借契約であることをしっかりと記載した上で、契約更新の条項については
「本契約は借地借家法第38条第1項における定期建物賃貸借であり、契約の更新がなく、期間の満了により本件賃貸借契約は終了します。」
という文言を必ず入れておきましょう。
ちなみにネット検索を行うと、「定期借家契約には公正証書による契約が必須」などと書かれているサイトを時折見掛けますが、これは誤った見解となります。
実は法令には「公正証書等で契約すること」との定めがありますから、これを根拠に『公正証書が必須』との勘違いをしている方が多いようですが、あくまでも「公正証書(等)」ですから、一定のルールさえ守れば通常の契約書でも『有効』と判断されるのです。
但し、公正証書での契約であれば賃料の滞納に対して「裁判所の判決無くして強制執行が行える」などのメリットもありますから、状況に応じて公正証書と通常の契約書を使い分けるべきでしょう。
「定期建物賃貸借契約の説明書」の交付
前項でご紹介した賃貸借契約書の内容に加え、重要となるのが契約締結時に「定期建物賃貸借契約の説明書」の交付を行うこととなります。
なお、このように書くと『説明書の作成が難しそう』と思われるかもしれませんが
- 「借地借家法第38条第2項に基づき、本物件の賃貸借契約は更新がなく、期間の満了により契約は終了し、明け渡しを行わなければならない」という説明内容
- 契約期間の表示
- 物件名・所在地の表示
- 「本状の内容について借地借家法第38条第2項に基づく説明を受けました」という借主の確認
- 借主の署名・捺印
以上の内容が記されていれば、書式にもルールはありません。
なお、不動産の契約における説明書と言えば宅地建物取引業法35条の「重要事項説明書」を思い浮かべる方が多いでしょうが、定期建物賃貸借契約の説明書は全くの別物となりますので、重説とは別紙で書面を作成して説明を行う必要があるでしょう。
ちなみに、この説明書を交付していない場合には定期建物賃貸借契約が成立したことにならず、普通建物賃貸借の契約とみなされますのでご注意ください。
「定期建物賃貸借契約」の終了通知
そして最後に行わねばならないのが、定期建物賃貸借契約終了の1年~6ヶ月前に貸主から借主へ行う「終了通知」となります。
こちらも記載内容は非常に簡単で、
- 「●月●日に契約が終了するので、定期建物賃貸借契約により物件の引渡しをせねばならない」という契約終了の通知文
- 契約期間の表示
- 物件名・所在地の表示
以上が必要な記載事項です。
なお、定期建物賃貸借契約の終了通知において、最も重要となるのが「借主が確実に通知を受け取り、内容を理解した証拠を残すこと」となります。
よって、普通郵便で終了通知を送付しただけでは「通知を受け取っていない」と言われてしまう可能性もありますので、貸主としては非常に不安です。
また、証拠を残すとなれば内容証明郵便が思い浮かびますが費用も高額であり作成にも手間が掛かるため、使い勝手はあまり良くありません。
そこでお勧めなるのが、
貸主・借主が互いに署名、捺印を行う、覚書のような形式の終了通知書
となります。
貸主・借主が揃って署名、捺印を行っていれば、流石に「説明を受けていない」という言い逃れはできないでしょう。
そして実務上は、終了通知書を2部作成して借主へ送付して、署名捺印済みのもの1部を返送してもらうケースが多いでしょうが、より確実性を求めるのであれば、直接借主と対面して書類の取り交しを行いたいところです。
ちなみに、契約終了の1年~6ヶ月前に終了通知を送り忘れてしまった場合には「通知が行われてから6ヶ月後に契約が終了する」こととなり、退去日が遅れる原因となりますのでご注意ください。
一方、期間が1年未満の定期建物賃貸借契約においては終了通知が不要となります。
実務における定期建物賃貸借契約の活用法
ではここからは、実務における定期借家契約の活用方法について解説を行っていきたいと思います。
転勤や取り壊し予定などの事情による一時的な貸し出し
さて、最も一般的な定期借家契約を活用するシーンとしては
- 転勤などの理由で自宅を一時的に貸し出したい
- 建物の建て替えを検討しているが、工事に着手するまで期間も部屋を貸し出したい
といった状況が考えられるでしょう。
転勤などによって『折角購入した自宅に住むことができない』という時には、定期借家契約を活用することで賃料収入を得ながら、再び転勤で戻ってきた際には「一定の期間で入居者に退去してもらうことが可能」となるです。
また、運用しているアパートが『そろそろ建替え時期だ』という状況に際しては、空き部屋に定期借家契約を締結した入居者を住まわせておくことで、着工ギリギリまで賃料収入を確保することができますから、これは大家さんにとって非常に大きなメリットとなるでしょう。
但し、定期借家契約で新規募集を掛ける際は、入居者に不利な契約内容となるため一般の賃料相場の80~70%の賃料設定を行う必要があることも申し添えておきます。
属性に不安のある入居希望者に対する担保としての契約
収益物件の運用を行っていると、時には「近隣トラブルを起こしそうな入居者」や「滞納のリスクの高そうな者」を入居させなければならないケースもあるかと思いますが、こうした場合には
当初1年を「定期建物賃貸借契約」として、問題がなければその後は「普通借家契約」に切り替える
という方法が有効です。
この方法であれば、入居後に不都合が生じた場合でも『時間の経過』によって立ち退きが可能となりますし、問題のない借主であることがわかれば「普通借家契約に切り替えて入居を続けてもらう」こともできるでしょう。
但し、入居審査において『定期建物賃貸借契約にして欲しい』という要望は、入居希望者にとって大きな負担となりますから「定期建物賃貸借の契約期間中は賃料を減額するなどの好条件」を提示することが交渉をまとめるポイントとなります。
立退き交渉のカードとして契約
定期建物賃貸借契約は立退き交渉のカードとして利用できるケースもあります。
例えば、繰り返し近隣に迷惑を掛ける入居者を退去させたい場合には、
「次に迷惑行為を行った場合には2年間の定期建物賃貸借契約に切替えを行い、状況に改善が見られれば普通建物賃貸借契約を再度締結する」
といった約定を交わすのです。
「迷惑行為」などについては、それだけを理由に退去まで持ち込むのは意外に困難ですから、敢えて「定期建物賃貸借契約」という逃げ道を残して更正のチャンスを与えつつも、再度問題を起こした場合にはスッパリと立ち退きを迫ることができる状態にしておくという訳です。
この方法であれば不要な争いを避けつつも、状況次第では確実に退去まで持ち込むことができますから、非常におすすめな方法であるかと思います。
スポンサーリンク
定期建物賃貸借契約とは?わかりやすく解説まとめ
さて、ここまでが定期建物賃貸借契約をテーマに解説を行ってまいりました。
名前だけ聞くと『少々敷居が高そう』にも思えるこの契約ですが、実は非常に手軽なものであることがご理解いただけたはずです。
また、既にお話ししたように定期借家契約は収益物件の運用における様々なシーンで活用が可能となりますから、入居審査や立ち退きに際してお試しいただければ幸いです。
ではこれにて「定期建物賃貸借契約とは?わかりやすく解説いたします!」を知恵袋を閉じさせていただきたいと思います。