アパートを借りる際などに避けては通れないのが、「賃貸借契約の締結」というイベントです。
そして、賃貸契約は私たちの生活に非常に身近なものとなりますから、「これまで何度も経験したことがある」という方も多いかと思いますが、『契約書の内容をしっかりと把握しているか?』と尋ねられると、返事に窮してしまう方も多いでしょうし、
これから初めてお部屋を借りるという方の中には、『不利な契約を締結させられたらどうしょう・・・』との不安を抱えておられる人もいらっしゃるはずです。
また不動産業界においても、売買の営業マンの中には「賃貸の契約なんて簡単!」などと豪語する方もおられますが、賃貸であっても契約の内容次第で大きなトラブルに発展するケースは決して少なくありませんので、『賃貸には賃貸の難しさがある』というの現実です。
そこで本日は「賃貸契約書の内容を解説いたします!(居住用)」と題して、居住用賃貸借契約書の注意すべきポイントなどについてご説明させていただきます。
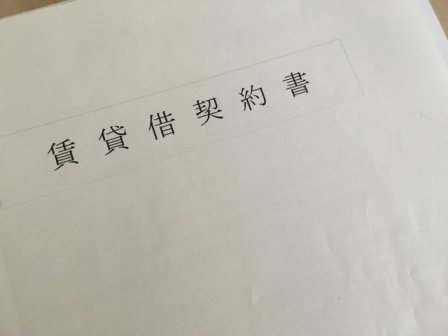
賃貸借契約書のポイントと注意点を解説!
では早速、「賃貸借契約書の条文解説」と「契約内容のポイントや注意点」を見て行くことにいたしましょう。
なお、今回取り上げる賃貸借契約は居住用物件が対象であり、且つ借主が個人のケースとなります。
賃貸の目的に関する条項
賃貸借契約書の冒頭に記されることが多い条項です。
賃貸契約の目的を明らかにして、「指定以外の用途に物件を使わせない」ことがこの条項の狙いですから、今回のケースでは「居住用」と記されることが多いでしょう。
なお、暴力団対策法の関係で記載しておくべき「組事務所としての使用を禁止する定め」についてもここで謳っておくべきです。
賃料等の条件に関する条項
月額賃料を表示する条項となりますが、管理費や共益費などがある場合には、ここで合わせて記しておきましょう。
また、賃料支払のタイミングを取り決めるのもこの条項となります。
一般的には「翌月分を当月末までに」という取り決めが多いようです。(例、5月分賃料は4月末までに支払うこと)
更には、月の途中で解約が発生した場合になどに備え、日割り計算の方法についても取り決めておけば完璧でしょう。
なお、一般的な日割り計算の方法は「月毎の日数に係らず、日割り計算の分母を30日」とするパターンとなりますが、最近では「実際の月日数を分母とする」という条文も多く見掛けるようになりました。
契約期間に関する条項
居住用物件の場合には、契約期間を2年間とするのが一般的となります。
そして、条文においては「●●●年●月●日~●●●●年●月●日」というように、具体的な年月日を記載しましょう。
なお、この条項では「賃貸借契約の更新」についても触れている契約書式が多く、「貸主・借主は協議の上、契約の更新が可能である旨と、更新料の額(通常・新賃料の1ヶ月分)」等について取り決めることになります。
※判例により「新賃料の1ヶ月分」の更新料は合法とされていますが、それ以上高額な更新料を取り決めた場合には無効と判断される可能性があります。
ちなみに更新料については、入居者が更新契約に応じてくれず「法定更新」となった場合、たとえ訴訟を起こしても更新料の支払い命じられる可能性は決して高くないのが実情です。
こうした事態を避けるためには「法定更新となった場合も、借主は更新料を支払うものとします」との一文を付加しておく必要があるでしょう。
敷金の扱いに関する条項
この条項では、借主から貸主に預け入れる敷金の額を明記しておきましょう。
また敷金の基本的な扱いである、「明け渡し時に無利息で返還する旨」と「賃料の滞納や部屋を汚損があった場合には、債務の弁済に充当する旨」もここで謳っておきます。
更には、賃料が増額・減額された場合には「敷金も変更額に合わせた積み増し、払い戻しを行う旨」を記するのが一般的です。
なお、私的に加えておいた方が良いと思うのが「借主からの敷金相殺禁止条項」となります。
これは、借主からの「来月分の賃料は敷金から差し引いておいて!」という要望を阻止するための条項です。
以前、こうした申し出を実際にして来た入居者がいましたので、今では欠かさずこの文言を入れるようにしています。
修繕費の負担に関する条項
後々の争いを避けるために、賃貸借契約書では「修繕に関する取り決め」もしっかりと行っておくべきでしょう。
まずは前提として、建物の本体の修繕費は貸主負担、水道パッキン・蛍光灯などの消耗品は借主負担である旨を謳っておくべきかと思います。
またこれに加え、「借主が建物本体の損傷を発見した場合には、速やかに貸主に通知する」ことも加えておきたいところです。
そして、「貸主が損傷の修繕を行わない時は、借主が修繕を行った上、これに要した費用を貸主に請求することができる」という定めが一般的でしょう。
諸費用負担に関する条項
入居後の生活における電気・ガス・水道・インターネット等の使用料は借主の負担、土地や建物の固定資産税などの公租公課は貸主の負担である旨を記します。
また、「退去時には借主が未精算の各使用料を精算する義務を負う」旨も合わせて謳っておきましょう。
賃料改定に関する条項
社会情勢が大きく変わった場合には、「賃料の増額・減額が、貸主と借主の合意の下で可能である」という文言になります。
但し、契約途中での賃料変更は様々な問題が生じる可能性がありますので、「賃料交渉は更新契約時」と定めておくのが無難でしょう。
借主の義務に関する条項
お部屋の貸出しにあたり、借主に守ってもらう義務について取り決める条項となります。
取り決める事項が多くなりますので、箇条書きでなるべく詳細に記しておくのがポイントでしょう。
記すべき事項については、下記の内容が一般的なものとなります。
- お部屋の又貸しや譲渡の禁止
- 危険となる行為や、迷惑行為の禁止
- 共用部分への私物放置、ポスターなどの貼り付け禁止
- 物件の改造・改築を勝手に行わないこと(配管・電気設備を含む)
- ペットの飼育禁止
- 重要物搬入に際しての通告義務
- 入居人員変更の届出義務
- 長期不在時の届出義務
- 連帯保証人に異動(変更・死亡)が発生した場合の告知義務
- 善管注意義務(建物を大切に扱う義務)
- 分譲マンションの場合には、管理規約・細則等の遵守義務
以上が、最低限記すべき内容となるでしょう。
★当ブログ管理人執筆の電子書籍(kindle)のご紹介!是非ご一読ください!★
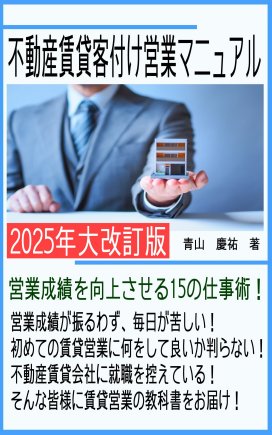 | 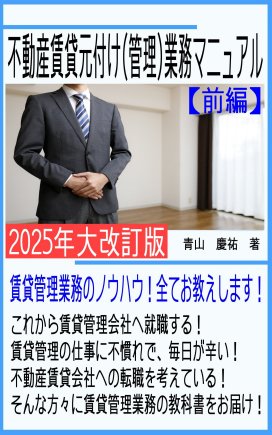 | 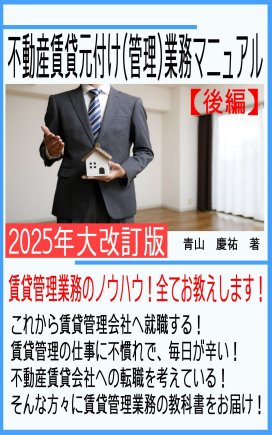 |
物件への立入りに関する条項
賃貸物件の運用を行っていると、様々な事情で賃貸中の物件の室内へ立ち入りを行わなければならない状況も出て来るものです。
そんな事態に備えての取り決めを事前に定めておくのが、本条の目的となります。
通常の立ち入りは建物のメンテナンスや修繕がメインとなるでしょうから、こうした際には「修繕等が必要となった場合には借主の立合い下、物件内に立ち入ることがあるので作業に協力すること」という条項を入れておきましょう。
但し、災害発生時など急を要する場合には「承諾を得ずして立ち入る場合がある」旨も加えておくべきです。
反社会勢力に関する条項
反社会勢力の入居を回避するために、まず本条項では『貸主・借主は反社会的勢力の構成員、またはそれに類する団体に所属していないことを確約します』という宣誓を行います。
そして、又貸しなどに備えて『借主は反社会的勢力への転貸および賃借権の譲渡を行ってはならないものとします』という文言も加えておくべきでしょう。
契約解除に関する条項
「こうした行為を行うと賃貸借契約が解除になります」という事項について定める条項となります。
なお、この条項では「解除となる様々なケース」を定めることになりますので、箇条書きにして判りやすく記していきましょう。
なお、一口に『解除になる』と言っても「即時解除となる事項」と「猶予期間(催告期間)を設けた上で解除となる事項」がありのますので、二通りに分けて記載を行います。
- 申込書への虚偽記載
- 反社会勢力に関する条項に違反した場合
- 暴力団事務所としての物件利用や、暴力団に類する団体に所属する人物を出入りさせた場合
- 覚醒剤・危険ドラッグの使用や製造
- 信義則違反や社会的信用失墜行為を行った場合
- 賃借人の義務条項違反、その他契約条項への違反があった場合
- 賃料の2ヶ月滞納(判例上1ヶ月滞納は解約要件になりませんので、ご注意ください)
- 建物に損害を与えたにも係らず、修繕費の支払いを怠った場合
以上が、一般的な記載内容となるでしょう。
解約予告に関する条項
「借主から契約解除を申し出る場合のルール」を取り決める条項となります。
そして居住用物件の契約においては「解約予告日から1ヶ月分の賃料は理由の如何を問わず支払義務がある」と定めるのが通常です。(所謂「1ヶ月前予告のルール」です)
よって、退去日まで1ヶ月を切った時期に解約予告をした場合には、たとえ引っ越しが先行しても、予告日から1ヶ月分の賃料を支払わなければなりません。
一方、解約予告日を過ぎても入居を続けた場合(退去をしない場合)に備えて、「退去が遅滞した場合には通常の日割り賃料の2倍の賃料が発生する」などのペナルティーを付加する条項を加えておくのがお勧めです。
賃貸借契約終了時の取り決めに関する条項
さて、この条項においては、まず最初に契約終了時に借主が原状回復義務を負う旨を明記しておきましょう。
なお具体的な原状回復の方法については、クロスや畳・襖など設備ごとに細かい取り決めを記した「別表」を契約書に添付しておけば、後々の紛争を予防できるはずです。
- 壁紙(経年変化/貸主負担、タバコによる汚損/借主負担)
- フローリング(日焼け/貸主負担、傷/借主負担)
- 障子・襖(日焼け/貸主負担、シミ・傷/借主負担)
- 畳(日焼け・通常の擦り減り/貸主負担、汚れ・大きな傷/借主負担)
また、「借主には未納賃料の支払いや、水道・電気代等の精算を行う義務があること」「残置した荷物を貸主が任意で処分できる(但し撤去費用は借主に請求する)旨」もこの条項に加えておくべきでしょう。
更には、「天災地変による建物滅失や、都市計画上の収容などの事態が発生した場合には契約が終了する旨」と「貸主の都合によらない契約終了に際しては、立ち退き料等の請求ができない旨」も組み込んでおけば完璧でしょう。
連帯保証人に関する条項
賃貸借契約における連帯保証人に関する取り決め事項となります。
通常の契約書の雛形ですと、「連帯保証人は借主が負担すべき一切の債務を定められた極度額の範囲内で保証する」という程度の文言となりますが、
万全を期するならば、借主との連絡が取れなくなった場合に備えて「契約の解除権」「返還敷金の代理受領権」「残置物の処分権」などを連帯保証人に与える旨の条文を加えておくのがよいでしょう。
賃貸保証会社について
近年の賃貸借契約では賃貸保証会社を利用することも少なくありませんので、保証会社利用についてのルールも定めておきます。
そして、まずは謳っておくべきなのが「貸主が指定する保証会社を借主が利用すること」が賃貸借契約成立の前提であるという旨です。
また万が一、利用する賃貸保証会社が倒産した場合などには、借主は新たな保証会社と再契約を行うか、連帯保証人を擁立しなければならない等のルールを定めておきましょう。
免責条項
免責条項においては『地震や火災などの災害、盗難などによって貸主・借主が被った損害は免責とする』のが基本となります。
また、設備の故障などに備えて『貸主・借主の責任に帰さない設備故障によって被った損害についても免責となる』旨も謳っておきましょう。
建物の一部滅失による賃料
2020年の民法改正により、『建物の一部が滅失し、賃貸部分が減少した場合には賃料の減額が可能』となりましたので、この条項ではその旨を記しておきます。
但し、『貸主・借主の協議の上で減額を行うものとし、減額割合は使用できなくなった面積を基準とします』との文言も加えておくべきです。
信義則に関する条項
あらゆる契約書の雛形にほぼ確実に記されているのが、こちらの「貸主・借主は互いに誠意を持って契約を履行しましょう」という条項になります。
一見、あまり役には立たない条文であるようにも思えますが、借主が不法行為などを行った場合に威力を発揮することになりますから、念のために組み込んでおきましょう。
管轄裁判所に関する条項
こちらもお約束の条項となりますが、退去後に訴訟を起こされた場合などに備えて、「物件所在地の裁判所にて訴訟を行う旨」を記しておくのがおすすめのです。
スポンサーリンク
賃貸契約書解説まとめ
さて以上が、居住用個人向け賃貸借契約書の条文と注意点の解説となります。
アパートなどを契約する際は、仲介業者が条文を早口で読み上げていきますので「なかなか理解が追い付かない」ものですが、こうして整理してみると条文のポイントや注意点がご理解いただけるのではないでしょうか。
また、不動産業界においては「賃貸の契約なんて楽勝!」などといった言い方をする人もいらっしゃいますが、賃貸借契約書の作成においてミスをしたばかりに、大家さんに甚大な損害を与えてしまったり、訴訟に巻き込まれてしまったりする可能性は充分に有り得ますから、しっかりと練り込まれた契約書を作成していただきたいものです。
ちなみに、今回ご説明した「ベースとなる条文」と並んで、賃貸借契約書の中で非常に重要なものとなる「特約事項」へ記すべき内容につきましては、次回の記事「賃貸契約書の特約事項の作り方を解説いたします!」にて詳しく解説をさせていただきたいと思います。
ではこれにて、「賃貸契約書の内容を解説いたします!(居住用)」の知恵袋を閉じさせていただきます。