これまで本ブログでは「急傾斜地法」「土砂災害防止法」など、様々な土砂災害に関する法律についての記事をお届けしてまいりました。
そして、これらの法令は日々私たちの生活を災害から守ってくれていますが、実はもう一つ「砂防法」という絶対に押さえておくべき法律があるのをご存じでしたでしょうか。
そこで本日は「砂防法とは?わかりやすく解説いたします!」と題して、砂防4法の中で最も古い歴史を持つ土砂災害防止法令の概要をご説明していきたいと思います。

砂防法とは
砂防法は明治30年に施行された非常に歴史のある法律であり、
豪雨などにより発生する土石流を未然に防ぐと共に、その被害を最小限に抑えることを目的に定めらた法令
となります。
そして「土石流」とは土砂災害の一種であり、豪雨などにより山から谷に向けて水と土、そして石や岩が時速20~40キロもの速さで押し寄せてくる現象となります。
なお、明治時代に土砂災害対策と聞くと非常に先進的な法律であるように思えるかもしれませんが、実はこの時代の森林地帯では無秩序な伐採が横行しており、多くの土石流が発生していたのです。
こうした事態を受けて施行された「砂防法」においては、災害発生リスクの高いエリアを国土交通大臣が『砂防指定地』に指定を行い、その管理については都道府県知事が職務に当たるルールとなっています。
土石流が起こりやすい地形としては、
- 流れが速い渓流
- 河川が谷から平地に流れ込む扇状地
などが挙げられますので、砂防指定地は山間部やこれに隣接する平地の付近に指定されるケースが多いようです。
また、砂防指定地においては土石流を抑止し、その被害を最小限にするために砂防ダム(別名/砂防堰堤えんてい)と呼ばれる「土砂が谷に流れ込む前にせき止める施設」などを設置する『砂防事業』も行われることになります。
ちなみに砂防法は「自然の地形が生み出す土石流」を防止することを目的としているため、盛り土などの開発行為よって人為的に危険性が生じた箇所については原則として砂防指定地に指定されることはありません。
*同様の理由により、砂防指定地が開発行為の抑止を目的に定められることもありません。
*盛り土などにより人為的に発生した土砂災害危険箇所については「宅地造成及び特定盛土等規制法」により制限が行われます。
砂防指定地の制限について
さて、砂防法の概要についてはおおよそご理解いただけたことと思いますが、この法律によって指定される砂防指定地においては土石流の発生を防ぐために様々な行為が制限されることになります。
なお、実際の条文には
砂防法第2条2項により、国土交通大臣が指定した砂防指定地においては、都道府県知事が治水上の砂防を行うために一定の行為を禁止または制限できる
とされておりますので、砂防指定地の制限については「自治体ごとに条例でルールが定められる」ことになるのです。
ちなみに各自治体の具体的な砂防指定地の制限としては
千葉県
- 土地の掘削、盛土、切土その他土地の現状を変更する行為
- 土石の採取、鉱物の採取またはこれらの堆積若しくは投棄
- 立竹木の伐採
- 施設または工作物の新築、改築、移転若しくは除却
- 竹木の滑下または地引による搬出
- 火入れまたはたき火
引用元: 千葉県HP
長野県
- 建築物、施設その他の工作物の新築、改築、増築、移転又は除去
- 立木若しくは竹の伐採又はそれらの滑下若しくは地引による運搬
- 切取り、盛土、掘削その他の土地の形質を変更する行為
- たん水又は水を放流し、若しくは浸透させる行為
- 土石砂れきの採取、鉱物の採掘又はこれらの集積若しくは投棄
- 樹根又は草根の採取
- 牛馬その他の家畜の放牧
引用元: 長野県砂防指定地管理条例第3条
以上のように各々の自治体が条例により独自のルールを定めていますが、掘削や開発行為については必ず制限の対象となっているため、都道府県知事の許可なく建物を建築することはできません。
また、こうした制限により土地の資産価値はどうしても低下してしまうため、多くの自治体では砂防指定地について固定資産税の減免措置(固定資産税評価額の減免など)を講じています。
★当ブログ管理人執筆の電子書籍(kindle)のご紹介!是非ご一読ください!★
 |  |  | 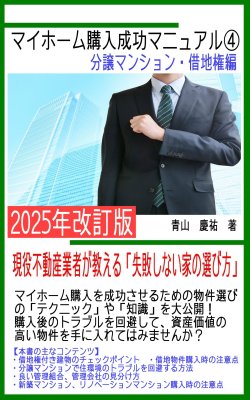 |
砂防法と他の土砂災害に係る法律の関係
冒頭でも申し上げた通り、本ブログではこれまで様々な土砂災害に関する法律を扱ってまいりましたので、本項では砂防法と他の法令の違いについてご説明しておきましょう。
まず、「砂防法」を含めて砂防3法と呼ばれる「急傾斜地法」、「地すべり等防止法」との違いにつきましては
- 対象となる土砂災害/土石流(谷へ土砂が流れ込むことで生じる災害)
- 指定される区域/砂防指定地
- 対象となる土砂災害/地すべり(砂と土など、異なる地層の境目がすべり落ちて生じる災害)
- 指定される区域/地すべり防止区域、ぼた山崩壊防止区域
- 対象となる土砂災害/がけ崩れ(角度の急な崖が崩落することで生じる災害)
- 指定される区域/急傾斜地崩壊危険区域
以上のように砂防3法は「対象とする災害の種類」が異なるため、自ずと指定される危険区域にも違いが生じることになります。
ちなみに、上記砂防3法に土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)を加えたものを砂防4法と呼びますが、土砂災害防止法は砂防3法が対象とする土砂災害によって『被害を受ける可能性のあるエリアを指定するための法律』であるため、その性質は他の法令と大きく異なるものとなるのです。
砂防法と不動産取引
さて、これまで砂防法と砂防指定地について解説してまいりましたが、ここでは『砂防指定地の不動産取引』についてご説明していきたいと思います。
まず気になるのが「砂防指定地の売却や購入はできるのか」という点になりますが、売買を行うこと自体には何の問題もありません。
なお、売却に際して行われる重要事項の説明においては
対象不動産が「砂防指定地」に指定されている旨は、必ず告知すべき事項となっています
ので、事前に自治体の土木事務所などに赴いての役所調査が必須となります。
また、既に解説した通り砂防指定地においては
自治体ごとに条例で独自の法的な制限が定められていますので、買主へその内容を正しく説明しなければならない
という点にも注意が必要です。
ちなみに何処の自治体においても、砂防指定地での掘削や工作物の設置には都道府県知事の許可が必要となるため、簡単にはマイホームの建築を行うことはできませんが、地域を管轄する土木事務所と相談することで建築が可能となるケースもあるでしょう。
但し、通常の不動産と比べて制約が多い土地であることは間違いありませんし、そもそも土石流に巻き込まれるリスクが非常に高い地域となりますので、資産価値としては非常に低い土地となることは避けられません。
スポンサーリンク
砂防法とは?わかりやすく解説まとめ
さてここまで、砂防法をテーマにお話をしてまいりました。
線状降水帯の発生やゲリラ豪雨によって土砂災害が頻発する昨今ですから、マイホームの購入に当たってはハザードマップの調査が欠かせなくなりつつありますが、土砂災害にも様々な種類と法律がありますので正しい知識を身に付けた上で不動産取引に臨んでいただきたいところです。
なお、「土砂災害警戒区域」や「急傾斜地崩壊危険区域」に比べて、『砂防指定地』は不動産取引において遭遇する機会が少ないのが実情ですが、土石流という非常に危険な土砂災害のリスクが高い土地となりますので、購入に際しては細心の注意を払うべきでしょう。
ではこれにて、「砂防法とは?わかりやすく解説いたします!」の知恵袋を閉じさせていただきたいと思います。