アパート経営を行っていると、実に様々な問題やクレームが発生してくるものです。
なお、このようなお話を聞くと『対応は管理会社に任せておけば良いのでは?』と思われるかもしれませんが、たとえ優秀な管理会社でも「オーナー判断が必須」という状況は多々ありますので、大家さん自身もクレームに対して的確な判断と対応を行えるように自身のスキルを向上させることが重要でしょう。
そこで本日は「賃貸のクレーム対応のコツをご紹介いたします!」と題して、賃貸物件を運用する上で遭遇する様々なトラブルへの対処法をご紹介してまいりましょう。

賃貸経営で発生する苦情の種類
既に賃貸経営を始めている方はともかく、これから投資を始めようという方には「どのような苦情が舞い込んでくるか?」という点も気になるところであると思いますので、まずはクレームの種類から解説を始めさせていただくことにしましょう。
お部屋の設備に関するクレーム
大家さんに寄せられるクレームの中で最も数多いのが、お部屋に設置されている設備の不具合などに関する苦情となるでしょう。
近年では新規募集の段階から「エアコン」「電灯」「ウォシュレット」などが設置されているのが当たり前となっており、これらを『設備』として契約している場合には基本的にそのメンテナンスは大家さんの費用負担となります。
特にエアコンや給湯器などは生活に欠かせないものとなりますから、迅速な修理が求めらることになるでしょう。
建物本体に関するクレーム
さて、アパートなどの一棟もの物件の運用を行なっていると雨漏りや、排水管・水道などからの漏水など建物本体にまつわる苦情も多いものです。
設備のクレームとは異なり、交換などでは済まないケースも多いですから、より慎重な対応が求めらることなるでしょう。
また、階段が滑りやすい、エントランスが暗いなど共用部分に関する苦情も少なくないのが特徴です。
近隣に問題に関するクレーム
こちらは非常に厄介な問題となりますが、「上の階の住人の生活音が煩い」「隣に住む者が嫌がらせをしてくる」など入居者間でのトラブルも大家さんが対処すべきクレームとなります。
また時には、入居者と収益物件に面する一般のお宅との間で揉め事が勃発することもあるでしょう。
契約条件に関するクレーム
契約途中での「賃料減額請求」や「更新料の支払拒否」、「退去時の敷金精算などの際に生じるトラブル」などが、契約条件に関するクレームに当たります。
お金が絡むトラブルであるだけに、より繊細な対応が求められることになるはずです。
★当ブログ管理人執筆の電子書籍(kindle)のご紹介!是非ご一読ください!★
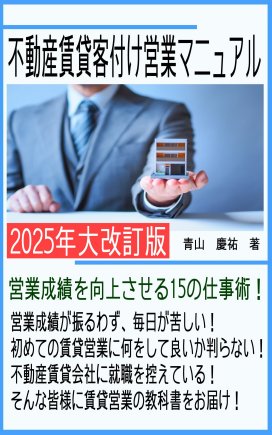 | 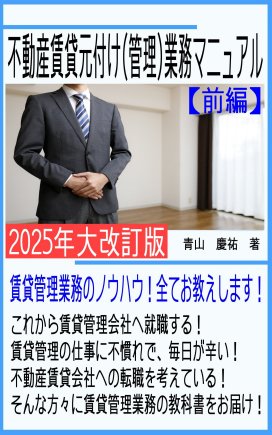 | 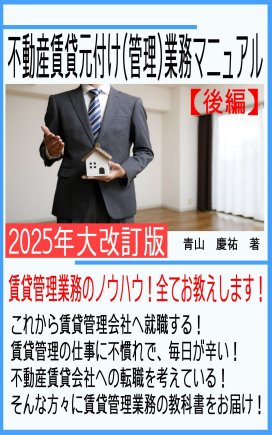 |
賃貸クレーム対応の秘訣をご紹介
さてここまでの解説にて、賃貸物件を経営する際に発生しがちなクレームの種類についてはおおよそご理解いただけたことと思います。
そこで本項では、それぞれのクレームに対する具体的な対処法について、お話ししてまいりしょう。
設備に関するクレームへの対処
先程も申し上げた通り、賃貸物件を運営する上で最も多いのがこのタイプのクレームとなるはずです。
「エアコンの不具合」から「給湯器の故障でお湯が出ない」などそのパターンは様々でしょうが、こうした苦情への対処で最も大切なのは
『発生しているトラブルの状況を正確に把握すること』
となります。
つまり、漠然と「不具合が生じている」という情報だけを得ても何も判断することができませんから、より具体的に「何がどのように、そして如何なる状況で問題が発生しているのか」をしっかりとヒヤリングすることが重要となってくるのです。
そして修理業者に依頼を行う際には、入居者から入手した詳細な情報を正確に伝えて『想定される作業内容を事前に把握』しておきましょう。
例えばエアコンの故障であれば、事前に修理業者へ詳細な状況説明をすることで
「年式と症状からして経年劣化による不具合の可能性が高く、部品交換では済まず、本体交換になる確率が高い」
といった意見を聞くことができれば、その後の判断も迅速に行えるようになるという訳です。
ちなみに、一般的な賃貸借契約書であれば「使い方に問題がある時には修理費用は入居者の負担」、「経年劣化などによるものはオーナーの負担」となっているはずですから、修理に際しては『故障の原因が何であり、誰の負担であるかの説明をその場で入居者に行える施工業者』を手配するのがベストでしょう。
なお、修理業者の手配を入居者に任せてしまうと「故障原因に関して偽った報告をして来る場合」もありますから、これは避けるべきです。
建物のクレームへの対処
建物に関するクレームについては、
「作業に当たる施工業者を固定しておく」ことが対応のコツ
となります。
一口に建物についてのクレームと言っても、「雨漏り」から「床の腐食」、「配管の詰まり」に「電気系統のトラブル」など、その種類は実に様々です。
そして、こうした不具合の原因を特定するためには天井を剥がしたり、床を開けたりといった大掛かりな「開口作業」が必要となることもありますが、実際に開口してみたら「そこが原因ではなかった」というケースも決して珍しくはありません。
そうとなれば、原因が特定できるまで別の箇所で同じ作業を繰り返すことになりますが、 実はこうした「作業の経験と蓄積」は建物を管理する上で非常に大きな財産となります。
つまり、修繕工事を毎回同じ業者に依頼していると「過去の経験」が蓄積されていき、別の不具合が発生した際にも、
- 天井裏は以前に修繕したから、今回の不具合は壁の内部に原因があるのでは?
- 前回見た床下の状況から考えて、あの配管から漏水しているのでは?
といった推測が成り立ち、不具合発生個所をスムーズに特定できる可能性が飛躍的に向上するという訳なのです。
これに対して、毎回異なる業者で対応を行っていると工事への責任の所在が曖昧になりますし、既に施工済み箇所に必要のない工事をしてしまうといったケースもありますから、これは何としても避けたい事態ですよね。
更に、常に同じ施工業者に作業をさせていれば、入居者と業者間での人間関係も構築されていきますから、よりスムーズな問題解決に結びついていくことになります。
近隣関係のクレームへの対処
さて、大家さんが最も頭を悩ませることとなる近隣関係の問題解決に当たっては、
当事者たちとオーナーができる限り「直接の話し合いを持たないこと」が重要
となります。
たとえ物件オーナーという立場であっても、揉めている人間の間に無防備で乗り込んでいけば「トラブルという火に油を注ぐことになる可能性」も充分にあり得ますし、当事者どちらか一方の肩を持つよう発言をしてしまうと、無用な恨みを買ってしまうことにもなりかねません。
そこで、このような場合には管理を依頼している不動産会社に代理人として仲裁に入ってもらうのがベストでしょう。
なお、管理の形態によっては「クレーム処理は業務対象外」と管理会社に言われてしまうこともあるかもしれませんが、その時は別途料金を払ってでも代理人になってもらうのが良いかと思われます。
特に騒音のクレームなどでは、話し合いの場で「防音工事をしろ」などの要望を突き付けられることもありますから、管理会社という「ワンクッション」を入れて冷静な判断ができる状態にしておきたいところです。
ちなみに、過去記事「賃貸契約書の特約事項の作り方を解説いたします!」の中でご紹介した、「トラブル防止条項」などを契約書の特約に書いておけば、こうした近隣トラブルの話し合いを有利に進めることができるでしょう。
契約に関するクレームへの対処
そして最後に解説するのが、家賃交渉などの契約内容に関するクレームとなります。
なお普通に考えれば契約書で取り決めたことなのだから、苦情が来ても「受け付けない」という対応で良いような気もしますが、収益物件をスムーズに運営していくにはある程度の寛容さも必要です。
但し、一方的に入居者の申し出を受け入れてばかりでは、相手を「調子付かせる」ことにもなりますから、
適度な「飴と鞭」の使い分けを行うことが重要
となるでしょう。
契約期間中の賃料変更などについては、契約締結の段階で「賃料交渉は更新時に行うこと」と書いておき、更新の際に少しずつ賃料を減額して上げれば「空室率を下げる」という意味でも有効な手段となるでしょうし、
「賃料は下げられないが、その分を更新料で調整する」などの微調整も可能となるはずです。(詳細は過去記事「入居者の退去理由から知る、長く住みたくなるお部屋の作り方!」をご参照ください)
また、退去立会いについては別記事「大家さん向け!退去立会いの注意点を解説いたします!」にて、そして敷金の精算に関しては「賃貸敷金トラブルについて解説いたします!」という記事にて詳しく解説しておりますので、是非ご参考になさってください。
スポンサーリンク
賃貸のクレーム対応のコツをご紹介!まとめ
さてここまで、クレームの種類に応じた対処法についてお話ししてまいりました。
なおクレーム対応全般に共通するポイントとしては、「可能な限り入居者との直接の話し合いはしないこと」となるでしょう。
大家さんの立場は、会社で言えば全ての権限を持っている「社長」と同じですから、一度「やる」といってしまうとなかなか引っ込みが付きません。
よってまずは、施工業者や管理会社などの第三者を噛ませることで、考える時間と心の余裕を確保するべきです。
また一方で、クレームを言って来ている人間の本当の目的を見抜くことも大切なスキルとなるでしょう。
単に事態の改善を図りたいのか、お金が目当てなのか、はたまた単にいちゃもんを付けているだけなのかという、相手の意図を正確に把握して、適切な対応を行うことが重要です。
ではこれにて、「賃貸のクレーム対応のコツをご紹介いたします!」の知恵袋を閉じさせていただきたいと思います。