不動産の売買には、プロしか知らない様々な裏技があるものです。
とは言え、魔法のような「凄技」などはそうそうあるはずもなく、その多くは「ちょっぴり取引を円滑にできる」「若干費用を抑えられる」といった程度のものであるのが現実でしょう。
しかしながら、こうした裏技の中には「それを行うだけで通常では考えられない程の効果をもたらす手法」も僅かながら存在しており、その代表格とも言えるのが「中間省略」というテクニックなのです。
そこで本日は、「不動産の中間省略とは?わかりやすく解説いたします!」と題して、この『凄技』についてお話ししたいと思います!

中間省略とは一体?
一般の方はもちろんのこと、不動産業者でも経験が浅い方にとっては、この「中間省略」という言葉は非常に『馴染みの薄いもの』であるはずです。
そしてこの技の概要を簡単にご説明するとすれば、「不動産転売などに中間者(売主から物件を購入し、買主に売却する立場)として介入しながら、登記上は一切その痕跡を残さない手法」というものになります。
ただ、上記の説明だけでは今ひとつ理解が難しいと思いますので、具体的な例を挙げて解説いたしましょう。
例えば「物件を売りたいAさん(売主)」と「物件を買いたいCさん(買主)」がおり、「Bさん」はAとCの間に入って転売で利益を上げたいと考えているとしましょう。
そして通常であれば、物件をA→B→Cという順序で名義変更登記(所有権移転登記)していかなければならないのですが、中間省略を用いることでC名義での登記は行わず、登記上はAB間の直接取引という外観を作り出すことができるのです。
このようなお話をすると「どうしてわざわざ、そのようなことをする必要があるの?」というお声も聞こえて来そうですが、通常通り「A→B→C」と売買された場合、Bさんは不動産取得税と登記に必要な登録免許税の課税を逃れることができませんが、中間省略を用いれば「合法的にこれらの税金を支払わずに済む」という訳なのです。
また、この中間省略においては『本来Bさんが負担するべきAさんに対する売買代金の支払いに、Cさんのお金を利用することができます』から、Bさんは一円の出費もなく転売を完了することが可能となります。
なお、こちらも少々わかり辛いお話であったかと思いますので、具体的な例を挙げておきましょう。
仮に、転売で収益を上げようと考えるBさんが「1億円でアパートを売りたがっているAさん」と知り合い、売却の依頼を受けたとしましょう。
そこで、BさんはCさんという不動産投資家に1億2千万円という価格で物件を紹介して、売買の話をまとめます。
そして実際の取引では、「AさんからBさんが1億円で物件を購入するという作業」と「BさんがCさんに対して1憶2千万円で売却するという作業」を同時に行うことで、実質Bさんは一切自分のお金を支払わずに売買を完了させて、売却益2千万円を手にすることができるという訳です。
ちなみにこの中間省略登記という方法、バブル最盛期には日本中で当たり前に行われていた売買の形態だったのですが、その後の法改正により「中間省略は原則禁止」とされてしまったため、一時期は不動産市場から完全にその姿を消していました。
このようなご説明をすると「中間省略は違法なの?」と思われてしまいそうですが、法改正後、紆余曲折を経て再び合法的に取引を行うことが可能となっているのです。(バブル期よりも少々複雑なやり方にはなってしまいましたが)
旧中間省略登記
ではここで、前項にて触れた「古いタイプの中間省略(旧中間省略)」と「新しい中間省略(新中間省略)」の違いなどについてお話ししてまいりましょう。
これまで「中間省略」という取引の形態について解説をしてまいりましたが、そのネーミングは「中間省略登記」という登記手続きに由来するものです。
その名の通り、この登記では最初の売主(前項の例でいうA)と最後の買主(前項の例でいうC)との間に中間者(前項の例でいうB)が入っていても、中間者の存在を完全に無視した所有権の移転が可能であり、バブル期の「土地転がしブーム」においては頻繁にこの手法が用いられていました。
但し、登記を管轄する法務局としては「実質何人もの不動産購入者(中間者)がいるにも係わらず、登記上でその名が上がらない状態は不健全である」と中間省略登記に不満を示しており、2005年の不動産登記法改正において『所有権移転登記時の売買契約書等(登記原因証明)の提出を義務付ける』こととしたのです。
つまり、この改正によりCの名義で登記を行うには「AC間の売買契約書」が必須となり、Bが介在する余地がなくなってしまったという訳です。
ただ、法改正後も『どうしても中間省略を行いたい』と願う者は数多く、そんな中で生み出されたのが新中間省略登記でした。
2つの新中間省略登記
前項でも解説した通り、法改正により旧中間省略登記は禁止となりましたが、どうしても中間省略を行いたい者たちは「これまでの手法とは全く異なる新たな2つの方法」を編み出すのでした。
そして以前の中間省略登記と区別する目的で、この二つの手法を「新中間省略登記」と称しているのです。
買主の地位の譲渡
まず最初にご紹介するのが「買主の地位の譲渡」と呼ばれる手法となります。
その名が示す通り、こちらは一旦「A(売主)とB(中間者)で不動産売買契約」を締結した後、B(中間者)の「Aに対する買主という立場」をCに譲渡する契約(「地位を譲渡契約」であり売買契約ではない)を結ぶことで、中間省略が可能となるのです。
但し、買主の地位の譲渡が効力を発するには「ABCの三面契約(立場が異なる3者で行う契約)の締結」、あるいは「BからCへの地位譲渡にAが同意すること」が条件となってきます。
そして、この条件が何をもたらすかと言えば、それは「AB間の売買契約の価格がCにバレてしまう」という事態です。
Bの儲けが露呈すれば取引上のトラブルとなることは必至でしょうから、新中間省略登記の中でも「買主の地位の譲渡」が用いられるのはレアなケースとなっているのです。
第三者のためにする契約(直接移転売買方式)
さて、もう一つの手法である「第三者のためにする契約」は民法537条に定められた契約形態となります。
この手法による新中間省略においては「AB間」で不動産売買契約、「BC間」で第三者のためにする契約が締結されることになりますが、AB間の契約は『あくまでもBがCのためにするものである』という建前を作ることで中間省略が可能となる上、この手法であればAB間の契約内容がCに知られることはありません。
なお、「BC間」で締結される第三者のためにする契約は他人物売買契約(売買契約の一種)、または無名契約(売買契約のように民法上具体的な定義のない「名もなき契約」)のどちらに分類されるべきであるかという法学的な議論が存在します。
そして、どちらに分類されるかによって契約の効力に大きな違いが生じますが、こちらについては後程詳しく解説させていただきます。
★当ブログ管理人執筆の電子書籍(kindle)のご紹介!是非ご一読ください!★
 | 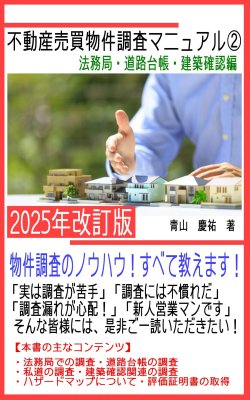 | 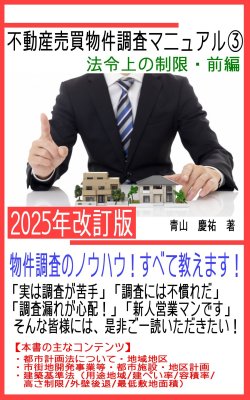 | 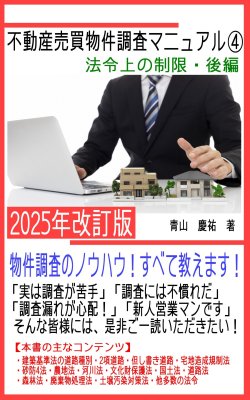 |
中間省略登記のメリット・デメリット
ここまで中間省略登記の海洋について解説してまいりましたが、ここではこの登記を行う上でのメリット・デメリットについてお話していくことにいたしましょう。
中間省略登記の利点
中間省略登記を行うメリットとしては
- 所有権移転登記費用が節約できる
- 中間者は不動産取得税が課税されない
- 中間者は資金なしで転売が行える
以上の点が挙げられるでしょう。
通常の不動産売買においてA→B→Cと所有権が移転した場合、2度の所有権移転登記が必要ですが、中間省略登記を行えば1度の登記で所有権の移転を完了できます。
なお、登記に際しては登録免許税が課税され、所有権移転登記に関しては固定資産税評価額の2%(令和8年3月31日までは1.5%)が税額となりますから、1億円の土地の所有権を移転すれば1度に200万円の登録免許税を支払うことになるため、この登記費用を節約できるのは非常にありがたいことでしょう。
また、不動産を購入した場合には不動産取得税が課税されることとなり、固定資産税評価額の4%が標準税率となりますから(自治体によって税率は変わります)、評価額が1億年の土地なら400万円の税金を節約できることになるのです。
そして中間省略登記の最大のメリットとなるのが、中間者(B)は資金がなくとも転売を行うことができるという点になります。
Aが受け取る売買代金は、Cの購入資金の中らか支払えば済みますから、中間者(B)は1円たりともお金を支払うことなく転売を成功させて、転売益を手にすることができるのです。
中間省略登記の問題点
一方、中間省略登記のデメリットとしては
- 取引完了までに時間を要する
- 中間者によって第三者へ所有権が移転される可能性がある
- 中間者による資金持ち逃げのリスクがある
- 転売価格の露見によりトラブルが発生する場合がある
以上の項目を挙げることができます。
通常の売買であれば、A→B→Cと一段階づづ所有権が移転しますので、物件の引渡しまであまり時間を要しませんが、中間省略の場合には2つの契約をまとめ上げた後に引渡しを行わねばなりませんので、どうしても通常の取引よりも時間が掛かってしまうため、急ぎの売却に際しては対応しきれないケースもあるでしょう。
また、原則としては当事者全員(ABC)が「同じ日」「同じ時間」に銀行へ集合して決済を行う(AとCが会わないよう別室が用意されます)べきですが、何らかの事情で日にちがズレた場合には、中間者(B)がC以外の者へ所有権を移転してしまうという危険性もあります。
更に同日に全員が集まったとしても、別室を行き来している間に中間者(B)が資金を持ち逃げするケースもあるでしょうし、トイレなどでAとCが鉢合わせして互いの売買金額が露呈すれば取引上のトラブルに発展するのは不可避でしょう。
実践!中間省略
ここまでのお話で中間省略の概要はご理解いただけたことと思いますので、本項では具体的に「第三者のためにする契約」を行うためのテクニックをご紹介してまいります。
但し、テクニックとはいっても、「AB間」「BC間」それぞれの契約書に一定の文言を加えて行くのみの作業となりますから、難しいことは何もありません。
A(売主)→B(中間者)間の売買契約書に盛り込む内容
- 本契約が第三者のためにする売買契約であることをA・Bは共に確認した。
- 所有権の移転先はBが指定するものとする。
- 所有権の移転は、Bの指定した者(C)が支払いを終えることを条件に行われる。
- Cが支払いを終えるまで、所有権はAに留保される。
B(中間者)→C(買主)間の契約書に盛り込む内容
- 本契約はBが、現所有者(A)の物件をCに売るという内容であることを確認した。
- Bは、Aとの契約(第三者のためにする契約)により、AからCへ直接所有権を移転する。
- 物件の所有権は、Cがお金を支払い、第三者のためにする契約によりBからAへの支払が完了した後に、Aが所有権移転の意思表示をすることでCに移転される。
売買契約書に記載する内容は、たったこれだけのものとなります。
そして実務上、最も問題となるのは「思いっきり、それぞれの契約書に第三者の存在が記されてしまっている」という点でしょう。
少し考えれば、間に入るBが中間で利益を得ていることは判るはずですから、「これをどのようにA・Cへ上手く説明するか」に全ては掛かっているという訳です。
もちろん方法は人それぞれでしょうが、「Aさんが一度はBさんに売らざるを得ない状況を作る」ことができれば、不可能な流れではないでしょう。
なお「中間省略登記の問題点」の項でもお話しした通り、「決済」は同日・同時刻に一つの銀行の別室で行われることが多いため、トイレなどのタイミングでAとBが鉢合わせするのを何としても阻止しなければなりませんし、決済当日に買主Cが欠席するなどのハプニングも発生する可能性がありますので、色々な意味で非常にリスクの高い取引であることは間違いありません。
契約不適合責任と中間省略登記
では最後に契約不適合責任と中間省略登記の問題についてお話しさせていただきます。
通常、売主が不動産業者である場合には、宅地建物取引業法の定めによって契約不適合責任(建物や土地の欠陥に対して売主が負う)を免責とする旨の特約は無効となってしまいます。
ところが、「買主の地位の譲渡」や「第三者のためにする契約」を用いた中間省略登記においては、不動産業者の契約不適合責任免責が可能となるのです。
その理由としては、中間省略登記におけるB(中間者)→C(買主)の契約は「不動産売買契約」以外の契約となり、宅地建物取引業法の制限が及ばないと解釈されることによります。
なお、第三者のためにする契約について、法学的な観点において他人物売買契約(売買契約の一種)であるか、無名契約(民法上定義のない「名もなき契約」)であるか意見が分かれるところですので、契約不適合責任免責としたい場合には契約書にはっきりと『無名契約である』ことを明記すべきです。
更に、「買主の地位の譲渡」「第三者のためにする契約」どちらの場合も、買主に売主が契約不適合責任を負わない旨、そして隠している物件の不具合や欠陥がないことを充分に説明しておく必要があるでしょう。
スポンサーリンク
中間省略まとめ
ここまで中間省略についてお話してまいりましたが、不動産業者以外の方がこの方法を実践するのは、スキル的にも非常に困難でしょうし、続けて取引を繰り返すことは不動産業の免許も必要となりますので、「あまりお勧めはできない」というのが正直なところです。
一方、不動産業者の方についてはリスクは高いものの、上手く立ち回れば巨額の利益を得ることができる方法ですので、「度胸には自信があるという人」は是非トライしていただければと思います。
なお近年では、この中間省略の方法を用いて荒稼ぎする業者(「第三者のためにする契約(中間省略)」を主に行うため、『三為業者』と呼ばれる)が急増しており、中には非常に悪質なやり方をする者もおりますので、一般の方もこうした業者の餌食にならないように充分な注意を払う必要があるでしょう。
ではこれにて、「不動産の中間省略とは?解りやす解説いたします!」の知恵袋を閉じさせていただきたいと思います。