自分が保有する不動産の価格を知りたい際に、重宝するのが不動産査定というサービスです。
しかしながら、この査定がどのような基準で行われ、依頼する業者によって如何なる違いがあるのかといった点については、「全くわからない」という方が殆どであるはずです。
そこで本日は、「不動産の査定方法について解説いたします!」と題して、物件査定のあれこれについて解説をして行きたいと思います。

不動産鑑定評価との違いは?
一般の方がまず戸惑ってしまうのが、「不動産業者が行う査定」と「不動産鑑定評価」との違いについてなのではないでしょうか。
まず不動産鑑定評価ですが、こちらは不動産鑑定士という国家資格を有する者が行う、不動産の評価方法となります。
物件の評価額を判定するという点では、不動産会社が行う査定報告と変わりなく見えますが、厳しい国家試験をクリアーした者が「原価法」「収益還元法」「取引事例比較法」等の様々な手法を駆使して行う鑑定となりますので、『精度も高い』が『費用も高い代物』となっているのが特徴です。
これに対して不動産業者の査定報告書は、評価方法に特段の決まりがない上、資格も不要、そして殆どの不動産業者が無料で実施しているサービスとなります。
なお、ここまでの説明を聞くと、不動産業者の査定報告書は精度も品質も『不動産鑑定評価に遠く及ばないもの』のように聞こえますが、実際にはそうとばかりも言えないというのが実情です。
実は不動産鑑定士が鑑定評価を行う際には、不動産業者への市場調査が必須となっており、実際に鑑定士が不動産会社へ足を運んで、相場を聞いて回る姿もよく目にいたします。
確かに不動産鑑定評価は非常に信頼の置けるものとなりますが、日々不動産の売買をこなしている不動産屋さんの意見なしには、結論を出すことは困難であるというのが実情なのでしょう。
更に、不動産業者も鑑定士が用いる「原価法」「収益還元法」「取引事例比較法」等について一通りの知識を有しているケースが殆どとなりますから、決して不動産鑑定評価に劣るものではないのです。
このように査定報告は、一般の方が手軽に、そして費用を掛けずに不動産の価格を知ることができる「非常に便利なサービス」となっているのですが、ここで気になるのが一体どんな方法で査定額を導き出しているかという点ですよね。
そこで以下では、不動産査定の概要や査定報告書の作成方法、査定に当たってのポイントや注意点等を見ていくことにいたしましょう。
不動産査定の種類について
さて、一口に不動産の査定と言っても実はいくつかの種類がありますので、以下で解説してまいりましょう。
簡易査定
別名「机上査定」とも呼ばれる、最も簡易的な査定の方法となります。
その別名の通り、原則として不動産業者が現地に出向くことなく「一般的な相場観」を基に価格を提示する査定方法です。
よって、その精度はあまり高くないと言わざるを得ませんが、実際に売却依頼を受ける場合には、次項で解説する訪問査定を行った上での価格を提示しますので、売却希望者が不利益を被ることはまず無いはずです。
なお、この簡易査定の最大の魅力は短時間で、売却物件の周辺相場を一気に把握できるという点でしょう。
通常、簡易査定の結果が出るまでの期間は3~5日程度となりますし、不動産業者と直接対面することなくある程度の相場を知ることができるのは非常にありがたいはずです。
ちなみに、近年流行りの「ネット一括査定」は殆どがこの簡易査定の結果を送って来るサービスとなります。
訪問査定
簡易査定の次のフェーズとも言えるのが、こちらの訪問査定となります。
この査定では営業マンが直接売却希望者の元を訪ね、対象物件の調査を行った上で査定価格を算出するのが通常です。
また、訪問査定においては行政が定める建築制限や近隣との権利関係についても調べることになりますので、結果が出るのに最短でも1週間以上の期間を要するのが通常となります。
なお、物件が接する道路の方位や土地の形状、建物の状態から周辺の住環境と言ったあらゆる要素を検討して、総合的な査定金額を算出することになりますので、その精度は簡易査定に比べて非常に高いものと言えるでしょう。
ただそれだけに、査定を行う者のスキルがダイレクトに反映されてしまう点には注意が必要となります。
不動産査定価格を算出する3つの方法
不動産査定の種類についてご理解いただけたところで、本項では査定を行うに当たって用いられる3つの不動産価格の算出手法について解説していきたいと思います。
取引事例比較法
その名の通り、近隣の取引事例を基に不動産の査定価格を算出する方法となります。
不動産業者はレインズや業者版アットホーム等のツールにて、全国の取引事例の閲覧が可能ですし、会社によってはこれまで蓄積してきた取引の記録をデータベース化しているところもあるでしょう。
こうした情報の中から査定対象物件の条件に近いものをピックアップし、これらを比較することで査定価格を算出する方法となります。
但し、不動産の取引において全く同じ条件の物件など存在しませんので、
- 査定物件は東道路だが、取引事例は南道路なので「200万円減額」
- 査定物件は間口7mだが、取引事例は間口4.5mなので「300万円増額」
といった具合に、微調整を行いながら査定価格を算出していくことになるでしょう。
原価法
原価法は主に戸建の査定において用いられる手法であり、現在建てられている建物を再建築した場合の費用を求めて、築年数に応じて減額することによって「建物の査定価格を求める方法」となります。
なお、具体的な算出方法としては
- 現在の建物を再建築する費用/2100万円
- 建物の耐用年数/30年
- 築年数/20年
- 再建築費用2100万円 × (築年数20年/耐用年数30年) = 建物償却価格1400万円
- 再建築費用2100万円 - 建物償却価格1400万円 = 建物残存価格700万円
以上のような計算を行い、中古戸建ての建物代を算出することになるのです。
そして、土地については前項で解説した取引事例比較法による算出を行い、建物については原価法を用いて査定額を導き出すことで中古戸建ての査定が完了することになります。
ちなみに、ここで問題となるが「建物再建築費用」「建物耐用年数」を如何に導き出すかという点になるでしょう。
まず再建築費用については、「同じグレードの住宅を今建てたら、いくら掛かるか」を算出するのが原則となりますが、注文住宅の場合などは計算が非常に困難となるはずです。
また、「売主の趣向が色濃く反映された注文住宅の価格を、売却に向けての査定価格にそのまま反映させて良いのか」という点も大いに疑問が残りますので、状況によっては注文住宅についても一般的な住宅の再建築価格で計算を行うケースも少なくありません。
一方、建物耐用年数については減価償却資産の法定対応年数(例・木造住宅耐用年数33年 など)をそのまま用いるのが一般的ですが、実際の取引事例と整合性がとれないケースも多いため、不動産業者が独自の基準(例・木造住宅耐用年数35年 など)で査定価格を算出する場合も珍しくありません。
収益還元法
収益還元法は主に収益物件の査定を行う際に用いられる手法となります。
なお、収益還元法には「直接還元法」と「DCF法」の2種類がありますので以下で簡単に解説してまいりましょう。
直接還元法
直接還元法は「査定対象の物件が1年間で稼ぎ出す利益」を「還元利回り」で割ることで査定価格を算出する手法となります。
- 直接還元法の計算式/1年間の純利益 ÷ 還元利回り = 査定価格
- 査定対象物件の家賃収入/月額20万円、年額240万円
- 物件運営に必要な経費/月額5万円、年額60万円
- 還元利回り/8%
- 年間家賃収入240万円 - 年間必要経費60万円 = 1年間の純利益180万円
- 1年間の純利益180万円 ÷ 還元利回り8% = 査定価格2250万円
さて、この直接還元法での査定を行う際の最大のポイントは「還元利回り」の算出方法となります。
なお、還元利回りは同じエリアの近傍同種の利回りを基に設定されることになりますから、この計算を行う場合には取引事例比較法の手法を活用することになるでしょう。
DCF法
DCF法は収益物件の「保有年数」と「物件を保有するに従って増加していく割引率」から、査定価格を算出する方法となります。
- 査定対象物件の家賃収入/月額20万円、年額240万円
- 物件運営に必要な経費/月額5万円、年額60万円
- 割引率/5%
- 物件の保有期間/5年
- 5年目の売却予想価格/2000万円
- 1年目の純利益180万円 ÷ (1+0.05【5%】)= 171万円(1年目の利益計算)
- 2年目の純利益171万円 ÷ (1+0.05【5%】)= 163万円(2年目の利益計算)
- 3年目の純利益163万円 ÷ (1+0.05【5%】)= 155万円(3年目の利益計算)
- 4年目の純利益155万円 ÷ (1+0.05【5%】)= 148万円(4年目の利益計算)
- 5年目の純利益148万円 ÷ (1+0.05【5%】)= 141万円(5年目の利益計算)
- 5年目の売却予想価格1567万円(2000万円÷1.05【5乗】)+778万円(5年分の利益計算合計)=査定価格2345万円
DCF法を和訳すると「キャッシュフロー割引法」という意味になり、物件が1年間に生み出す利益から、物件固有のリスクを「割引率」として差し引いて、査定価格を算出する手法となります。
なお、この手法の最大のポイントは割引率を如何に正確に設定するかという点になりますが、その計算方法は非常に複雑であるため担当業者のスキルが大いに問われることになるでしょう。
★当ブログ管理人執筆の電子書籍(kindle)のご紹介!是非ご一読ください!★
 | 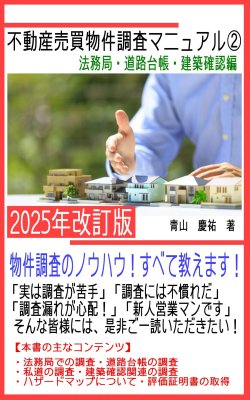 | 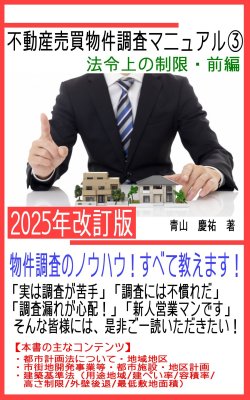 | 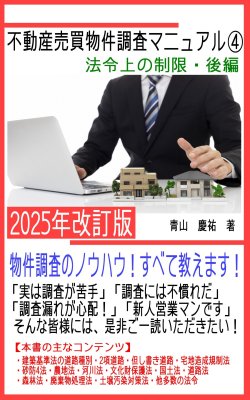 |
訪問査定を受ける場合のポイントや注意点
ここまでの解説にて不動産査定の概要についてはご理解いただけたことと思いますので、ここからは実際に訪問査定を受ける際の注意点などについてお話ししていきたいと思います。
既にご説明したように訪問査定の段階ともなれば、本格的な物件調査をした上で査定価格を算出することになりますので、これを請け負う不動産会社の労力も「それなりのもの」となってきます。
そして不動産の査定は原則無料ではありますが、「全く売却の意思がない」といった場合には依頼を行うべきではないでしょう。
また、査定を受けるに当たっては物件に関する資料をできる限り集めておくのがベストです。
なお、必要書類に関しては
- 登記識別情報(権利証)
- 身分証明書
- 測量図
- 筆界確認書
- 建築確認関係書類(建物がある場合)
- 建物修繕工事の記録(建物がある場合)
- 建物耐震診断結果(建物がある場合)
- 建物状況調査【インスペクション】の報告書(建物がある場合)
- 固定資産税等通知書
- 近隣住民や私道の権利関係者と取り交した書面(覚書等)
などが主なものとなるでしょう。
もちろん、これら全ての書類を集めておく必要はありませんが、査定に際して提示できる資料が多ければ多い程に、査定の精度は向上することになります。
ちなみに、こうした資料以上に重要となるのが「査定担当者のヒヤリングに対して正直に回答を行うこと」です。
雨漏りや建物の傾きなどの物件の欠陥はできれば隠しておきたいところですし、近隣住民とのトラブルなどもわざわざ第三者に伝えたい話ではありませんが、こうした事実を隠して売却を行えば、必ず大きな問題へと発展しますので、査定を受ける際には話辛い事実も包み隠さず担当者に伝えるようにしましょう。
査定報告書作成のポイント
さてここまで、査定を依頼するユーザーの立場で解説を行ってまいりましたが、ここからは査定報告書を作成する不動産業者の目線でお話を進めていくことといたします。
不動産業者がどのように査定業務を進めているかを理解することは、依頼を行う側にとっても大きなメリットをもたらすはずですから、一般の方も是非最後までお目通しいただければ幸いです。
客観的な根拠を示しながら、説得力のある報告書を作る
不動産の営業マンにとって「相場観を養うこと」は非常に重要な課題となりますが、どんなに的確な相場観を有していても、それをお客様に伝え、理解していただかなければ、査定価格に納得していただくことはできません。
よって、提示する査定価格が適正なものであることを証明するためにも、具体的な取引事例等をふんだんに折り込んだ報告書の作成を心掛けるべきでしょう。
また取引事例も単なるデータの羅列とならないよう、事例同士の比較等を行いながら、論理的で起承転結が明確な報告書が望ましいと思われます。
シンプル且つ解りやすく
前項で査定報告書の説得力についてお話しいたしましたが、よく目にするのが「文章が長いばかりで解り辛い報告書」です。
文章のボリュームがあると「一生懸命感」は伝わりますし、丁寧に説明しようとすればどうしても長文になってしまうものですが、最後まで飽きずに読めるシンプルさも重要でしょう。
よって、グラフや地図を用いるなどの工夫を施し、解りやすさ重視の報告書を目指すべきです。
誠実な査定を行う
査定報告書作成において、一番問題なのがこちらのポイントです。
お客様は査定報告の作成を他社にも依頼している可能性がありますから、売却が前提の場合などは「少しでも高額な査定額を提示したい」という気持ちになって来ます。
事実、大手不動産仲介業者の中にも、驚く程の高額査定を行って売却依頼を獲得し、後々ゆるゆると値段を下げさせるという手法を使っている会社もあるようです。
しかしながら、現在ではネット検索などを駆使すれば、一般の方でもある程度の相場を調べることができますから、こうした手法もやり辛くなりつつありますし、何よりお客様が「故意に高額査定が行われている事実」を知れば、一気に信頼を失うことにもなりかねません。
お客様の期待を裏切らない誠実な仕事を心掛けたいものです。
実際の作成例
ここまで、査定報告書作成のポイントについてお話をしてまいりましたが、本項では具体的な作成手順を見ていきたいと思います。
なお、査定報告書の作り方や構成は人それぞれかとは思いますので、「こういう作り方をする奴もいるのか・・・」という参考程度にご覧いただければ幸いです。
なお、査定対象は築5年の木造中古戸建て、北側道路、土地の大きさは30坪、建物の延べ床面積は28坪という前提とさせていただきます。
路線価・地価公示で物件周辺の土地価格を算出する
査定報告書の作成においては、まず最初に路線価と地価公示の価格を提示して、物件周辺の相場を依頼者に把握していただくという手法が一般的です。
路線価・地価公示共にインターネット等で手軽に情報が入手できますし、どちらも行政が提示している評価額ですから、依頼者への説得力は抜群と言えるでしょう。
なお、路線価は実勢価格(実際に取引されている価格)の70%~60%程度の価格、地価公示はの100%~90%程度であることを説明した上、
実際の取引事例を提示して、先に述べた「路線価や地価公示価格の減額のパーセンテージが妥当である」ことを示せれば完璧かと思います。
物件周辺の取引事例を紹介
不動産業者間の物件情報共有媒体であるレインズやアットホームなどでは、成約事例の情報を入手することができますので、これらの資料を提示しつつ、取引事例の紹介を行います。
但し、これらの媒体に全ての取引事例が掲載されている訳ではありませんので、自分自身が日々の仕事をする中で入手した近傍同種物件の成約価格や、取引のある不動産業者さんから仕入れた情報等を織り込めれば、他社が行う査定報告に差を付けられるのではないでしょうか。
なお、地域によっては物件周辺に全く成約事例が登録されていない場合も多々あります。
こうしたケースでは、「現在販売中の物件」を事例として取り上げるしかありませんが、売主が個人である場合には、売主の希望やローン残額の問題で相場を逸脱した価格で売りに出ていることも少なくありません。
よって「現在販売中であり、且つ売主が一般の方である中古物件」は採用せず、建物価格が算出しやすく、地域の相場が反映されやすい新築の建売物件を事例として取り上げるべきでしょう。(建売物件は分譲会社が綿密な市場調査を行った上で値付けをしているため、相場から逸脱した価格が付けられることは殆どありません)
情報の整理
そして、本項で扱う「情報の整理」が査定報告書の中で一番の「肝」となる部分です。
ここまで「物件周辺の取引事例」等を示して来ましたが、不動産の価格は立地や周辺環境、そして建物の築年数などによって大きな差が出るものですし、全く同じ条件の取引事例など存在する訳もありません。
そこで、個々の事例の条件を比較し、物件の価格に影響を及ぼす要素について情報の整理を行う必要が出てきます。
例えば実際の査定対象物件が北側道路に面しているのに、取引事例では南側道路の物件しか存在しない場合には、「北道路と南道路でどれくらい価格に差が出るのか」という点を説明しなければなりません。(取引事例比較法)
また、査定対象物件が築5年であるにも係わらず、取引事例は新築のものしか見当たらない場合には、「5年でどれだけ建物の価格が償却するか」という検討も必要になるでしょう。(原価法)
※築年数の異なる建物同士の価値を比較する場合には、一般的な木造住宅の新築建築単価(坪67万円程度)に延べ床面積を掛け、新築価格を割り出した後、この建物価格が30~35年で償却するという考えの下で検討を行う方法が一般的です。
※この解説の前提となる物件は「築5年・床面積28坪」ですから、『床面積28坪×新築建物単価67万円=新築時の建物価格1876万円』という計算となり、30年で建物価値が0円になると考えれば「1年ごとに約62.5万円が償却(1876万円÷30年=約62.5万円)」し、これが5年で約62.5万円×5年=約312万円分の建物価値が失われますので、現在の建物価値は1876万円(新築時の価値)-約312万円(5年の償却分)=1564万円(現在の建物価値)という計算が成り立ちます。
更に査定対象の土地面積は30坪ですが、事例が15坪などの小さい土地の場合には「事例よりも低めの坪単価での査定となる」はずですし、逆に50坪など大きい土地が比較対象ならば「査定価格の単価は高めの査定となる」のが通常です。(取引事例比較法)
※土地の坪単価は「面積が広くなればなるほど下落する傾向」にありますが、この価格のメカニズムについての詳細は別記事「マイホームの土地の広さや面積について解説いたします!」をご参照ください。
そして、こうした物件ごとの条件の差が『査定価格に如何なる影響を及ぼすか』について、説得力のある説明をするのが「情報の整理」における最重要なポイントとなりますから、正に不動産業者の腕の見せ所ともなっているのです。
ちなみに私が情報の整理において用いているのが、「土地の条件による価格差早見表」というもので、
- 北側道路の物件(南道路に比べて) -10%
- 角地の物件 +10%
- 前面道路の幅員が4m以下の物件 -10%
- 専用通路のある物件(旗竿地) -20%
というように、プラスになるポイントと、マイナスになるポイントを一覧表にした上、項目ごとに価格に及ぶ影響(減額・増額の%)が一目で判る資料となっています。
もちろん、減額と増額のパーセンテージには根拠が必要となりますから、一覧表作りにはかなり手間と時間が掛かりますが、一度良いものを作ると査定報告書の作成が非常に楽になるかと思いますので、是非ご参考になさってください。
査定価格算出
さて「情報の整理」において、事例として取り上げた物件と査定対象の間に『如何なる条件の差があり、どの程度の価格の違いが生じるか』が明らかになっているはずですから、いよいよ締め括りとして査定価格を提示する段階となります。
なお、ここまで展開して来た説明の内容と査定価格に矛盾する点があれば、折角苦労して作成した報告書が台無しになってしまいますので、全体をしっかりと見直して問題点がないかをチェックするようにしましょう。
また、査定報告書の末尾には「本報告書はあくまで実勢価格を算出したものであり、不動産鑑定評価とは異なるものであること」、そして「市況の変化によって今後、価格が変動する可能性がある」旨の注意書きは必ず加えておくべきです。
スポンサーリンク
不動産の査定方法まとめ
さてここまで、不動産査定の概要や査定報告書の作成方法や注意点などについて解説をしてまいりました。
物件の査定は、お客様との距離を縮める大切な業務となりますから、自分にぴったりの方法を編み出し、今後のお仕事に繋げて行きたいところですよね。
また一般の方についても、不動産屋さんがどんな方法で査定価格を弾き出しているかが解れば、意図的に行われた高額査定を見抜くことができるでしょうし、
インターネット等の物件情報を元に、ご自身で自宅の査定などにチャレンジしてみるのも面白いかもしれません。
では、これにて不動産査定方法の知恵袋を閉じさせていただきたいと思います!