不動産の賃貸仲介には、大きく分けて2つの取引対象物件があると言われており、その2つとは「居住用物件」と「事業用物件」ということになります。
さて、このようなお話をすると、「同じ賃貸なのに、そんなに違いがあるの?」というお声も聞えて来そうですが、その違いは『かなりのもの』と言えるしょう。
また不動産屋さんの中には、「正直、事業用は取り扱いたくない」という方もおられる程ですから、事業用物件の取引はなかなかに手間の掛かる仕事であることがお分かりいただけるはずです。
そこで本日は、そんな事業用賃貸の契約書作成、並びに特約の作り方についてお話ししてみようと思います。
なお本記事は、これまでに書いた「個人向け賃貸借契約書の作り方」、「法人向け居住用賃貸契約書の作り方」の記事と比較しながらお読みいただくとより理解が深まるかと思いますので、こちらも是非ご参考になさってください。
では、賃貸事業用契約書の書き方と特約についての知恵袋を開いてみましょう。

事業用契約の注意点
法人向け居住用賃貸契約の記事にて、「取引の相手が法人となると、それだけでも契約のハードルはかなり高いものになる」と申し上げましたが、事業用物件の場合、契約の相手方はその多くが法人となります。
ましてや、取引対象は社員寮などの居住用物件ではなく、店舗や事務所となりますから、その難易度は更に上昇することになるのです。
では、「一体どこがそんなに難しいのか?」という点からご説明を始めましょう。
まず最も厄介なのが「契約対象の物件において借主が商売を行う」という点です。
「何を当たり前のことを」と言われてしまいそうですが、その差は非常に大きいものがあります。
例えば、雨漏りなどが発生して、物件の利用ができなくなったとしましょう。
居住用であれば一時的にホテルなどに移り住んでもらい、そのホテル代を補てんすればことは済みますが、相手が物件で商売をしているとなれば、そう単純にはに事が運びせん。
その上、「もし工事のために休業している期間がなければ、●●●万円の売り上げがあったはずだ!」など相手が言い出したなら、これは最早「悲劇」としか言いようがありませんよね。
そして現実に、こうしたトラブルが素で訴訟に発展するケースや、高額の営業補償料を支払わされた事例が数多く発生しているのです。
また営業活動する以上、巻き起こるトラブルの数も、寝に帰るだけの自宅とは段違いなものとなります。
作業所・工場などであれば、音や振動による近隣問題が発生する可能性がありますし、飲食店なら害虫や利用客によるトラブル、そして火災のリスクも急上昇することになるでしょう。
更には、物件に出入りする社員や店員の入れ替えも激しいでしょうから、問題が発生した際の責任の所在も不明確になりがちです。
事業用契約書に加えるべき条文と特約
よって、こうした事業用物件ならではの問題を「如何に上手くカバーできるか」が、賃貸借契約書や特約条項を作る上での最重要課題となる訳です。
では具体的に、条文や特約の内容を見て行くことにしましょう。
物件の使用目的を限定する特約
契約書の作成において、まず行うべきは「物件の使用目的をしっかり取り決めておくこと」です。
そこで、「借主は本物件を●●の目的で賃貸するものとします」などの文言で使用目的に縛りを入れましょう。
事業用契約の場合には事業内容の転換などに伴い、事務所を店舗に変更したり、販売所に変更したいなどの希望が出されることも少なくありません。
もしここで契約書に、しっかりと用途の限定していなければ「気が付いたら全く別の商売を行っていた」という事態も起こりかねません。
よって●●の部分には、「保険業の事務所」「和風居酒屋」「建築資材の作業場」など、極力限定した用途を定めておくことが肝心です。
こうすることにより、物件の利用方法を変更する場合にはオーナーへの申し出が必須となりますから、事業内容の把握も容易になるでしょう。
緊急時の連絡先等を契約書に盛り込む
事業用物件の契約における借主は法人となるケースが多いことは既にお話ししましたが、緊急事態が発生した場合に「一体どこの部署に連絡を入れれば良いのだろうか」と悩んでしまうようではお話になりません。
そこで事業用物件の契約書においては、借主となる法人、そして担当部署の連絡先のみならず、物件を直接管理する立場にある支店長や所長などの責任者の氏名と連絡先(可能であれば携帯番号)を緊急時の連絡先として記載しておくべきでしょう。
また、人事異動などで責任者が変更になった場合には、速やかに貸主に対して新たな責任者の氏名等を通知する義務を借主へ課することも重要です。
★当ブログ管理人執筆の電子書籍(kindle)のご紹介!是非ご一読ください!★
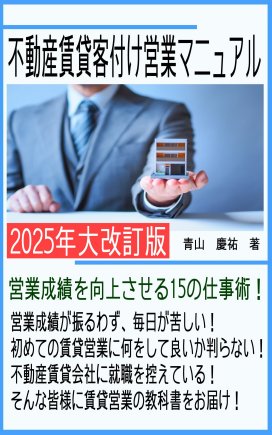 | 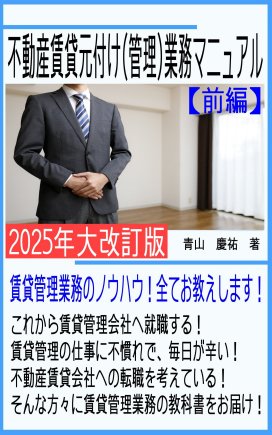 | 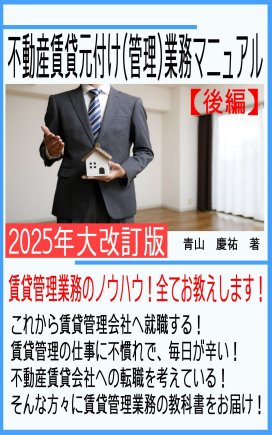 |
保証金の償却についての定め
事業用物件の契約においては、借主が差し入れた保証金が一定の割合で償却されるケースも珍しくありません。
- 契約更新ごとに償却
- 契約終了時に償却
- 1年ごとに一定割合で償却
また、償却が行われた場合には「既定の額まで保証金の積み増し」を求められる場合も少なくないでしょう。
こうした慣習が存在する背景には「(居住用契約と比較した場合に)事業用契約は貸主にとってリスクが高い」という事情があるのですが、保証金償却のような特別ルールを定めるのであれば、契約書にはしっかりとその旨を明記しておく必要があります。
なお関東の場合、償却が行われるのは主に保証金であり、敷金の場合にはこうしたルールを設定しないケースが殆どですが、この点については地域性にも大きく左右されるますのでご注意ください。
ちなみに、敷金と保証金は呼び名が異なるだけで「同じ性質のもの」と考えて差し支えありません。
有益費償還請求権と造作買取請求権
事業用賃貸借契約が終了した際に問題となりやすいのが、有益費償還請求権と造作買取請求権についてとなります。
有益費償還請求権は民法に定められたルールであり、床など建物の一体化した部分について「借主が物件の付加価値を向上させる行為を行った場合(フローリングを新品に交換する等)」には、それによって生じた利益の償還を貸主へ請求できるというものです。
一方、造作買取請求権は建物と分離可能な造作(ガスコンロ等)について、貸主の承諾を得て借主が設置を行い、これによって物件の価値が向上した際には、造作の買取を貸主に請求できるというルールになります。(借地借家法)
なお、この二つの権利は契約書上に請求禁止の特約を組み込むことで、借主の請求権を排除できますから、事業用賃貸借契約書の作成に当たっては条文に加えておくべきでしょう。
造作の取り扱いについて
前項にて造作のお話をいたしましたが、事業用物件の賃貸には造作が付き物であり、物件を借りた際に前賃借人が残していった造作が設置されているケースも珍しくありません。
こうした造作については、前賃借人が所有権を放棄した残置物として扱うものとし、その性能や故障等について貸主が責任を負わない旨を契約書に謳っておくのが無難でしょう。
また、借主が新たに造作を行う場合には、貸主の許可を得た上でこれを行うものとし、退去時にはそれを借主が撤去する取り決めを加えておくのが得策です。
なお、造作の中には「撤去するには惜しいもの」もあるでしょうから、『但し、貸主が許可する場合には、造作を撤去せずに残置することができるものとします』という文言を入れておくのも良いでしょう。
内装工事や看板の設置に関する特約
契約対象の物件を店舗などとして利用する場合、借主による大規模な内装工事や建物への看板設置は充分に想定できる工事内容となるはずです。
但し、どんな工事や看板もOKにしてしまうと後々トラブルとなることも多いので「内装工事や看板を設置する場合には、事前に施工内容を貸主に申し出て、承諾を得るものとします」という特約を加えるようにしましょう。
また将来的に、借主が退去をすることとなった際に「内装等をどのように処理するか(スケルトン渡しにする等)」についても取り決めを行っておくべきです。
事業用契約の連帯保証人について
2020年の民法改正により、賃貸借契約において連帯保証人を擁立する際には「保証に対する極度額」を定める必要があり、これに違反した場合は保証契約自体が無効となるのがルールです。
しかしながら、賃貸事業用契約においてはこの極度額に加えて、
- 借主の事業の収支の状況
- 借主の債務の状況
- 当該契約に関して担保提供を行う場合にはその内容
以上の点に対して、借主は連帯保証人へ情報提供を行う必要があり、これが行われない場合には保証契約が無効と判断されます。
よって、賃貸事業用契約にて連帯保証人を擁立する場合には、この情報提供が確実に行われたことを確認する条項を契約書に加えておく必要があるでしょう。
営業補償に関する特約
前述の「事業用契約の注意点」でも申し上げた通り、事業用契約の最大の問題点は営業補償に関するものとなります。
よって「賃借人は、建物に損害が発生した場合や、メンテナンスに際し、営業が行えない場合にも、貸主に対して営業補償費用などを請求することはできないものとします」という条項を特約として加えておくべきでしょう。
但し、この文言を入れたからといって、完全に営業補償料の支払いを拒否することは法解釈上、困難であると思われます。
それでも契約書に謳っておくことにより、営業補償の請求を抑止したり、補償額の交渉において有利に活用できますから、記しておいて損は無い特約でしょう。
防火管理者・消防計画に関する特約
店舗などの事業用物件の場合、安全性確保の観点から消防法による法的規制も強くなるのが通常です。
具体的には消防署の査察などが頻繁に入ることとなる(業種にもよります)のですが、場合によっては「防火管理者の選任」や「消防計画の提出」を求められることもあります。
なお、こうした状況において、借主から「消防についてはオーナーさん側で対応して欲しい」との要望が出される可能性もありますので、「関係官庁より防火管理者の選任や・消防計画の提出を求められた際には、借主の責任と負担にてこれに対応するものとします」という文言を入れて置きたいところでしょう。
スポンサーリンク
事業用契約まとめ
さて以上の内容が、事業用契約にて組み込んでおくべき条項と特約事項の例となります。
なお冒頭でも申し上げましたが、事業用物件の場合には契約の相手方が『法人』となることも少なくありませんので、過去記事「賃貸法人契約書と特約の作り方をご紹介!」にてご紹介いたしました
- 解除条項に付加するべき特約/破産手続き開始等を解約事由とする旨の条項
- 借家人賠償保険に関する特約/保険内容を開示する旨の条項
- 重要事項説明・契約書の説明義務特約/従業員等へ契約書や重要事項の周知を行う旨の条項
等々の法人用特約も不可欠となるでしょう。
ここまでご説明して来たように、不動産屋さんにとっては事業用の賃貸借契約はなかなか荷の重いものとなりますが、仲介手数料、広告宣伝費共に高額となるチャンス物件も多いはずですから、トラブルを避けつつ、スムーズな成約を目指したいところですよね。
ではこれにて、賃貸事業用契約書の書き方と特約についての知恵袋を閉じさせていただきたいと思います。