これまで本ブログでは「土石流」や「がけ崩れ」と言った土砂災害に関する記事をお届けしてまいりましたが、実はもう一つ『地すべり』という災害があるのをご存じでしたでしょうか。
なお、この『地すべり』というワードに「あまり聞き覚えがない」という方も多いかもしれませんが、一度この災害が発生すれば広範囲におよび甚大な被害が発生することになりますので、マイホームの購入などにおいては十分に注意すべきものとなるのです。
そこで本日は「地すべり等防止法とは?わかりやすく解説いたします!」と題して、『地すべり防止区域』や『ぼた山崩壊防止区域』の行為制限、不動産取引における影響などについてお話ししていきたいと思います。

地すべり等防止法の概要
ではまず、我が国における「地すべり対策」の法律である『地すべり等防止法』の概要についての解説からお話をスタートさせていきましょう。
地すべり等防止法は1958年(昭和33年)に施行された地すべり及びぼた山の崩壊を防止するための法律となります。
なお、「地すべり」とは
雨水や地下水の影響により『地盤が滑り落ちる現象』を指し、地面に染み込んだ水が地底に染み込む過程において「水を通さない地層」に蓄積し、その層よりも上部に位置する地層をゆっくりと押し流していくことで発生する
とされています。
「ゆっくりと押し流す」という表現からはあまり危険性が感じられないかもしれませんが、他の土砂災害に比べて非常に広い範囲に被害が及ぶことに加え、大規模な地形の変化により『土石流』や『がけ崩れ』と言った他の土砂災害を引き起こす可能性もある非常に危険な現象となります。
そして、こうした災害被害を防止するために地すべり等防止法においては、
- 国土交通大臣
- 農林水産大臣
の双方が危険個所について
- 地すべり防止区域
- ぼた山崩壊防止区域
というエリア指定を行い、地すべり等の被害の防止、または軽減を図るため一定の行為について制限を行っているのです。
なお、エリア指定を行うのは国土交通大臣、農林水産大臣となりますが、地すべり防止区域等の管理を行うのは自治体となりますので、制限対象となっている行為を行う際には都道府県知事の許可が必要となります。
※地すべり防止区域等の中には国が直接管理を行っている場所もありますので、このケースにおいては農林水産省等の担当部署が制限行為に対する許可等を行うことになります。
ちなみに「ぼた山崩壊防止区域」の『ぼた山』という言葉は聞き慣れないかと思いますが、これは
石炭や亜鉛を採掘した際に出た岩石や残土を積み上げた人口の山や丘
を指す言葉です。
こうした「ぼた山」は自然にできた山と比較して崩壊しやすい箇所が多いため、地すべり等防止法において危険区域としての取り扱いのルールが定められることになりました。
スポンサーリンク
「地すべり防止区域」と「ぼた山崩壊防止区域」について
前項にて地すべり等防止法の概要についてはご理解いただけたことと思いますので、本項では「地すべり防止区域」と「ぼた山崩壊防止区域」の具体的な制限内容について解説してまいりましょう。
なお、以前にお届けした砂防法の記事において、土石流を防ぐために指定される『砂防指定地の行為制限は自治体ごとにルールが異なる旨(条例でルールが定められる旨)』をお話しいたしましたが、地すべり防止区域等の行為制限については「全国同一」となっている点にご注意ください。
さて、地すべり防止区域に関しては
地すべり防止区域で制限される行為
- 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させる行為
- 地下水の排水施設の機能を阻害する行為、その他地下水の排除を阻害する行為
- 地表水の放流、または停滞させる行為、その他地表水のしん透を助長する行為
- のり切または切土
- 地すべり防止施設以外の施設または工作物の設置
- 地すべりの防止を阻害し、または地すべりを助長し、若しくは誘発する行為
引用元: 地すべり等防止法 第十八条
以上の行為について都道府県知事の許可が必要となります。
一方、ぼた山崩壊防止区域については
ぼた山崩壊防止区域で制限される行為
- 立木竹の伐採または樹根の採取
- 木竹の滑下または地引による搬出
- のり切または切土
- 土石の採取または集積
- その他のぼた山の崩壊の防止を阻害し、またはぼた山の崩壊を助長し、若しくは誘発する行為
引用元: 地すべり等防止法 第四十二条
以上が制限され、これを行うには都道府県知事の許可が必要です。
なお、「地すべり防止区域」、「ぼた山崩壊防止区域」のいずれにおいても、
掘削や工作物の設置は制限されているため『マイホームの建築等には必ず許可が必要』
となります。
また、災害発生リスクの高い地域となりますので許可制と言っても、そう簡単に建築等が認められることはないはずです。
地すべり等防止法と不動産取引
このように地すべり等防止法においては危険区域における行為制限が定められているため、
取引対象が「地すべり防止区域」「ぼた山崩壊防止区域」に指定されている場合には、『売買契約締結前の重要事項説明にてその旨を必ず告知する必要』
があります。
なお、「地すべり防止区域」または「ぼた山崩壊防止区域」に指定されているか否かの調査は、各都道府県の担当部署にて調べることができますが、国土交通省や農林水産省が直接管理を行う防止区域については各省庁へ問い合わせを行う必要があるでしょう。
また前項でも解説した通り、これらの防止区域での建築行為は原則として都道府県知事の許可が必要となる上、簡単に許可を得ることができないのが実情ですから、物件としての価値は非常に低いものなってしまうのが現実です。
ちなみに、「地すべり防止区域」においては
- 擁壁工事(コンクリートの土留めを設置する工事)
- アンカー工事(斜面をコンクリートで抑える工事)
- 護岸工事(岸辺をコンクリートで固め川の浸食を防ぐ工事)
- 杭工事(地底に杭を打ち込み地すべりを抑制する工事)
などが行われることになりますので、物件の下見に訪れた際にこうした施設を見掛けた場合には注意が必要です。(指定区域である旨の標識も設置されています)
一方、「ぼた山崩壊防止区域」についても現地に指定区域である標識が設置されていますが、『ぼた山』は通常の山よりも整った円錐形をしているのが特徴となります。
よって、周囲を見渡して「人工物と思われる整った形状で、峰が一つしかない山」を発見した場合には、十分な調査を行う必要があるでしょう。
地すべり危険箇所
さて、不動産取引に向けて役所調査などを行っていると「地すべり防止区域」と似た名称の『地すべり危険箇所』という地域を目にすることがあります。
そして、この『地すべり危険箇所』は地すべり等防止法とは全く関連のないものとなっており、過去の履歴や地形の特徴などから、土砂災害が発生するリスクが高いと自治体などが判断した場合に指定されるエリアです。
なお、地すべり危険箇所には
法的な根拠はありませんので建築等の行為が制限されることはなく、単に「土砂災害のリスクがある地域」
というものになります。
★当ブログ管理人執筆の電子書籍(kindle)のご紹介!是非ご一読ください!★
 |  |  | 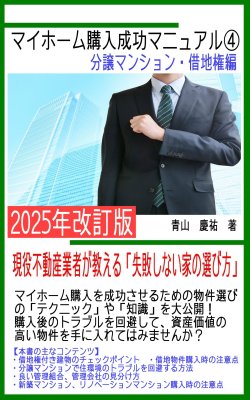 |
地すべり等防止法とは?わかりやすく解説まとめ
さてここまで、「地すべり等防止法」をテーマに解説を行ってまいりました。
これまでの記事をお読みくだされば、「地すべり」という聞き慣れない土砂災害が、私たちの生活や不動産取引に如何に係ってくるかをご理解いただけたはずです。
そして、同じ土砂災害関連の法律である「急傾斜地法(がけ崩れを防止する法律)」および「砂防法(土石流を防止する法律)」と、今回解説した『地すべり等防止法(地すべりを防止する法律)』を3つ合わせて、砂防3法という呼び方がされています。
なお、土砂災害関連の法律と言えば「土砂災害防止法」というものもありますが、こちらは『砂防3法が管轄する災害が発生した場合に被害を受ける可能性が高いエリアのルールを定めた法律』となりますので、かなり性質の異なる法律であることをご理解ください。
ちなみに、砂防3法へ「土砂災害防止法」を加えたものを『砂防4法』と称しています。
ではこれにて、「地すべり等防止法とは?わかりやすく解説いたします!」の知恵袋を閉じさせていただきたいと思います。