収益物件の運用を行っている方にとって、最も気になるはやはり「毎月の賃料収入に関すること」かと思います。
よって、『なかなか埋まらい空室』などには非常にストレスを感じるものですし、「賃料の未払い」により資金繰りが圧迫されるのは非常に厳しい事態となりますので、退去にも応じてくれない滞納者に対しては『法的手続きによって、強制的に立ち退かせるしかない』のが実情でしょう。
そこで本日は「賃貸強制退去の流れを解説いたします!」と題して、賃料滞納による物件の明け渡し訴訟、そして強制執行に至るまでの流れをご説明して行きたいと思います。

強制執行までの流れ
では具体的に「物件の明け渡しまでの流れ」をご説明して行きたいと思いますが、強制執行に至るまでには
- 賃料滞納の発生
- 合意解約等に向けた話し合い
- 明渡訴訟の提起
- 強制執行の申立て
- 強制執行の断行
以上のような段階を踏んでいく必要がありますので、以下でその詳細を解説していきましょう。
賃料滞納の発生
賃貸強制退去の「第一歩」となるのが『賃料の滞納』となります。
もちろん、賃料滞納以外にも契約違反などを理由に賃貸借契約が解除されるケースはありますが、借地借家法においては徹底して借主が保護されますので『賃料滞納以外の強制退去はレアケース』となるでしょう。
さて賃料の滞納が発生すれば、まずは
- 借主への督促
- 連帯保証人への督促
- 賃貸管理会社への連絡
- 賃貸保証会社への連絡
などを行って行くことになります。
なお、督促に際しては
- 電話連絡
- 内容証明郵便での督促
- 物件への直接訪問
などを行うことになりますが、借主や連帯保証人に関して
- 全く連絡がとれない
- 支払いの意思が認められない
という場合には、一気に「明渡訴訟の提起」を行うことになります。
これに対して、しっかりと大家側からの連絡に対応し、遅れながらも定期的に賃料の支払いが行われている「借主」については、次項の合意解約等に向けた話し合いを行うことになるでしょう。
合意解約等に向けた話し合い
さて、賃料滞納は解消できないものの真摯な対応をする借主については、まずは話合いの場を設けて
- 毎月の賃料に滞納分を分割で上乗せして、正常化を図る
- より賃料の安い物件への引っ越し(合意解除)を勧める
といった方向へと誘導していくことになります。
なお、分割払いで正常化を図る場合には「覚書などの文書を取り交わして支払いスケージュール明確に取り決める」ことが重要でしょう。
また、合意解除を進める場合も
- いつまでに物件の引渡しを完了するか
- 解約後の滞納賃料の支払いスケジュール
- 原状回復費用の精算方法
などを取り決めた文書を取り交わす必要があります。
そして、こうした約束事が無事に守られればなにも問題はありませんが、これが履行されない場合には明渡訴訟の提起を行うことになるのです。
明渡訴訟の提起
ここまで解説してきたような努力を行っても、問題が解決できない場合には法的手段に訴えるしか方法はありません。
そこでまずは、内容証明郵便などで借主へ「賃貸借契約の解除」を通知しましょう。
そして、ここからは物件の明渡しを求める訴訟の準備を進めていくことになりますので、通常は弁護士や司法書士などの法律家を代理人とするケースが多いかと思います。
また、賃貸保証会社が介在している場合には「全てをお任せできる」とお考えの大家さんが多いのですが、訴訟において原告となれるのは『あくまでも貸主のみ』となりますから、弁護士費用等は負担せずに済むものの、訴状への署名捺印等の作業は自ら行わねばなりません。
ちなみにここで、明渡訴訟に関する法律な周辺知識をご紹介しておきましょう。
明渡訴訟に勝訴して、裁判所の退去命令に借主が応じない場合には「強制執行」という方法で、貸主は物件の引渡しを受けることが可能となります。
そもそも強制執行とは「個人間の紛争においてどうしても解決できない事柄について国家権力が介入する制度」であり、その強制力は非常に強いものとなるため、厳格な法的根拠と手続きを必要としているのです。そして、強制執行を可能にするために入手しなれなければならないのが、
- 債務名義
- 執行文
- 送達証明
の3点となります。
但し、送達証明については「間違いなく相手方に強制執行を通達した旨の証明」に過ぎませんし、執行文は「現在も強制執行が行える状態にある」という裁判所のお墨付きとなりますから、その取得にそれ程手間は掛かりません。
これに対して「債務名義」は、
- 裁判所の明渡しを命じる判決に背いた場合
- 裁判による和解条件が反故にされた場合
- 調停による合意内容を覆された場合
といった条件を満たさなければ入手できませんから、如何に債務名義を手に入れるかが「最大の難関」となる訳です。
よって、明け渡しの強制執行を行うのであれば、
まずは「賃料の不払いなどを原因とした立ち退き訴訟を提起して勝訴する」か、「民事調停で約束を破った場合には立ち退く旨の合意を得る」ことが必要
となる訳です。
そして「判決」や「調停での合意」に相手が従わない際には、債務名義を入手することが可能となり、その後は裁判所で「執行文」を付けてもらった上、「送達証明書」を入手することでようやく強制執行が可能となります。
★当ブログ管理人執筆の電子書籍(kindle)のご紹介!是非ご一読ください!★
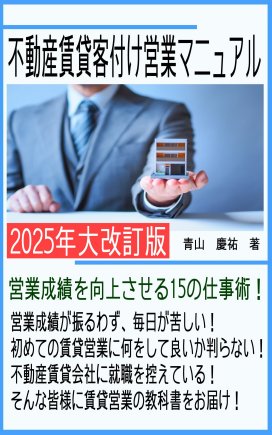 | 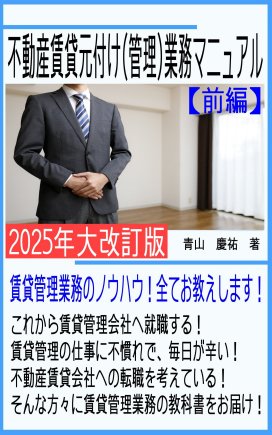 | 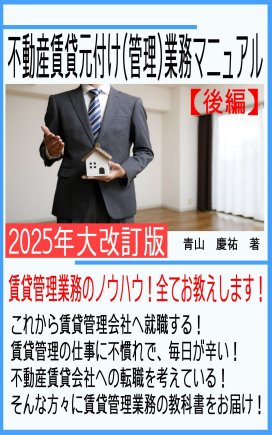 |
強制執行の申立て
さてここからは、実際に強制執行を行う手順となりますが、まずは対象の物件が所在する地域を管轄する裁判所へ出向き、強制執行の手続きを行います。
この手続きが完了すると、
「執行官」と呼ばれる公務員と具体的な強制執行の手順の打ち合わせが始まる
ことになるでしょう。
なお「執行官」という名の通り、ここで打合せを行う相手は『執行を統括する者』となる訳ですが、彼らが直接物件内の荷物を搬出してくれる訳ではありません。
実際の作業は「執行補助者」と呼ばれる業者が行うことになるのですが、この業者は『執行の申立てをする本人が手配するルール』になっています。(もちろん業者の利用は有料となり、費用は申立人負担です)
ちなみに、執行補助者に心当たりがない場合には執行官に申し出れば「業者の紹介をしてもらうことが可能」です。
そして実際に執行日(断行日)が決定すれば、
その1ヶ月以上前に「明け渡しの催告」というイベント
が待っています。
これは執行官と共に物件に赴き、相手方に強制執行による退去が行われる旨を通知するというものですが、通知を貼り出す場所は物件内部となりますから、合鍵がない場合などは鍵屋さんの手配も必要となるでしょう。
一方、この段階で起こり得るトラブルとしては、物件に出向いた際に「全くの第三者が物件を占有している」というパターンです。
こうしたトラブルは、
強制執行を察知した入居者が執行を妨害するため、物件の「又貸し」を行った際に発生する
ものとなります。
こうなると、その第三者に対して改めて強制執行の手続きを行わなければなりませんので、これは非常に手間の掛かる作業となるでしょう。
そのようなトラブルを避けるためには、強制執行前に裁判所に対して「占有移転禁止の仮処分(又貸しを禁じる法的処置)」を行っておくことが必要ですから、この手続きも忘れずに手配しておくのがお勧めです。
強制執行の断行
さて、こうして断行日を向かえれば、執行官、執行補助者、立会人(こちらも執行官に紹介してもらえます)、そして大家さんにて物件を開錠し、入居者の排除と荷物の処分を行うことになります。
なお、ここで撤去した荷物は一定期間倉庫などで保管した後で競売に掛けられることになりますが、実際に買い手が現れることはありませんので大家さんが自ら競落して、処分することになるでしょう。
そして最後は鍵の交換を行って強制執行は完了することとなり、大家さんは原状回復工事を行って、新たな入居者募集を行うことになるのです。
スポンサーリンク
賃貸強制退去の流れを解説まとめ
さてここまでが、立ち退きの強制執行の具体的な流れとなります。
正式な手続きを踏めば、確実に物件を明け渡させることが可能となりますが、裁判費用や運搬費、撤去した家財などの処分費などの費用もそれなりに掛かる上、時間もかなり要してしまうのが現実です。
また、強制執行を前に絶望した入居者が自ら命を絶つというケースも多いですから、断行には細心の注意が必要となるでしょう。
ちなみに入居者が強制退去に刃向った場合には公務執行妨害で逮捕されるケースもありますし、「どうしても行く所が無い」という入居者に対しては、執行官が公営の宿泊所などを手配してくれるケースもありますから、トラブルや最悪の結果を避けるためには、こうした制度を充分に相手方に説明しておく必要があります。
なお、大家さんの中には絶望した入居者が凶行に及ばないためのケアとして、物件管理を任せる不動産屋さんを介して「見舞金」などという形で現金を渡す方もおられるようです。(あくまで不動産屋からの見舞金として渡すのですが)
このようなお話をすると『随分甘いことをするな」と思われるかもしれませんが、物件内で事故を起こされればその損害は莫大なものとなりますし、申立てをした本人が現金を渡すのも問題がありますから、この方法はなかなか配慮の行き届いた対処と言えるでしょう。(見舞金を元手に夜逃げをしてくれれば、荷物の処分費を安く上げることができるので大家さんにもメリットがあります)
ではこれにて、「賃貸強制退去の流れを解説いたします!」の知恵袋を閉じさせていただきたいと思います。