「不動産に関する資格」と言われて、一番最初にイメージされるのが『宅地建物取引士』なのではないでしょうか。
そして、この「宅地建物取引士」の資格は不動産に係わる仕事をするのであれば「必携」とも言えるものですし、アパート経営をされる大家さん、不動産投資家の方にとっても取得しておくと『非常に大きなメリットのある資格』とされているのです。
そこで本日は、宅地建物取引士の資格と勉強について解説いたします!」と題して、不動産会社への就職や、本格的に不動産の運用や投資を行いたい方におすすめの国家資格の概要と、試験対策についてお話ししてみたいと思います。

宅地建物取引士の資格とは?
さて、不動産を扱う者にとって必要不可欠とされる宅地建物取引士ですが、具体的にはどのような資格なのでしょうか。
「宅建士」の略称でもお馴染みのこの資格は年に一度の試験に29万人もの受験者が殺到する人気の国家資格となります。(合格率は17%程度と言われています)
そして、この資格は有する者は、
- 不動産取引あたっての重要事項説明
- 35条書面(重要事項説明書)への記名
- 37条書面(売買契約書など)への記名
以上の3点の業務を行うことができます。
賃貸でも売買でも、不動産の仲介を行う際に必ず「借り手」や「買い手」に対して行わなければならないのが、物件に対する重要な事柄を説明する「重要事項説明」であり、この説明を行った上で、重要事項説明書に記名を行うことは『宅建士の独占業務』となっているのです。
また、重要事項説明の後は売買契約書等(37条書面)を取引の当事者が取り交わすことになりますが、仲介業者が取引に介在する場合には『37条書面にも記名が必要』であり、これも宅建士のみが行える業務となります。
さて、このようなお話をすると「不動産会社に就職するだけなのに、そんな資格が必要なのだろうか」というお声も聞えて来そうですが、
国土交通省の許可制となっている宅建業の免許取得には、会社に一人以上の専任の宅建士が必要と定められている
ので、不動産会社としては『宅建士の確保が最優先事項』となっているのです。
更に、将来的に不動産業での独立を考えるならば、宅建士の資格はどうしても取得しておきたいところでしょう。
一方、アパートを経営される方や、不動産投資家様にとっては宅建士の資格を取得することで不動産に対する知識が深まり、投資・運用の幅も広がるはずですから、ここは是非試験にパスしておきたいところです。
また、宅建士合格後に不動産の免許を取得すれば、
- レインズで自由に物件検索が可能になる
- 物件を何度転売しても法令違反とならない
- 自分でレインズに物件情報を載せ、自力で空室が埋められる
- 自力で空室を埋めることで、管理会社に支払う広告宣伝費が不要となる
といったメリットがありますから、これは非常に魅力的ですよね。
そして、こうした理想を叶えるためにも、「まず行うべきは宅地建物取引士の資格取得」ということになる訳です。
※宅建士になるためには試験合格後に自治体への登録が必要であり、この登録には「2年以上の実務経験」または「実務登録講習の修了」が要件となります。
★当ブログ管理人執筆の電子書籍(kindle)のご紹介!是非ご一読ください!★
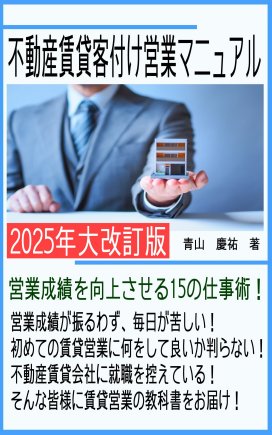 | 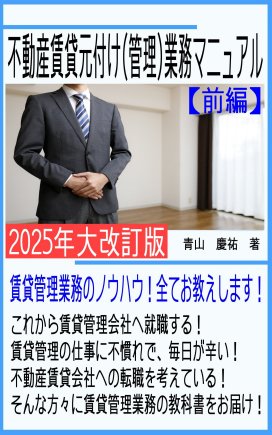 | 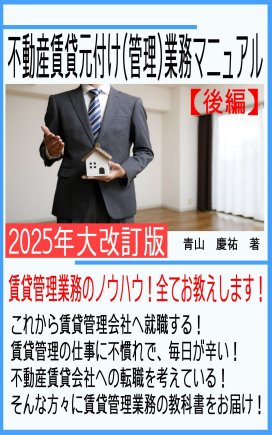 |
宅建士試験合格のポイント
では、宅地建物取引士に試験においては一体どのような問題が出題され、どれくらいの勉強が必要なのでしょうか。
近年、宅建士試験は非常にレベルが上がって来ており、合格は狭き門となりつつあるのが現状ですが半年~1年程度しっかりと勉強をすれば決して手の届かない資格ではないはずです。
なお試験問題の構成としては全て4択で50問が出題され、年度ごとの差はあるものの
通常は30点~35点(30〜35問正解)くらいが合格ライン
となります。
そして試験は年に一度の実施となり、例年10月に試験が行われているのです。
また、各種資格の中でも非常にメジャーなものである上、不動産会社に勤務している場合には資格を保有しているだけで手当てが付くケースも多いため、その人気は「なかなかのもの」と言えるでしょう。
こうした背景から各資格試験専門のスクールには必ずといってよい程、宅地建物取引士取得用のコースが用意されていますし、通信口座なども大変に充実しています。
一方、問題の出題傾向としては、
- 民法の問題/15問(全体の30%)
- 宅建業法の問題/20問(全体の40%)
- 法令上の制限の問題/8問(全体の16%)
- その他の問題(税法、建築の知識等)/7問(全体の14%)程度
以上のような配分が恒例です。
このように書くと、何やら非常に難しそうなイメージとなってしまいますが、この資格の勉強法には少々コツがあります。
まず点数配分の30%を占める民法ですが、
受験者の多くが民法の勉強に時間を掛け過ぎ、他の分野に手が回らずに「不合格となる」
というのが王道のパターンです。
確かに民法は非常にウェイトの高い出題カテゴリーですが、あまりに範囲と奥が深過ぎるため、決して深追いしてはならない科目となります。
これに対して
「宅建業法(点数配分40%)」と「法令上の制限(点数配分16%)」は、丸暗記すれば全問正解も夢ではない、点を取りやすい科目
となっているのです。
そして残りのその他(点数配分14%)は、勉強してもまず正解できないカテゴリーと言えるでしょう。(建築に対する知識などが出題されるため、勉強する範囲が広過ぎて対応が難しい)
なお、既に解説した通り合格を勝ち取るためには、30点から35点(50問中で60~70%)の正解が必要となりますが、
「宅建業法40%」+「法令上の制限16%」=合計56%となるため、この2科目を確実に正解することができれ『ほぼ合格ラインに到達可能』
ということになるです。
後は民法を深追いせず、 基礎だけをガッチリ固めれば30%の半分である15%くらいは正解できるでしょうから、56%+民法半分15%=71%となり、余裕で合格圏内に達することになります。
世間では折に触れて「宅建士の試験は難しい」と言われますが、多くの受験者がこうした勉強のコツを知らない上、殆ど休みのない営業マンが勉強不足の状態で試験に臨むのが、難関と言われる最大の原因なのです。
よって「自分には無理だ・・・」と思われている方も、挑戦する価値は充分にありますから、この機会にチャレンジされてみては如何でしょうか。
スポンサーリンク
宅地建物取引士の資格と勉強方法について解説まとめ
さて本日は、宅地建物取引士の資格試験に関するお話をさせていただきました。
私もこの資格を持っていますが、実は取得までに2回程不合格となっています。
不動産屋さんの仕事をこなしながらですと、なかなか勉強時間が取れないというのもありましたが、「実務」と「勉強する内容」が微妙に異なっている点にもかなり頭を悩ませられた記憶があります。
また実際のデータを見てみても、不動産業に従事している方より、それ以外の主婦や学生さんの合格率が高いのが実情ですから、「不動産業のことを殆ど知らない」というのは、むしろ有利な点と言えるかもしれません。
不動産投資に必要な知識が身に付くばかりか、不動産免許の取得までも可能にする、『宅地建物取引士』の資格に是非チャレンジされてみては如何でしょうか。
ではこれにて、「宅地建物取引士の資格と勉強方法について解説いたします!」の知恵袋を閉じさせていただきたいと思います!